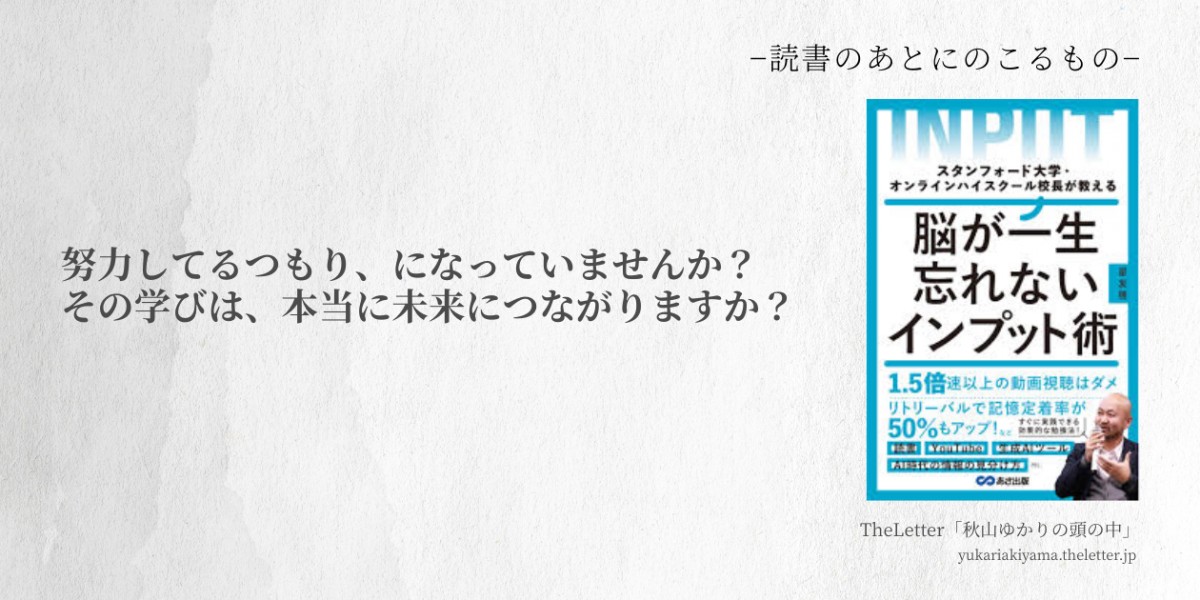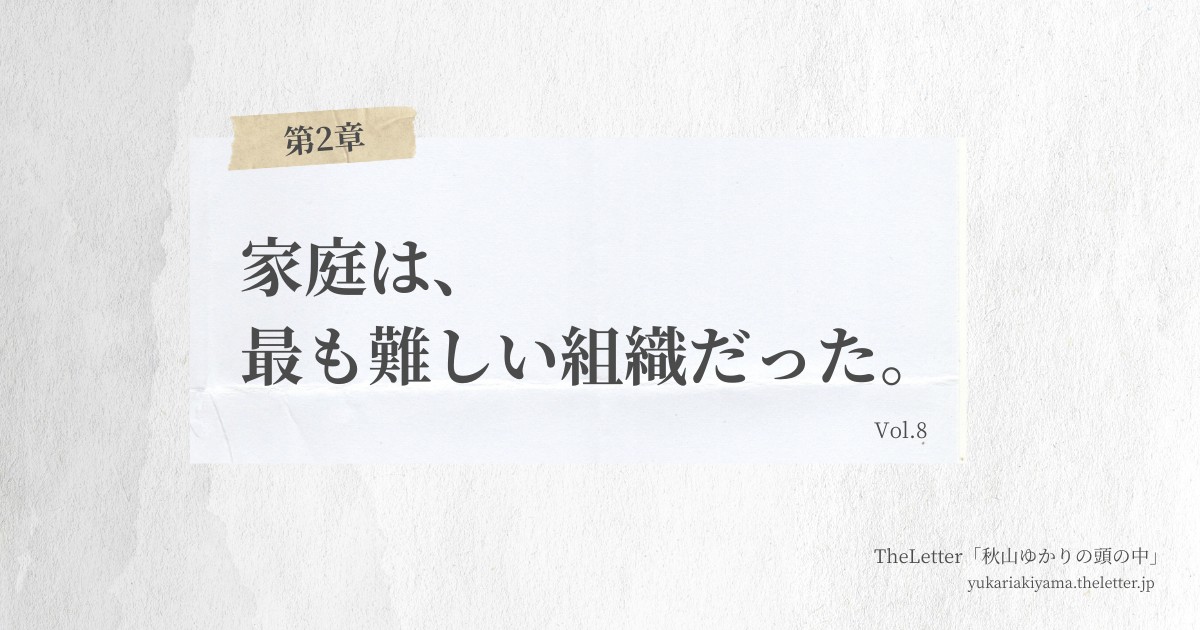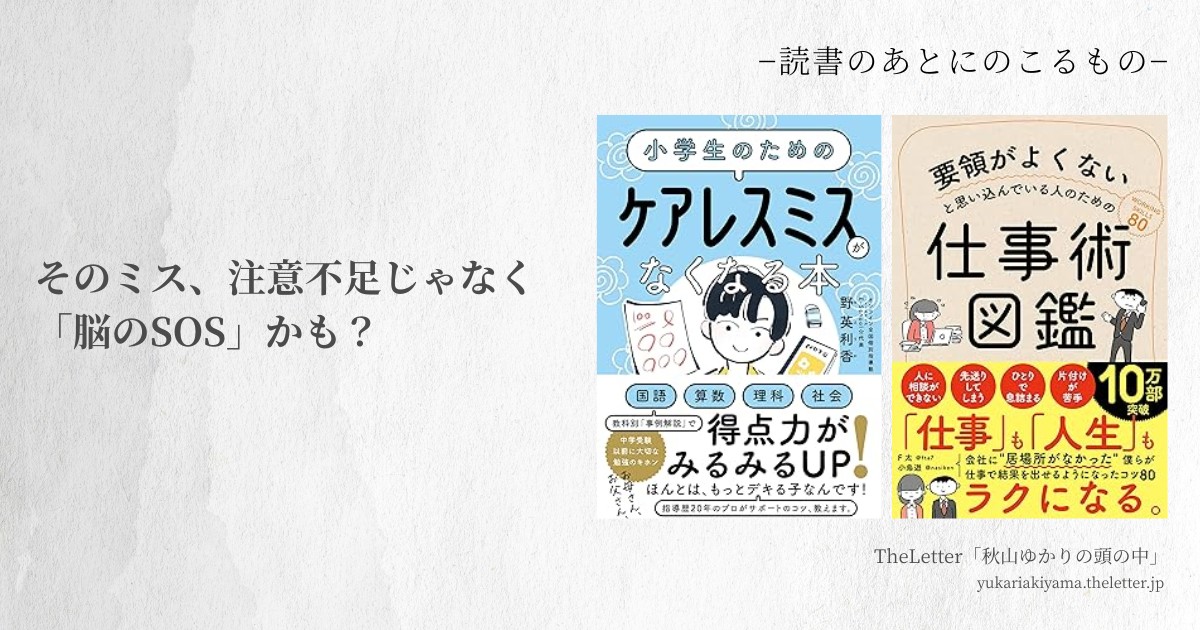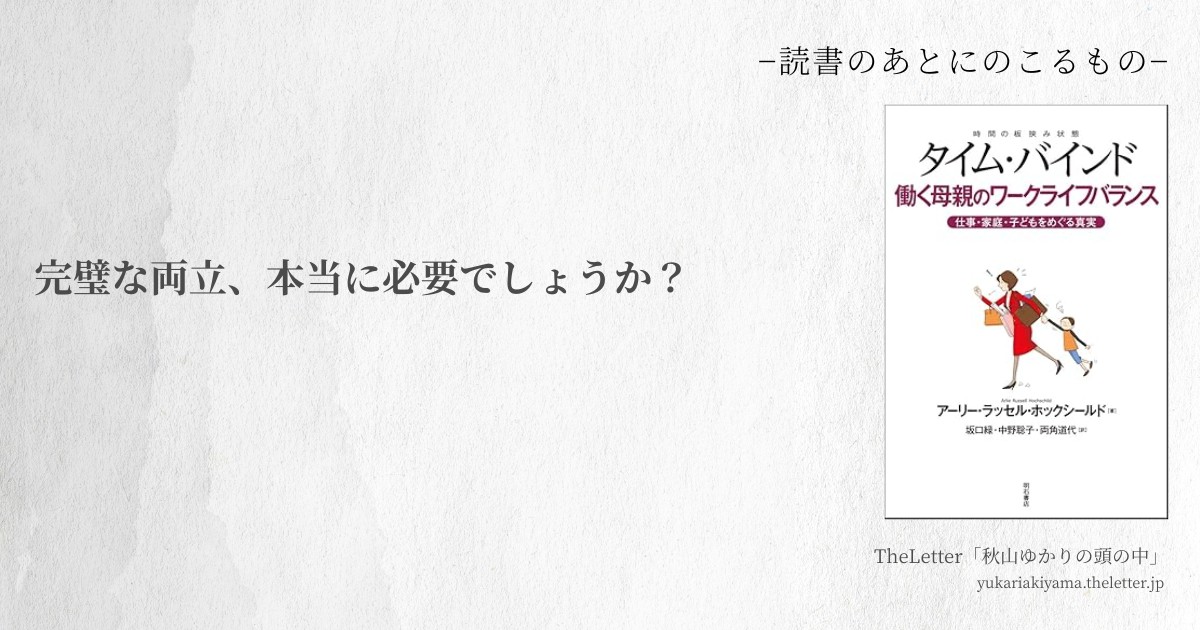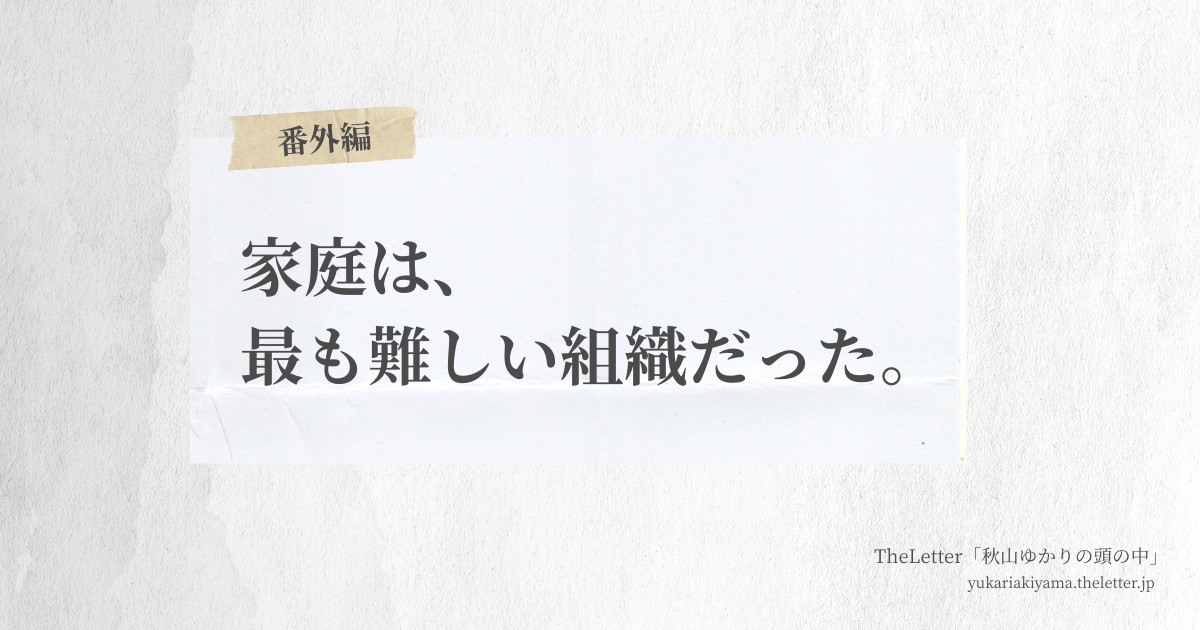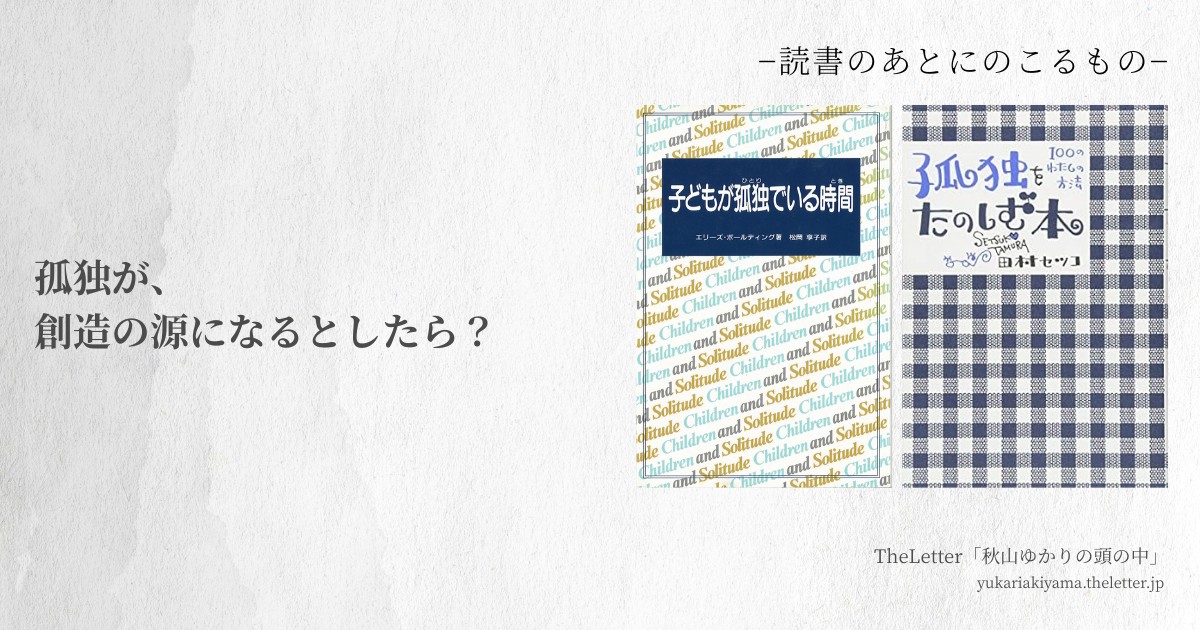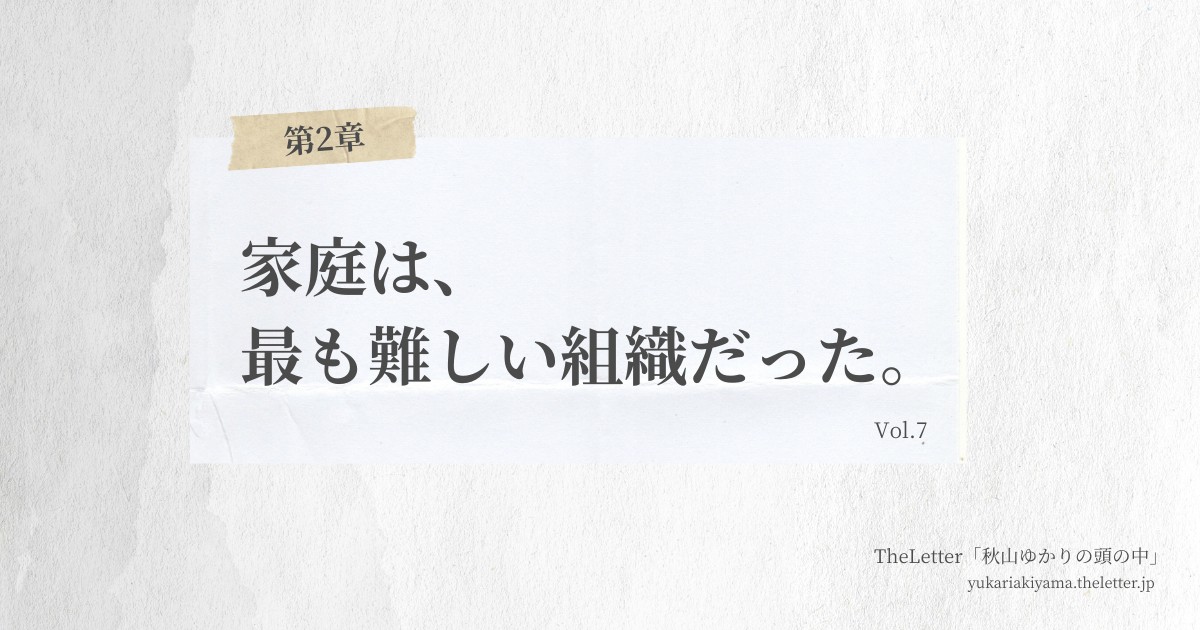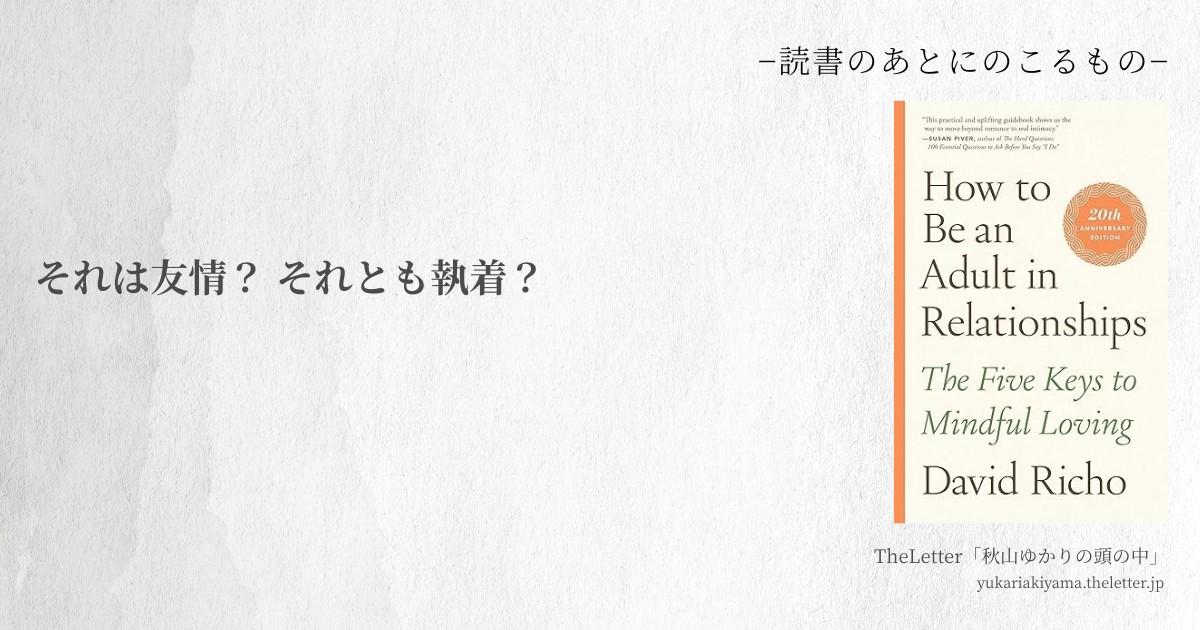「思い出す力」で未来を変える——スタンフォード流・脳が一生忘れない学び方
戦略コンサル、グローバル企業での事業開発、エグゼクティブの実務に加え、アーティスト・研究者・母の視点から発信しています。無料記事はサポートメンバーの支えで成り立っています。共感いただけた方は、ぜひご参加ください。
学ばされる子どもと、学び直す親——再発見された「記憶」の正体
「なんで覚えてないの? 昨日やったよね?」
ある晩、ムスメの算数の問題集を一緒に解いていたとき、思わず出た私の言葉です。そんな私を見て、ムスメは小さく首をかしげて言いました。「でも、やったのに出てこないんだもん……」と。
その姿にハッとしました。私たち大人も同じです。読書やセミナーで学んだはずの内容が、いざというとき出てこない。資料を読んでも、数日後には内容があいまいになっている。これは、学ぶ量の問題ではなく、学び方の問題なのではないか?
そんな問いが胸に生まれたときに再読したのが、星友啓さんの『脳が一生忘れないインプット術』でした。スタンフォード大学で博士号を取得し、オンラインハイスクール校長を務める著者が提示するのは、「やったつもり」の学びから脱却し、「一生ものの知識」に変えるための科学的アプローチです。
今回はこの本から得た気づきを、ムスメとのやりとりや私自身のビジネス・子育て・学びの現場の経験と重ね合わせながら、紹介したいと思います。
💡まとめ:この章のポイント
-
「覚えたはずなのに思い出せない」は大人にも子どもにも共通。
-
問題は“量”ではなく“学び方”。
-
「インプット術」を見直すことで、“記憶に残る学び”が可能に。
親と子で学び方はこんなに違う。スタイルをつなぐ“橋のかけ方”
ムスメの受験勉強を通して、私はある大きな発見をしました。
それは、「学習スタイルは親子でもまったく違う」ということです。
私は明らかにビジュアルラーナー(視覚学習者)で、構造的な図や色分けされたノート、イメージを活用することで理解が深まります。一方、ムスメはオーディトリーラーナー(聴覚学習者)。声に出して説明したり、オーディオ教材を使ったりするほうが記憶に残るようです。
こうした違いに気づいてから、私たちは互いのスタイルを尊重しながら学びを工夫するようになりました。たとえば、私がまとめた図やチャートを、ムスメが声に出して説明する。動画を一緒に見たあとに感想を語り合う。そんな風に、お互いの強みを組み合わせることで、一人では得られなかった“深い理解”が生まれるようになったのです。
中でも印象的だったのは、ムスメが自分で作った語呂合わせカルタを一緒に読み上げながら覚えたこと。私はその言葉のリズムを聴きながら、頭の中にチャートを描いていました。
このように、親子の学習スタイルの違いを「ズレ」ではなく「資源」としてとらえることは、学びの質を大きく変えると感じています。
学習スタイルの違いをブリッジする方法
私たちは、学習スタイルが違うからこそ、それを「ズレ」ではなく「補い合えるもの」として活かすようになりました。たとえば——
-
私が構造化したノートやチャートを作り、ムスメがそれを読み上げる。
-
教育動画を一緒に見て、ムスメが感想を口頭で語り、私はそれをメモに整理する。
-
私が図解した内容をクイズ形式で出題し、ムスメが口頭で答える。
-
ムスメが音読している間に、私がビジュアル的にまとめ直す。
こうして、視覚と聴覚、2つのアプローチを組み合わせることが、双方にとっての“記憶のブースター”になっていきました。
それはまるで、お互いの橋を架け合っていくような体験です。私の強みをムスメが使い、ムスメの強みを私が取り入れる。お互いのスタイルが混ざり合うことで、学習が“共同作業”に変わるのです。
そして何より——この工夫をしようとする過程そのものが、「私はあなたの学びに関心があるよ」という愛情のサインになっているのだと思います。
学習法の違いを、ただの相性の問題で終わらせず、親子の信頼を築くきっかけにできたのは、本書を通じて得られた大きな学びでした。
💡まとめ:この章のポイント
-
学習スタイルは個人差が大きい。親子でも異なる。
-
視覚・聴覚の違いを尊重し合うことで学習は深まる。
-
「ズレ」ではなく「資源」としてスタイルの違いを活かすことがカギ。
この記事は無料で続きを読めます
- 「やった=覚えた」は幻想だった。学びが残らない本当の理由
- 「うーん、なんだっけ?」の時間が、記憶を深くする
- 読んだそばから忘れる人へ——記憶に残る読書3ステップ
- 「できた」が「もっとやりたい」を生む。学びのサイクルの設計法
- やる気は「育てられる」。継続できる人の思考法
- 学びを続ける人は、ビジネスパーソンと同じ土台を持っている
- 動画・AI・アプリで“わかった気”になってない? デジタル時代の学びの落とし穴
- 「やる気に頼らない!続けられる学びの“仕掛け”
- 本当に効くの? 科学的学習法の“落とし穴”
- 学びは“記憶”から“変化”へ。未来につながる学び方とは?
すでに登録された方はこちら