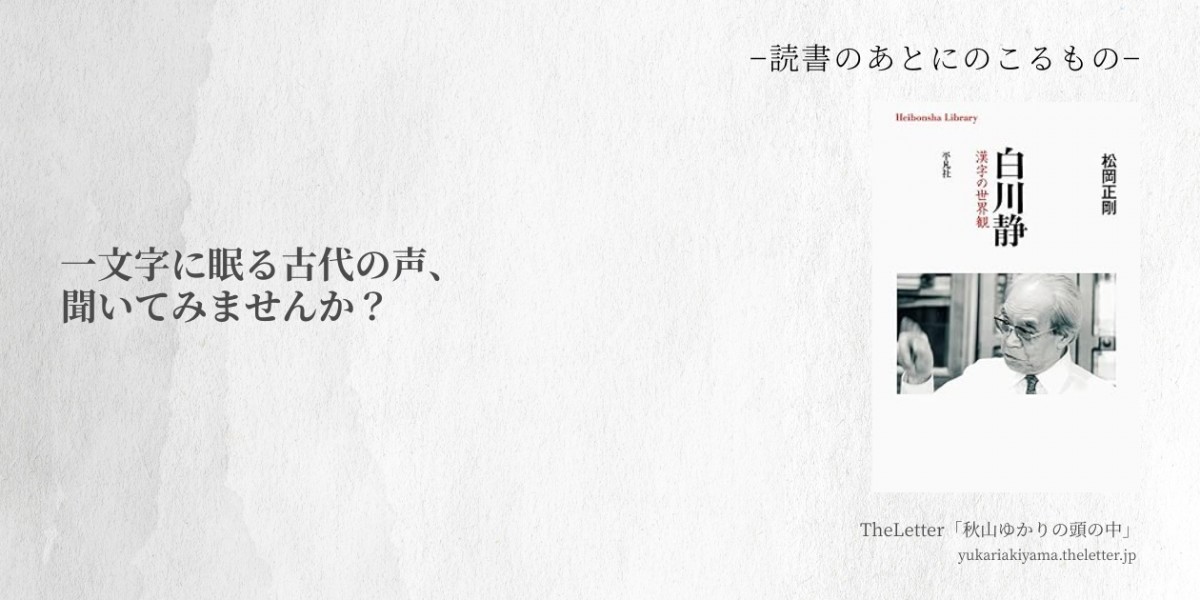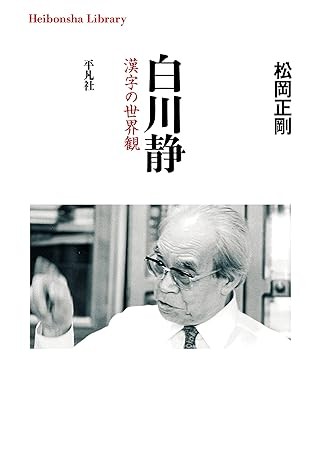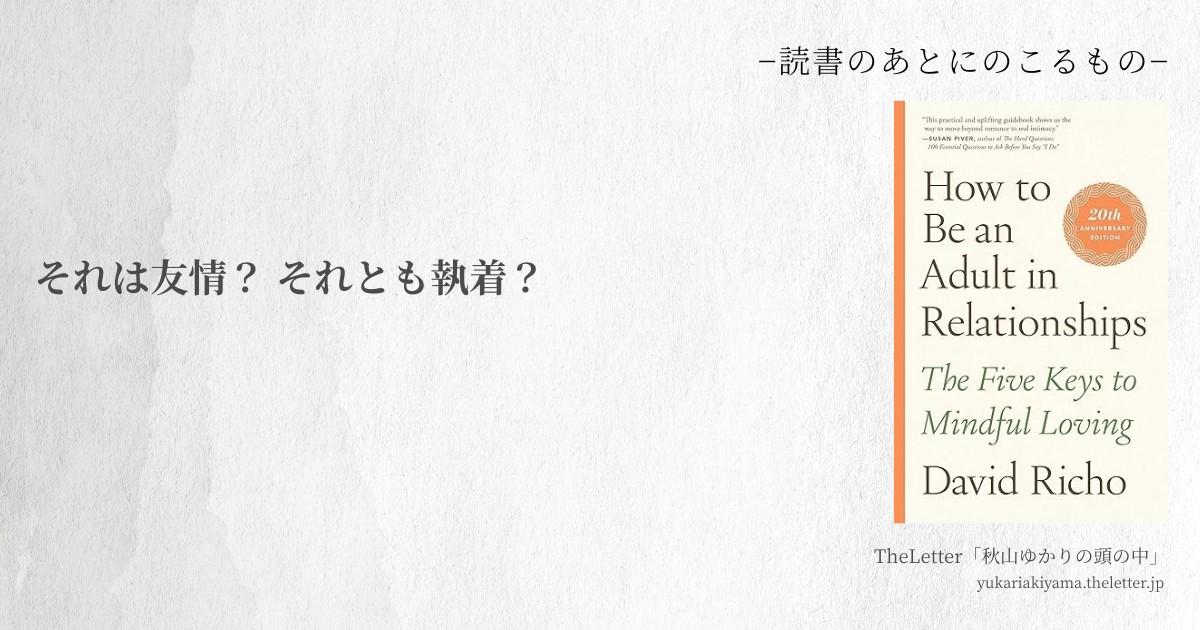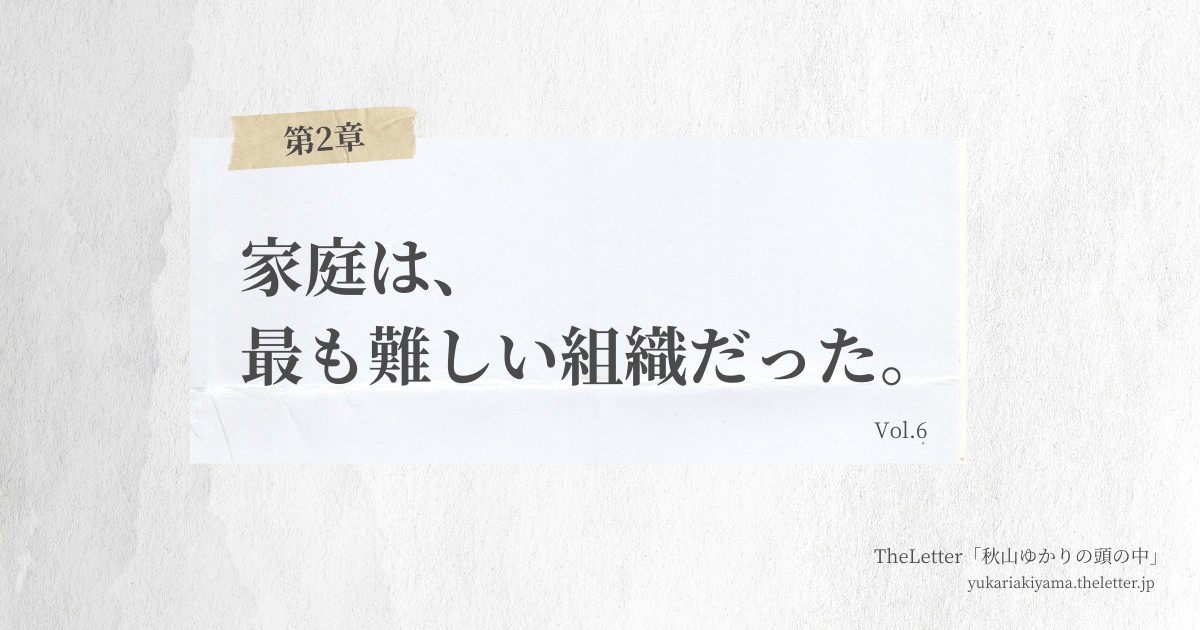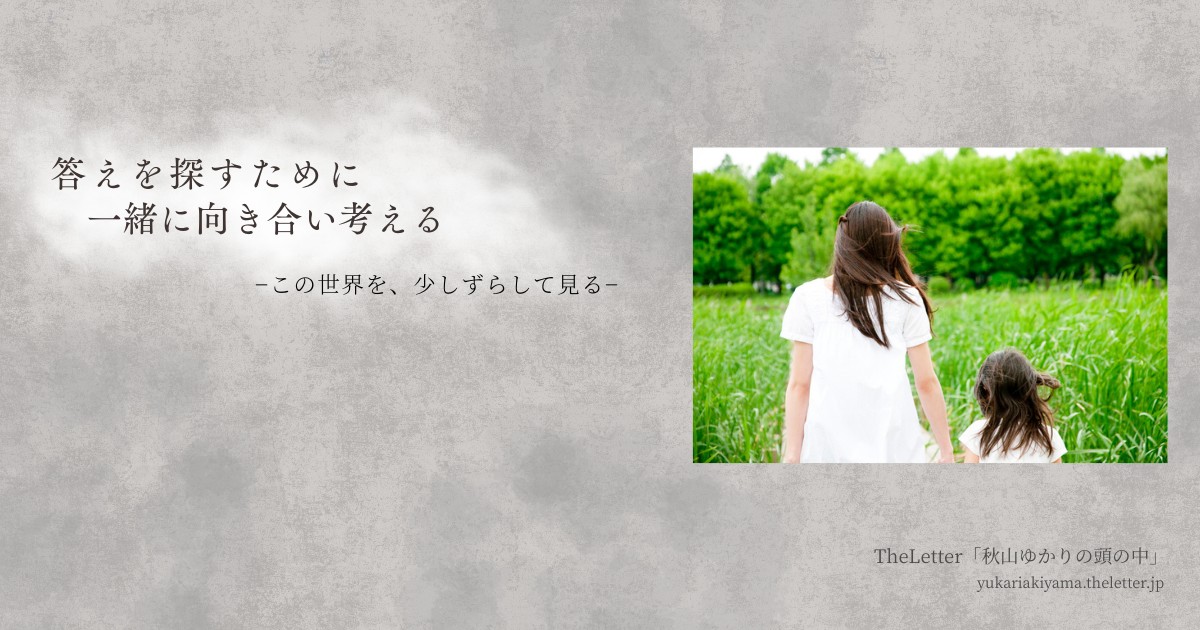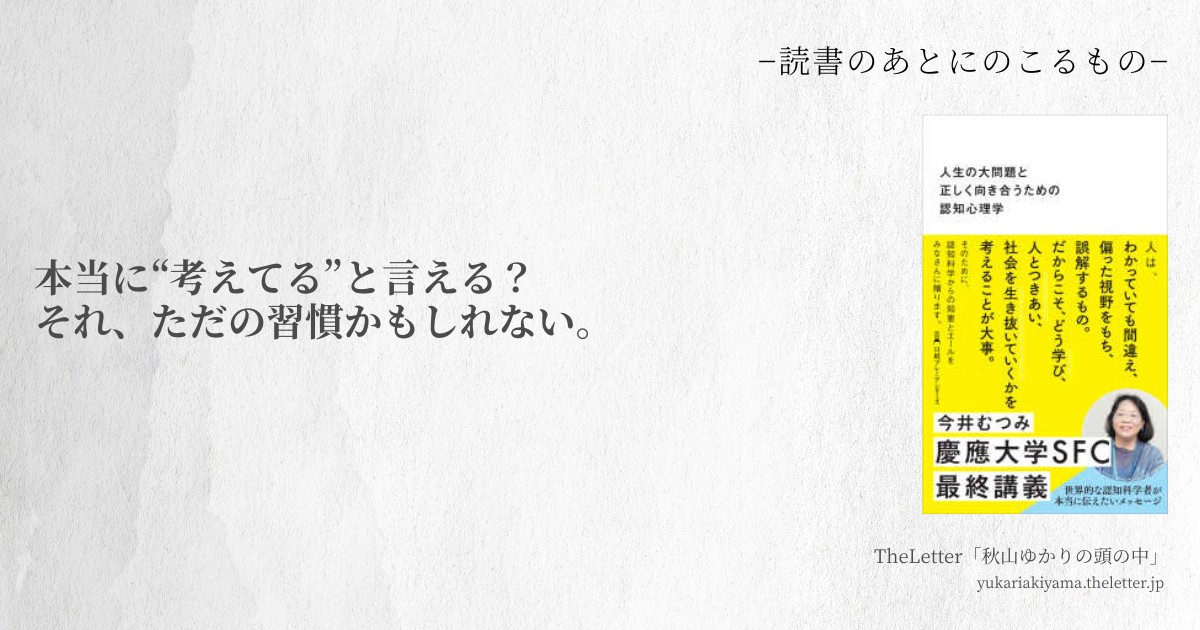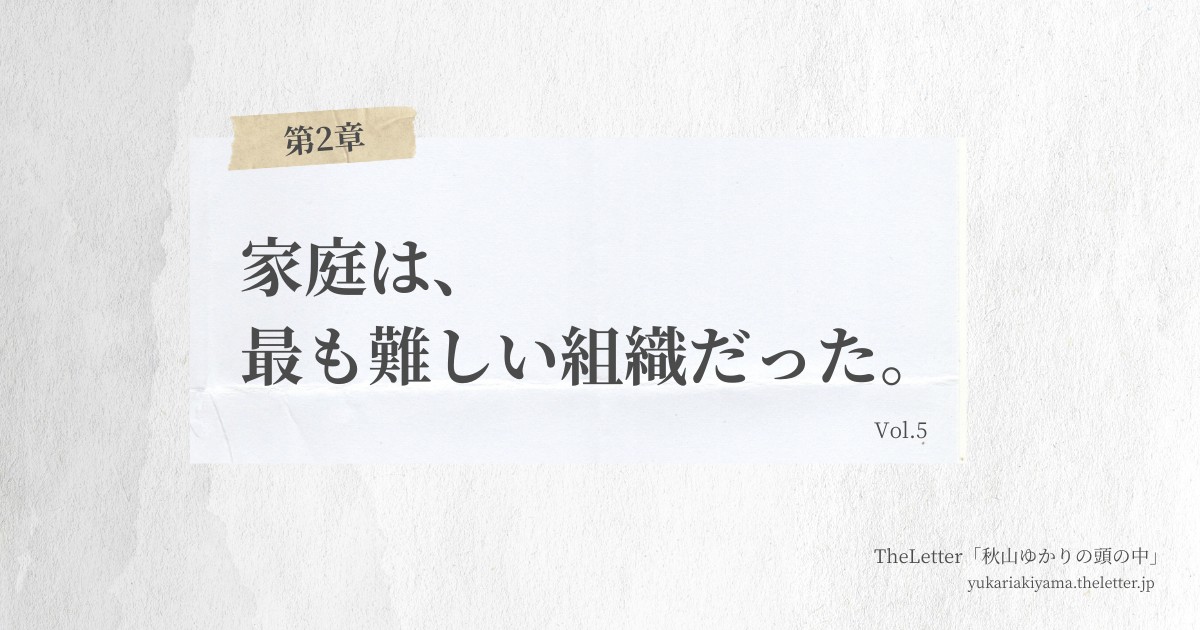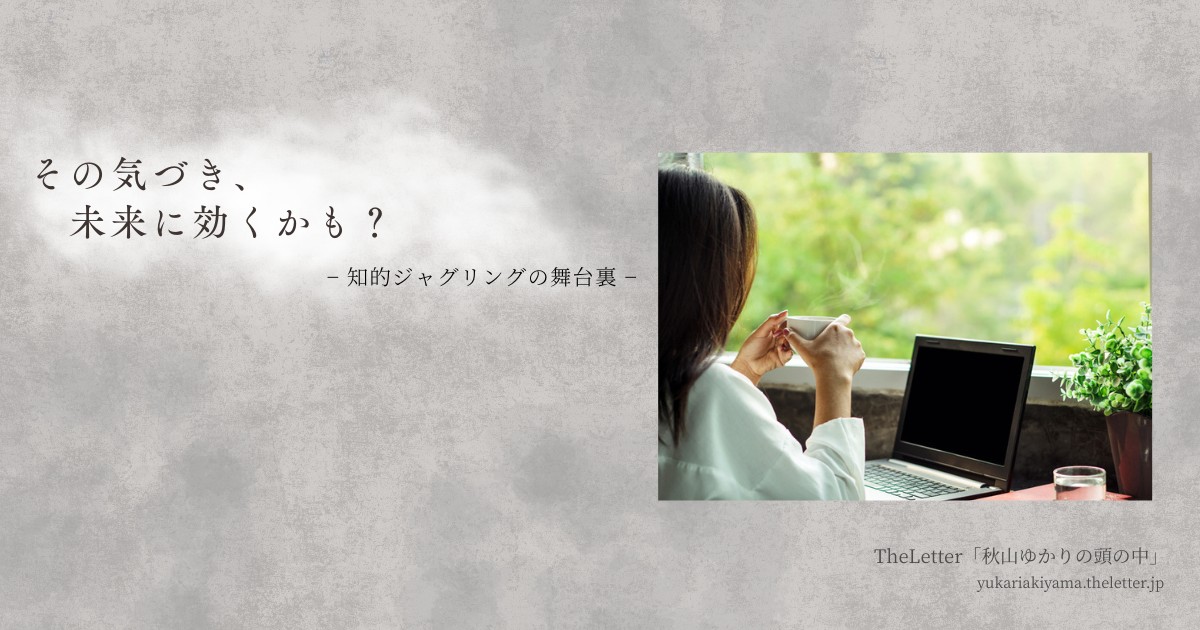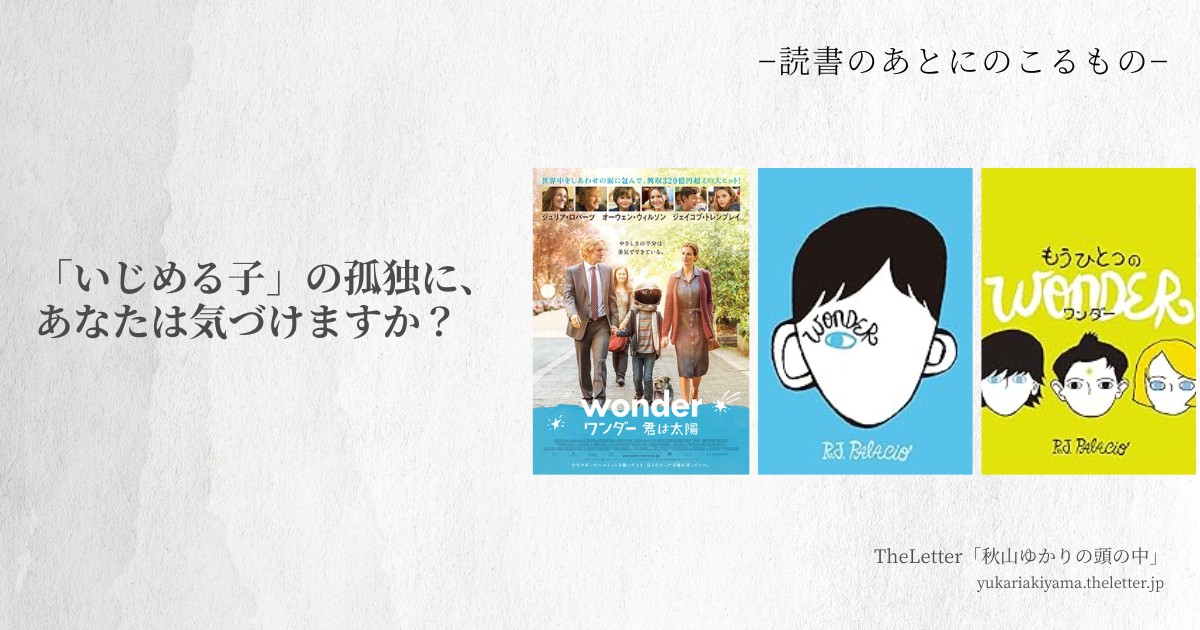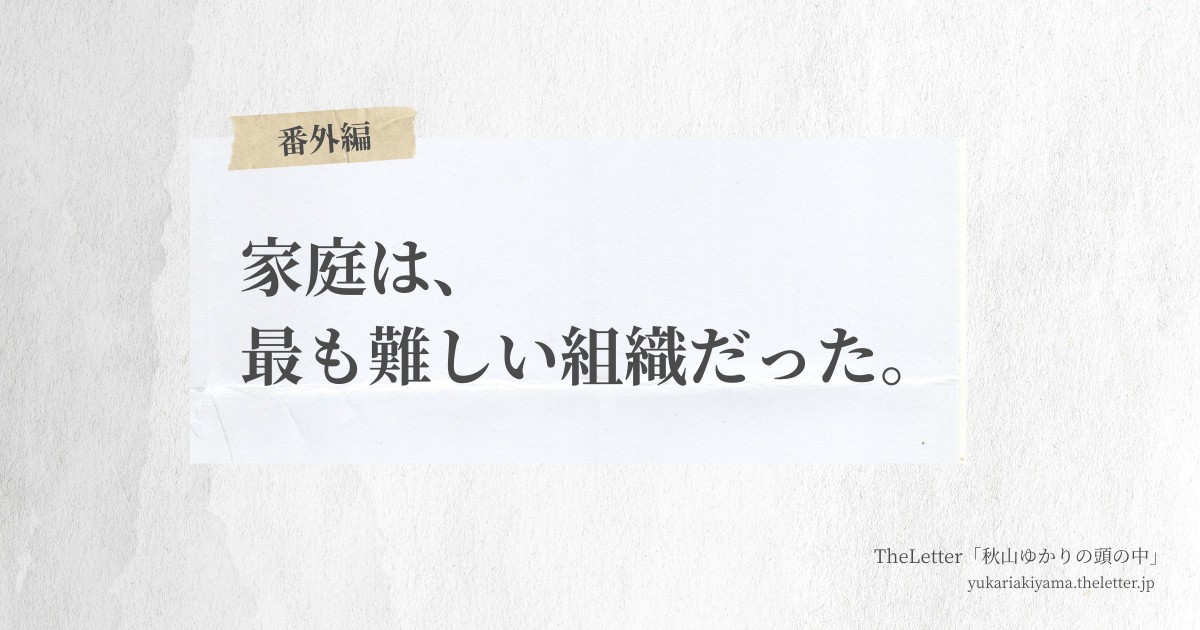漢字はこうして生まれた——白川静と松岡正剛に学ぶ古代の世界
親子で始めた漢字探訪が、古代の精神世界へと私たちを導いた。白川静と松岡正剛の知の旅から見えた文字の起源とは。
秋山ゆかり
2025.08.11
読者限定
戦略コンサル、グローバル企業での事業開発、エグゼクティブの実務に加え、アーティスト・研究者・母の視点から発信しています。無料記事はサポートメンバーの支えで成り立っています。共感いただけた方は、ぜひご参加ください。
夏のはじまり、小さな旅のはじまり
夏休みという特別な時間が流れる中で、ムスメと私は一つの小さな探究の旅に出ました。
行き先は、漢字。
日々目にしているのに、その奥行きは果てしない世界です。
きっかけは3年前。ムスメが小学校1年生になったばかりのころ、PTA副会長のKさん(国語塾を経営)に「言語理解力はあるのに漢字がうまく書けない」悩みを相談したときのこと。
「白川静さんの本、すごく面白いからムスメちゃんにおすすめよ」と言われたのが、すべての始まりでした。
その後、ムスメが小2でイシス編集学校の守に入門し、私もお守役として一緒に参加。ただのお守役のつもりが、松岡正剛さんの世界にどっぷりはまって、最終的に師範代の花伝所まで出てしまったのは、今思えば必然だったのかもしれません。
松岡正剛が描いた白川静の"知の革命"
この夏、改めて手に取ったのが松岡正剛著『白川静 漢字の世界観』。
白川静の膨大な研究を地図のように見取り図化した一冊です。
この記事は無料で続きを読めます
続きは、3504文字あります。
- 漢字に宿る"神の杖"と白川学の5つの特色
- 「国字」としての漢字と日本の創造性
- 編集学校と壁打ち、そして効率化からの解放
- 学びが日常に息づくとき
すでに登録された方はこちら