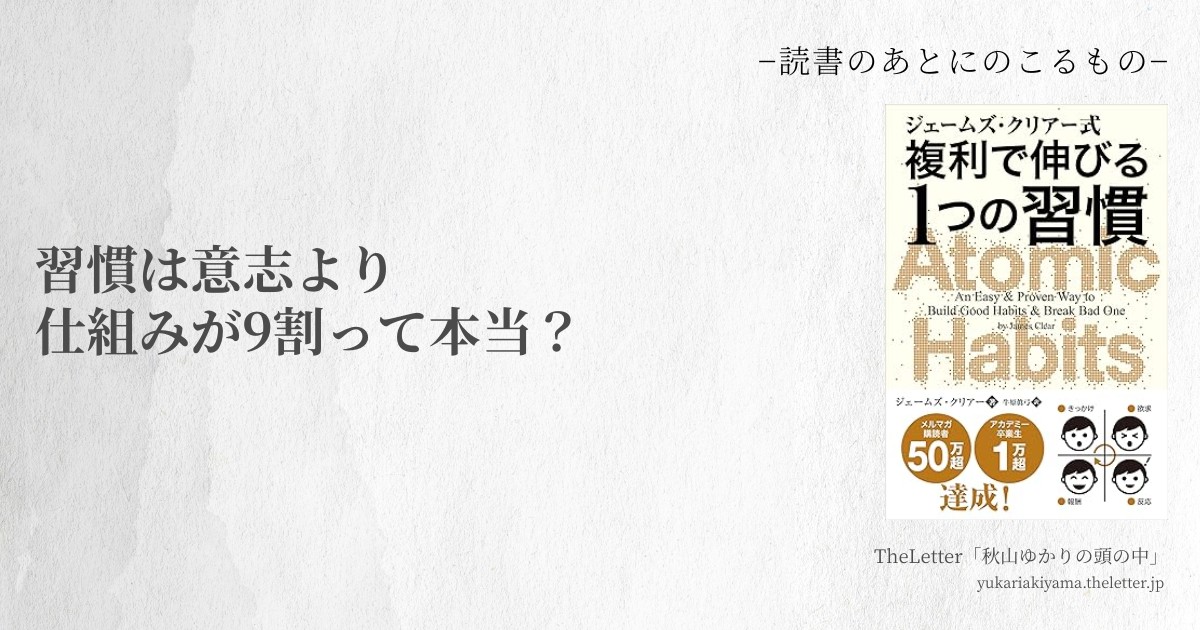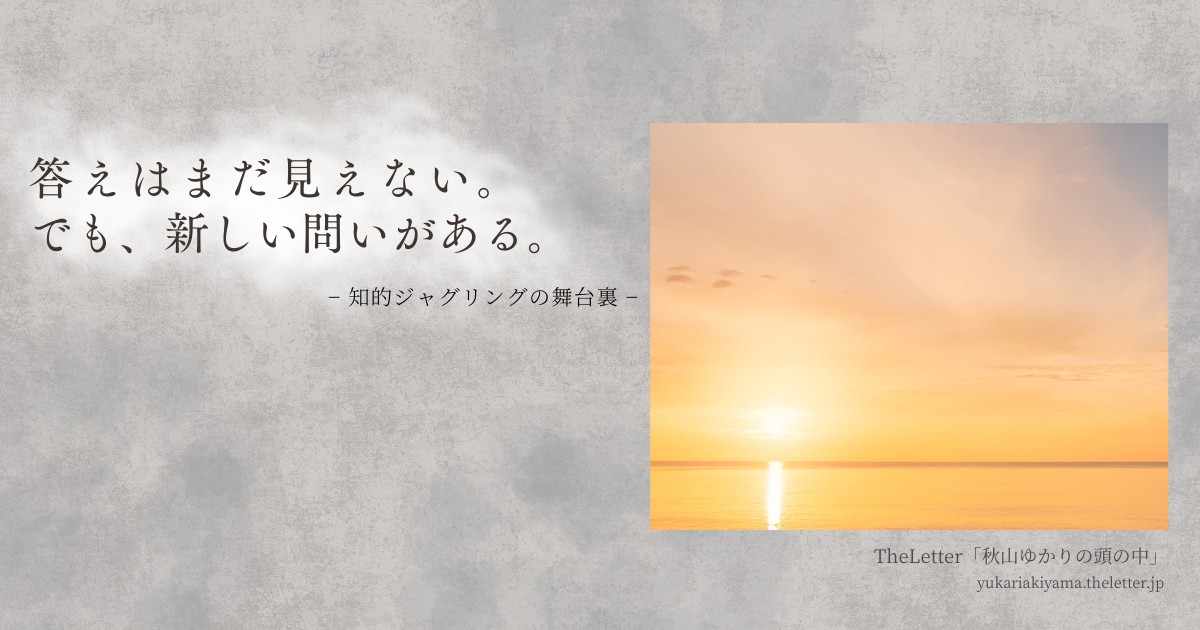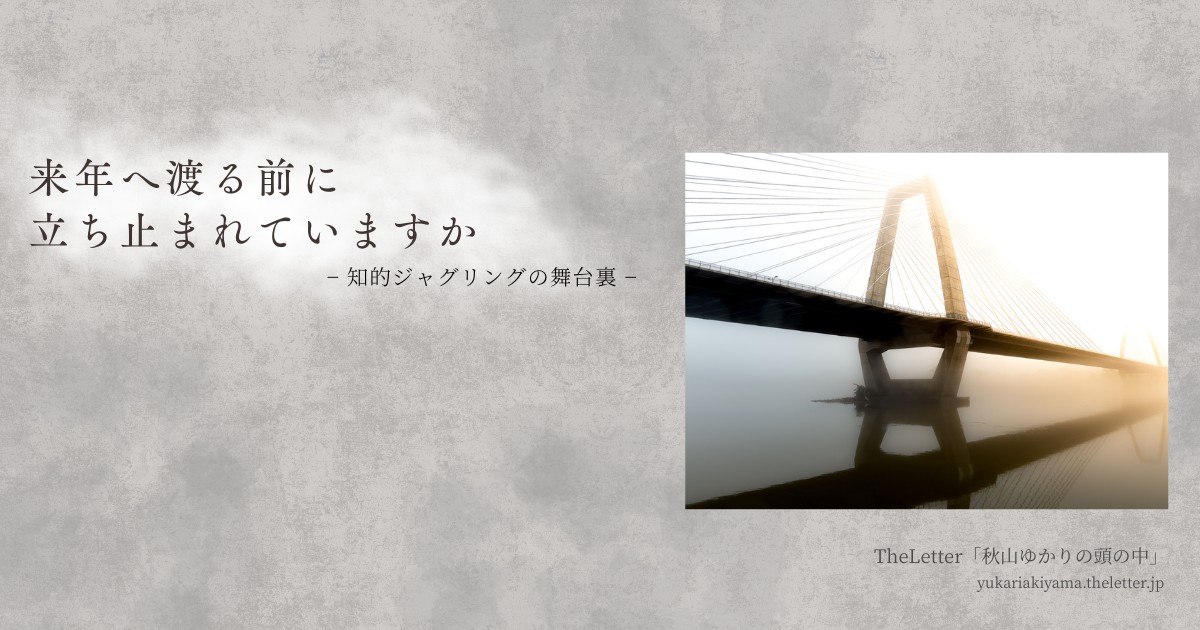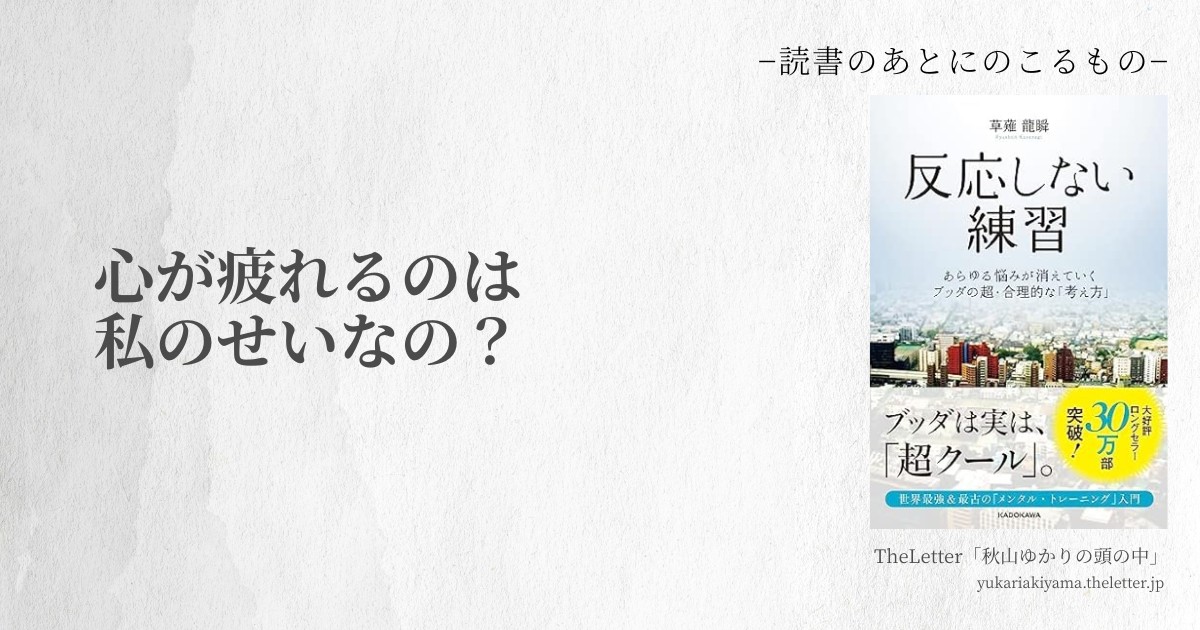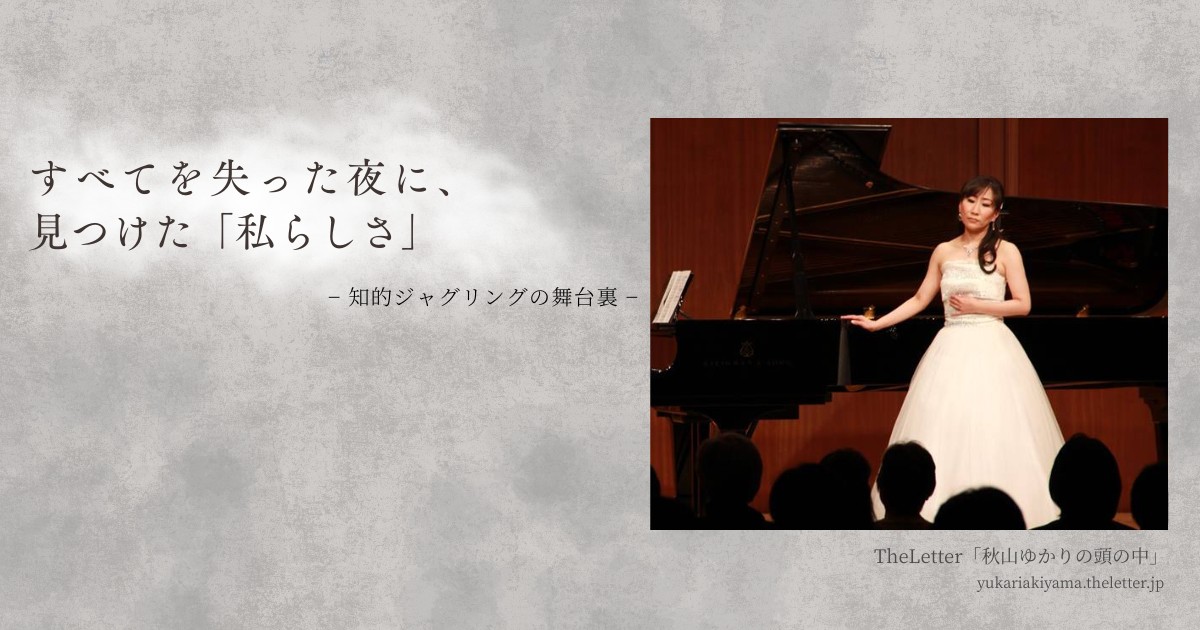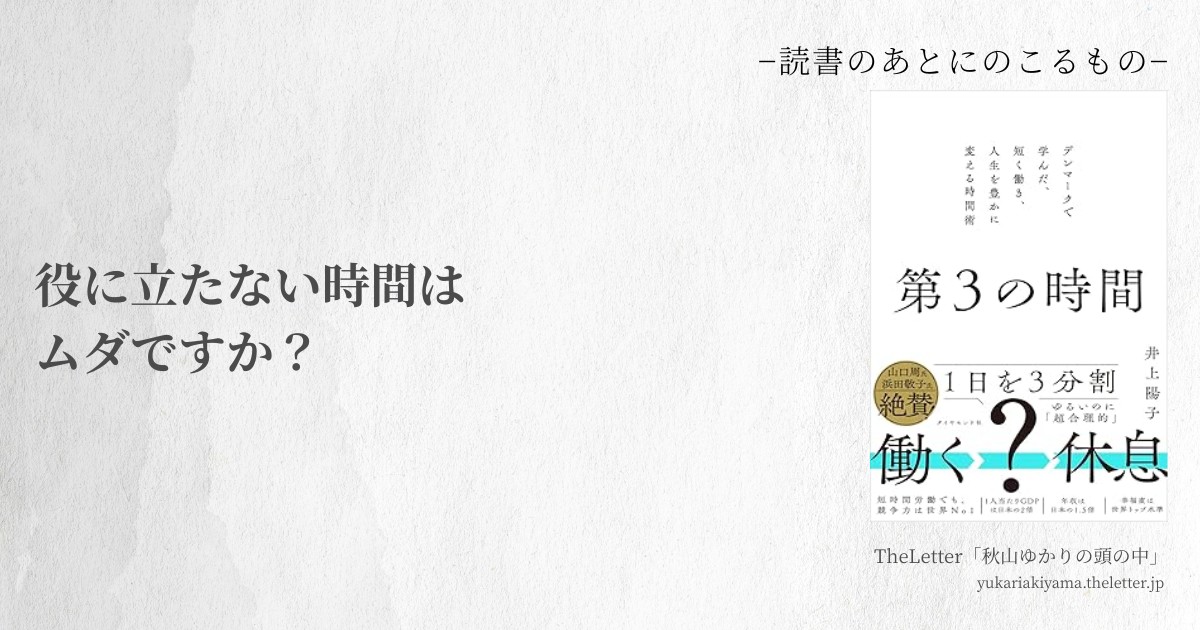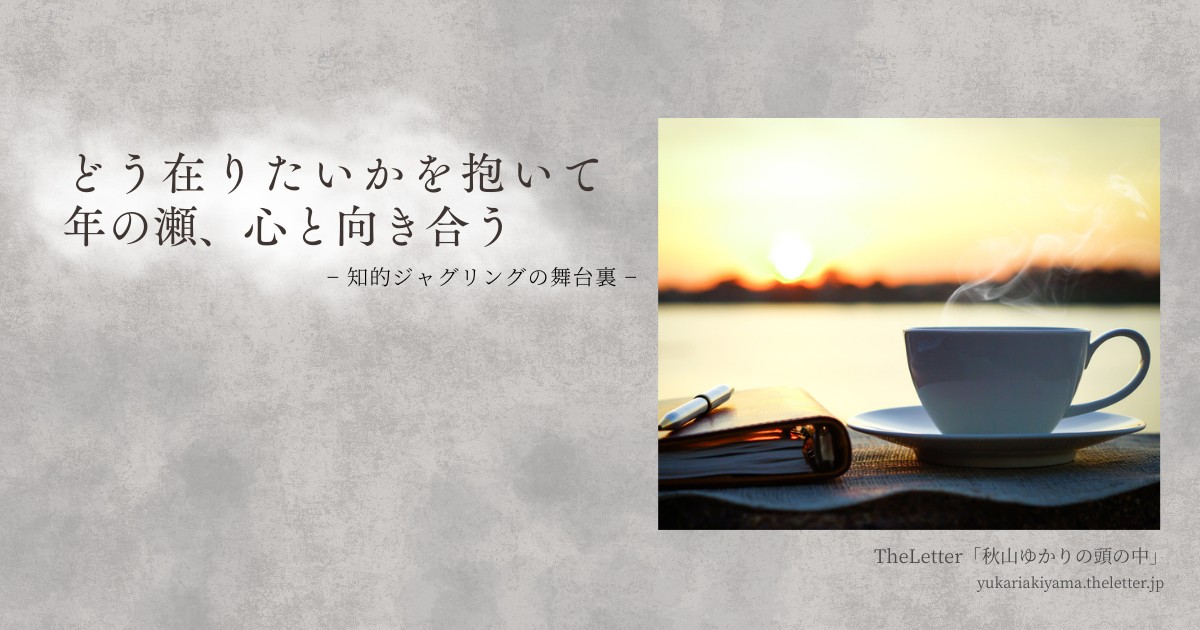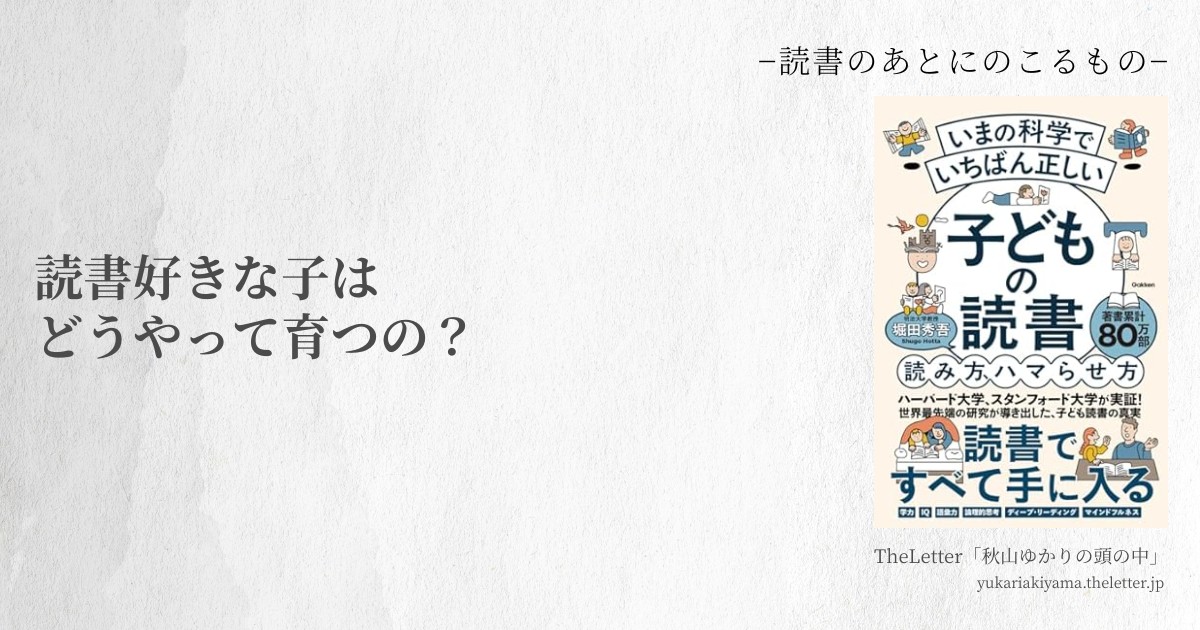緊急モード第2弾──ムスメの怪我で見えた「チーム化」の定着度

戦略コンサル、グローバル企業での事業開発、エグゼクティブの実務に加え、アーティスト・研究者・母の視点から発信しています。無料記事はサポートメンバーの支えで成り立っています。共感いただけた方は、ぜひご参加ください。
想定外のシステム障害が再び発生
皆さん、こんにちは。
先週の「ぎっくり腰編」では、夫の予想外の覚醒ぶりをお伝えしましたが、今回また緊急事態が発生しました。
ムスメが壁の角に顔面激突。
近所からクレームが出るほどの号泣で、壁まで凹む勢いでの激突でした。眼底骨折の疑いがあり、10日間の厳重な経過観察が必要な状況に。
これまでの「ワンオペ救急対応」の歴史
実は、うちのムスメは親の斜め上をいく大怪我が多い子なのです。
1歳の時:「虫さん、飛べる。鳥さん、飛べる。センセー、飛べない。あたし?」と言って2階から飛び降り。
その時に思いました。「この子は本当に命に関わることをしでかす子だ」と。 私自身の対応力も、根本からアップデートが必要だと痛感し、ムスメが1歳半の頃から上級救命講習を受け始めました。
AEDの使い方から、止血の方法、緊急搬送の手順まで。
「いつか使う日が来るかもしれない」じゃなくて、「また絶対に来る」。
そう確信していたからです。
2-4歳:頭をぶつけて脳震盪を起こすのが年中行事。石垣、塀、木に登っては上から落ちてくる。
2年生の夏:海で波返し護岸(テトラポッド)から落下。着地点に大量の貝があり、足に深く刺さって大出血。私では止血できないレベルなのに、近隣病院はすべて受け入れ不可。圧迫止血を試みながら、タクシーで高速を使って家の近所まで戻り、主治医に泣きつき、総合病院の形成外科に緊急受け入れしてもらいました。180cc出血していて(ペットボトルを傷口に当てて計測)、病院到着時には出血性ショックを起こしていました。看護師さんから「お母さん、一人でよくここまで持たせた!」と褒められました。いや、無我夢中なだけです。
これらすべて、私一人で対応してきました。
この記事は無料で続きを読めます
- 初動対応で見えた「学習効果」
- 継続的関与への意識変化
- 「やればできる」から「当たり前にやる」への進化
- システム改善の定着度測定
- 「チーム化」の本当の意味
- まだ見えない課題
- 家族PMプロジェクトの新フェーズ
すでに登録された方はこちら