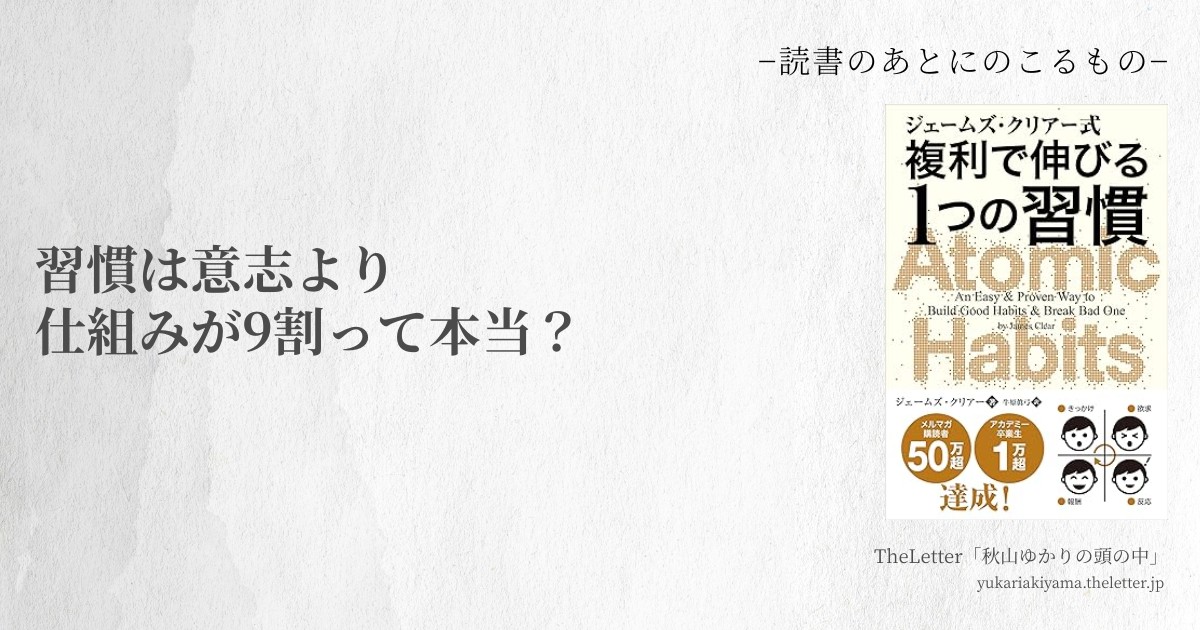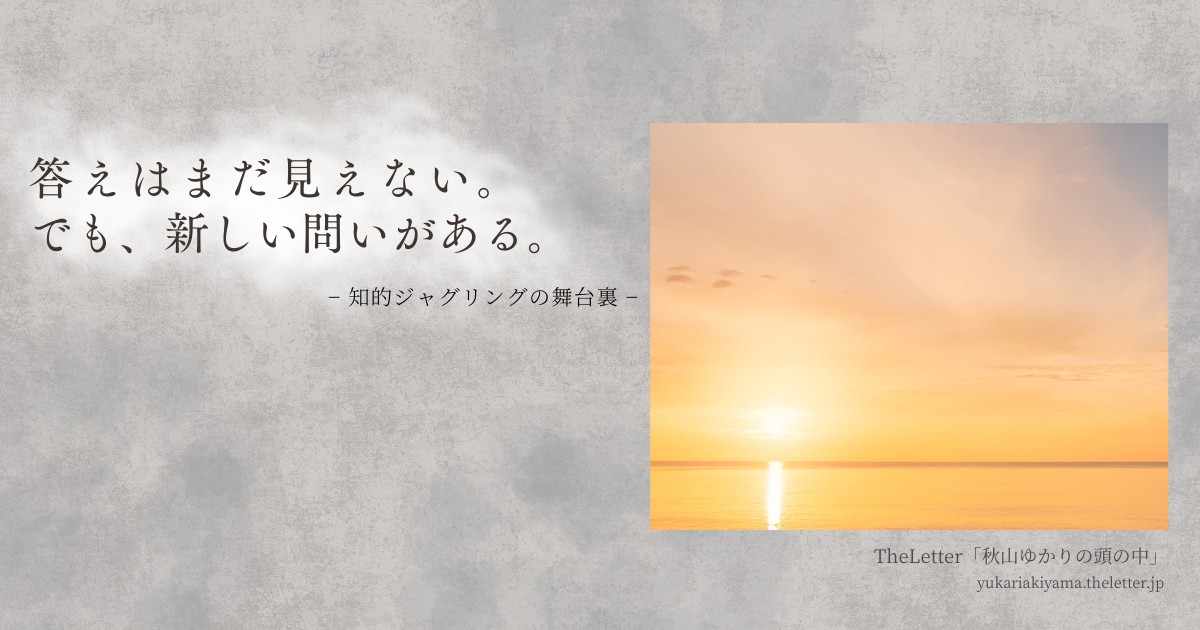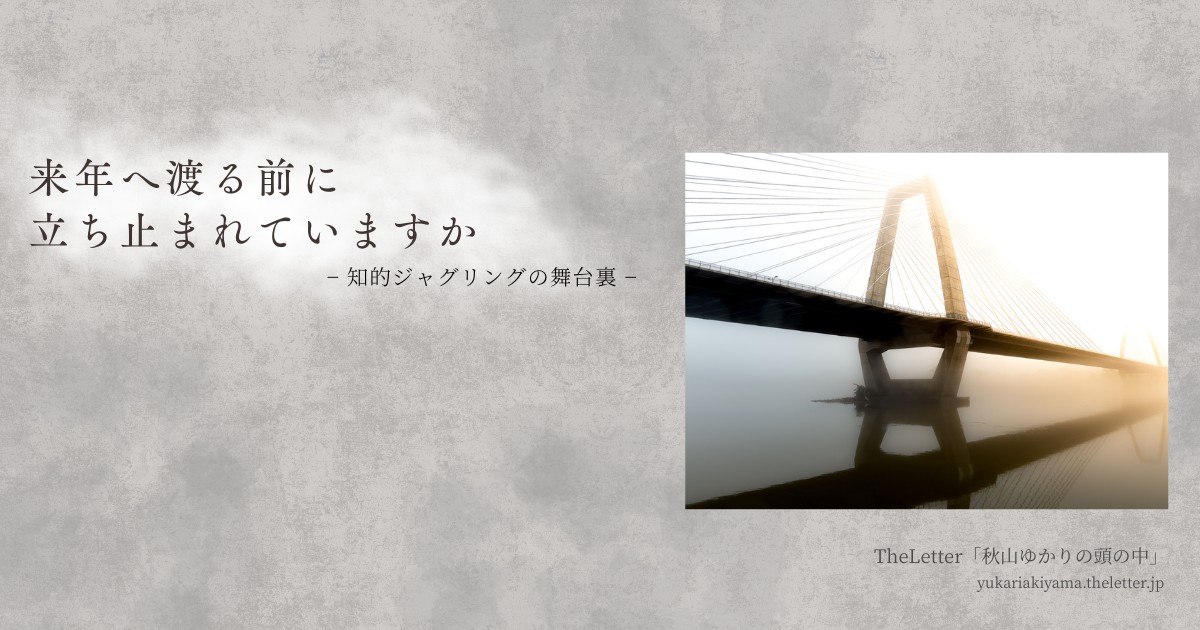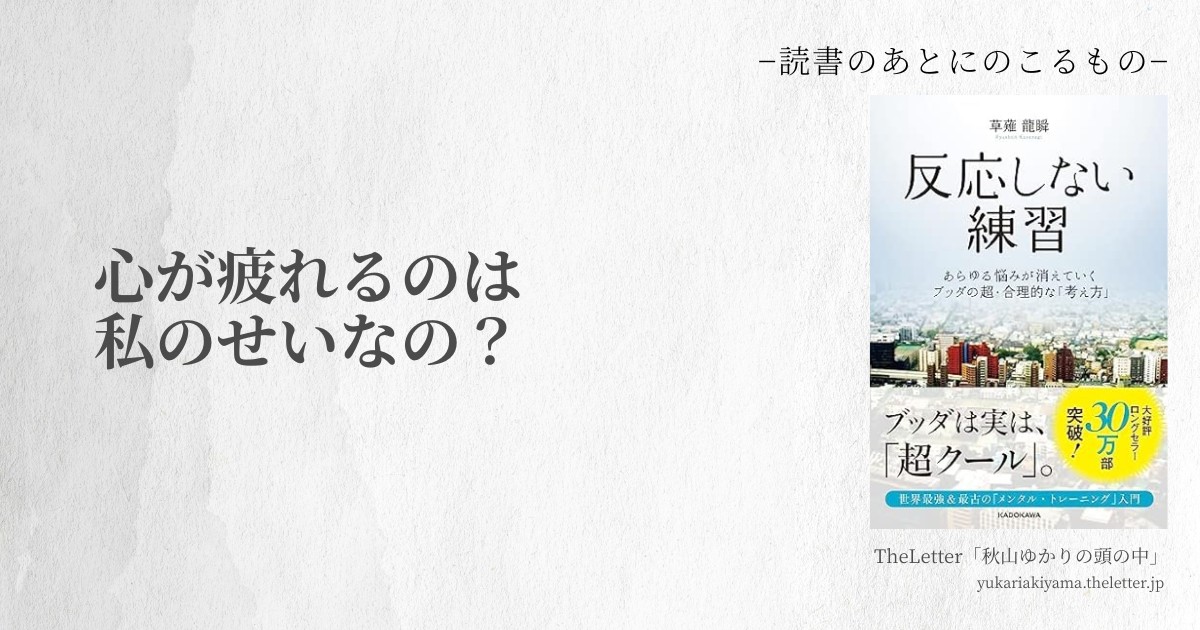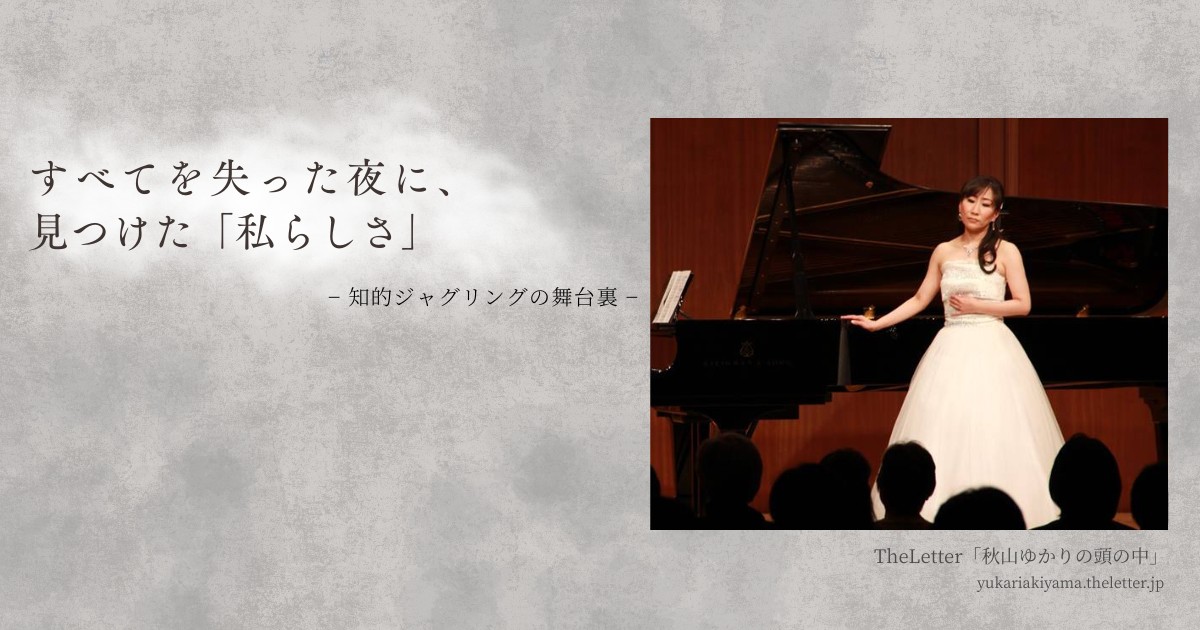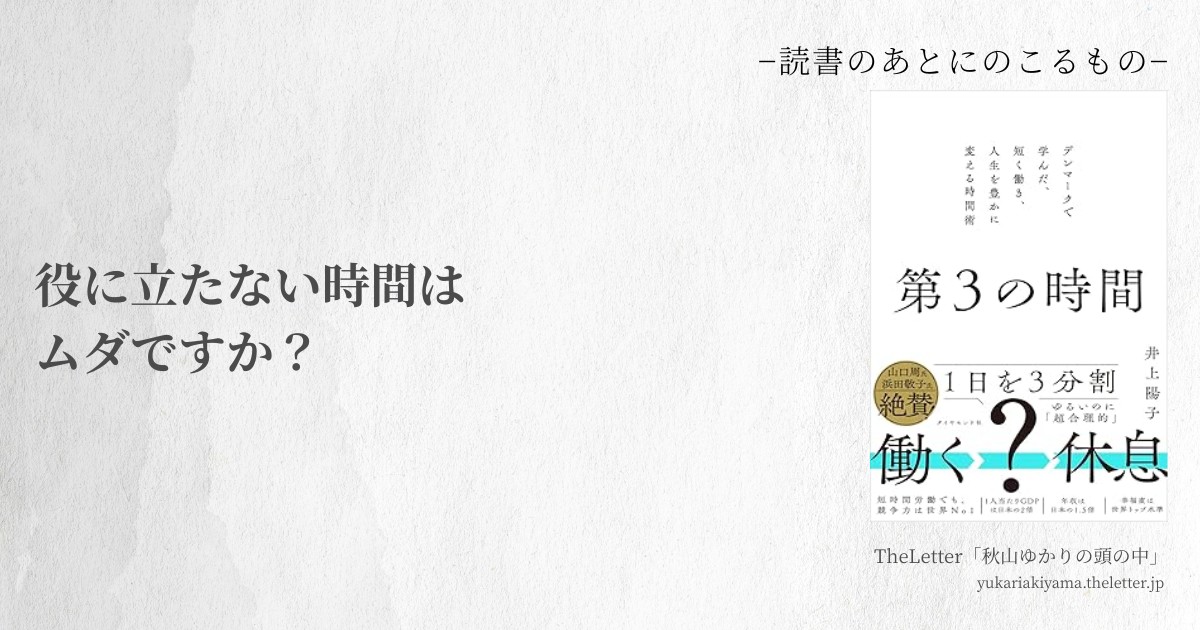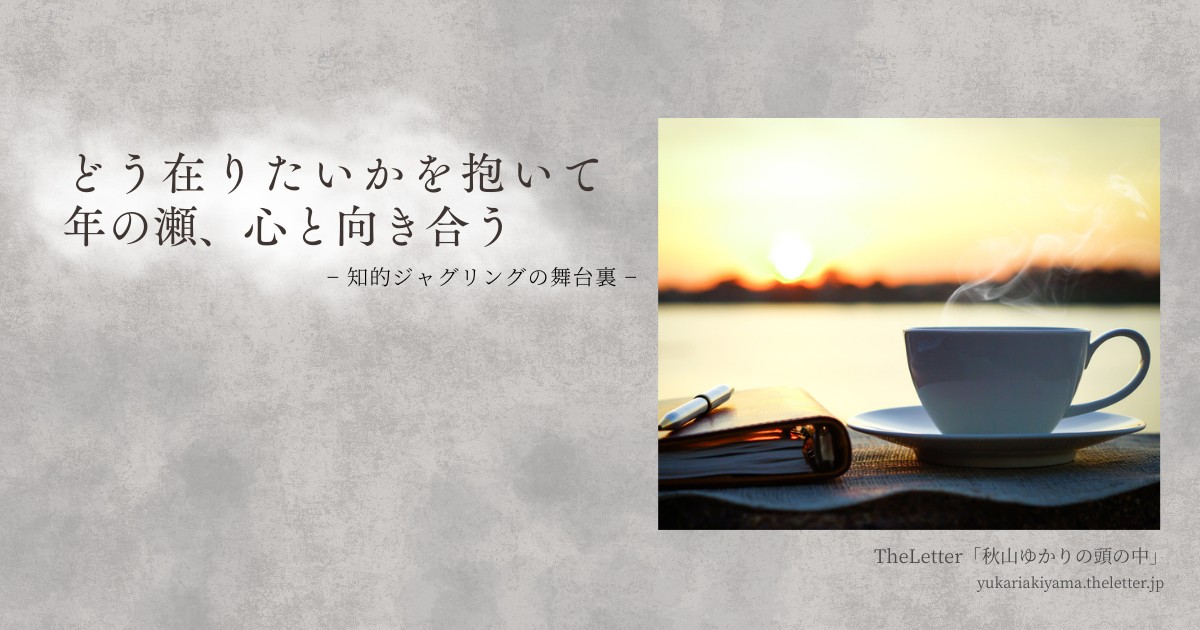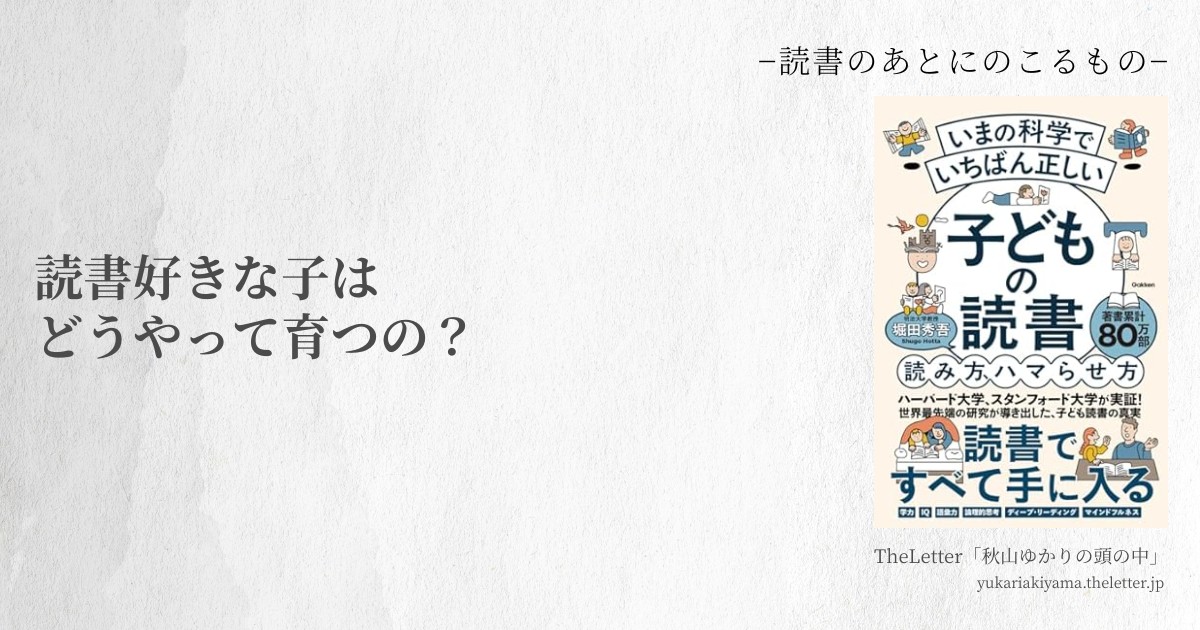教育の最終責任者は誰? 「子ども主導」を支える親の役割
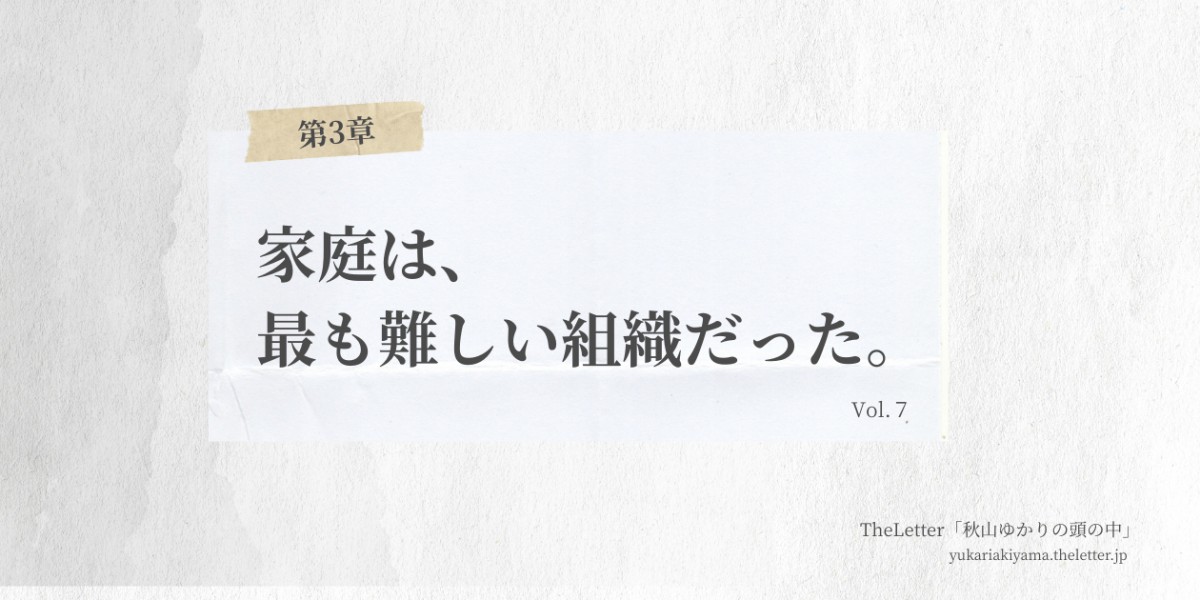
戦略コンサル、グローバル企業での事業開発、エグゼクティブの実務に加え、アーティスト・研究者・母の視点から発信しています。無料記事はサポートメンバーの支えで成り立っています。共感いただけた方は、ぜひご参加ください。
親の設計図にない選択
「この子、発達が普通じゃないです」
3歳児健診でムスメの言語理解が飛び抜けていると指摘されたことが、すべての始まりでした。発達支援センターで知能検査を受けたところ「異常なほどの言語能力」が明らかになったのです。発達障害ではなく、むしろ高い知性による「ズレ」だと。
子どもが1人しかいない私には、他の子と比べようがありませんでした。保育園のクラスにはムスメ以上に達者にしゃべる子もいたので、「女の子なんてこんなものか」くらいに思っていたのです。
でも、専門家の評価を聞いて思いました。
「あ、これは普通の教育環境では難しいかもしれない」
それから私は、幼稚園から入れる教育哲学を持った学校を片っ端から見学し始めました。モンテッソーリ、シュタイナー、レッジョ・エミリア......。ムスメと一緒に何度も足を運び、比較検討を重ねました。
ムスメはモンテッソーリとレッジョ・エミリアには興味を示さず、シュタイナー教育に強く惹かれました。私も「これだ!」と思い、学校説明会に参加しました。
そこで、海外でシュタイナー教育を長年実践してきた、日本で一番経験のある先生から言われたのです。
「本来、この子はシュタイナー教育にぴったりです。でも、この子のレベルのシュタイナー教育は、日本ではできません。どうか、ドイツかアメリカへ行ってください」
もう引っ越してそこへ行く気満々だった私たち。
ムスメもショックを受け、「えっ、うそ、断られちゃった!?」と涙ぐんでいました。
それでも、ムスメは立ち上がります。
「インターに行ってアメリカでシュタイナー教育を受ける?」と聞くと、ムスメは即答しました。
「私は、日本語力を伸ばしたいからインターには行かない。公立でいい」
4歳の子が、自分の教育方針を明確に持っている——この瞬間、私は子ども主導の進路設計が本格的に始まったことを悟ったのです。
この記事は無料で続きを読めます
- 選ぶのは子ども、決めるのも子ども
- 意思決定プロセスは、ここまで見せられる
- 親の役割は意思決定の土台をつくること
すでに登録された方はこちら