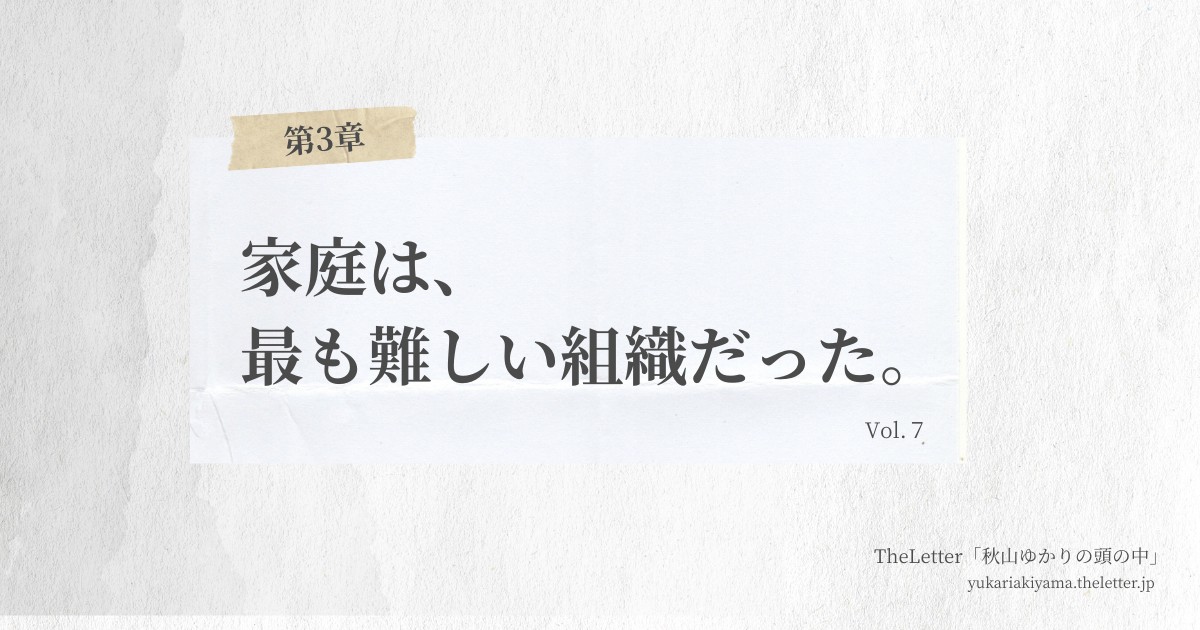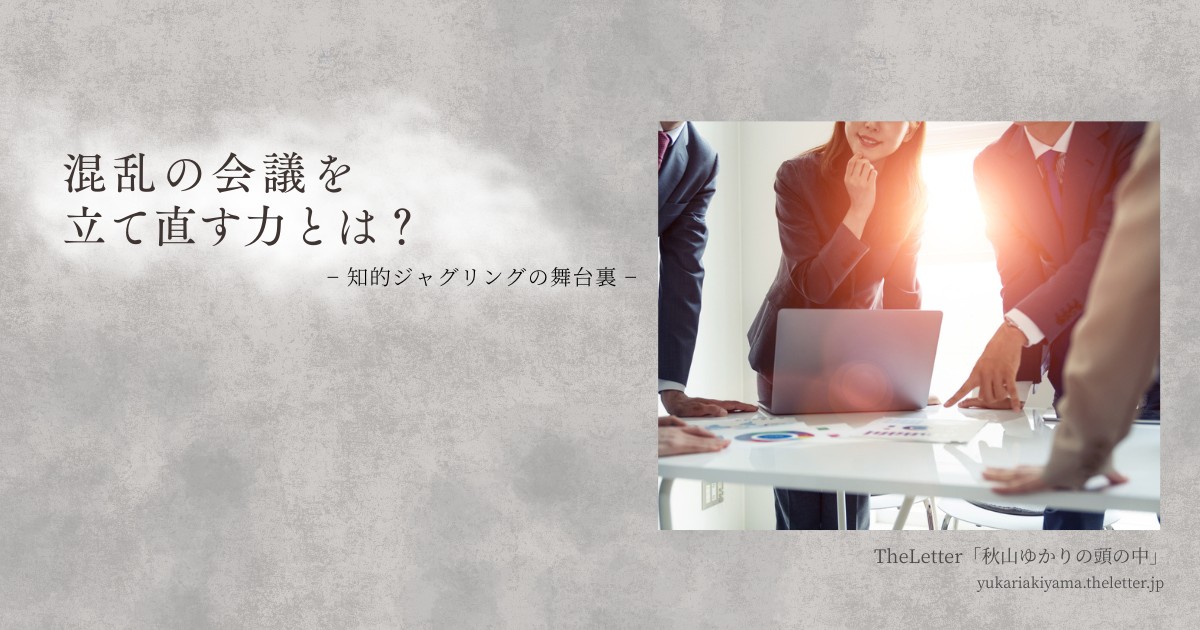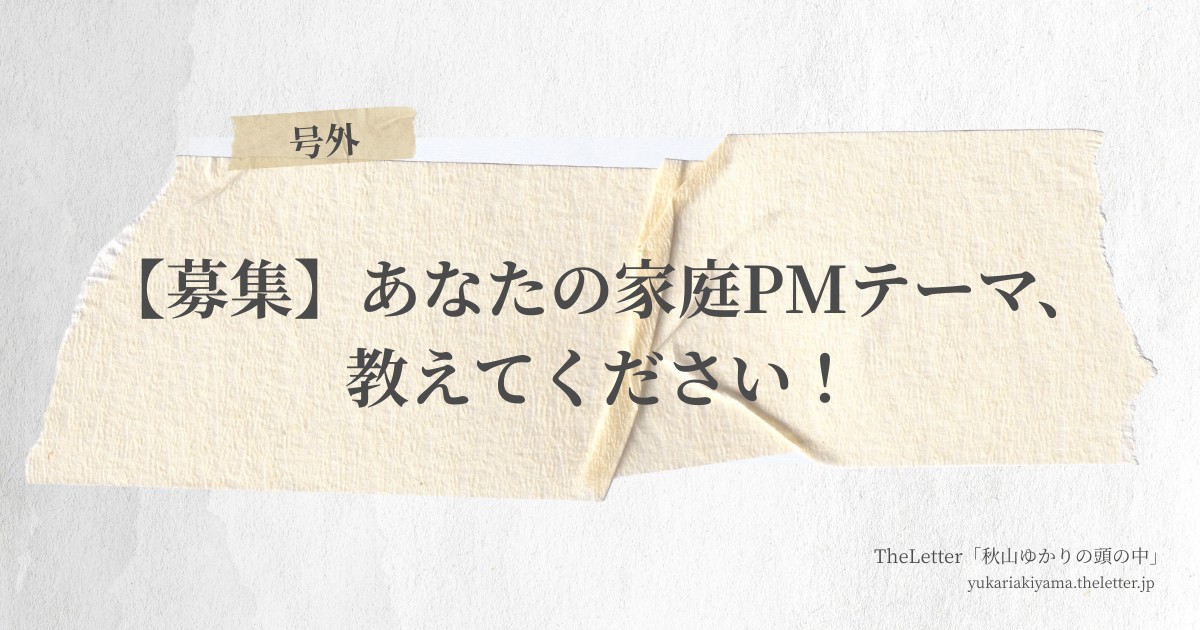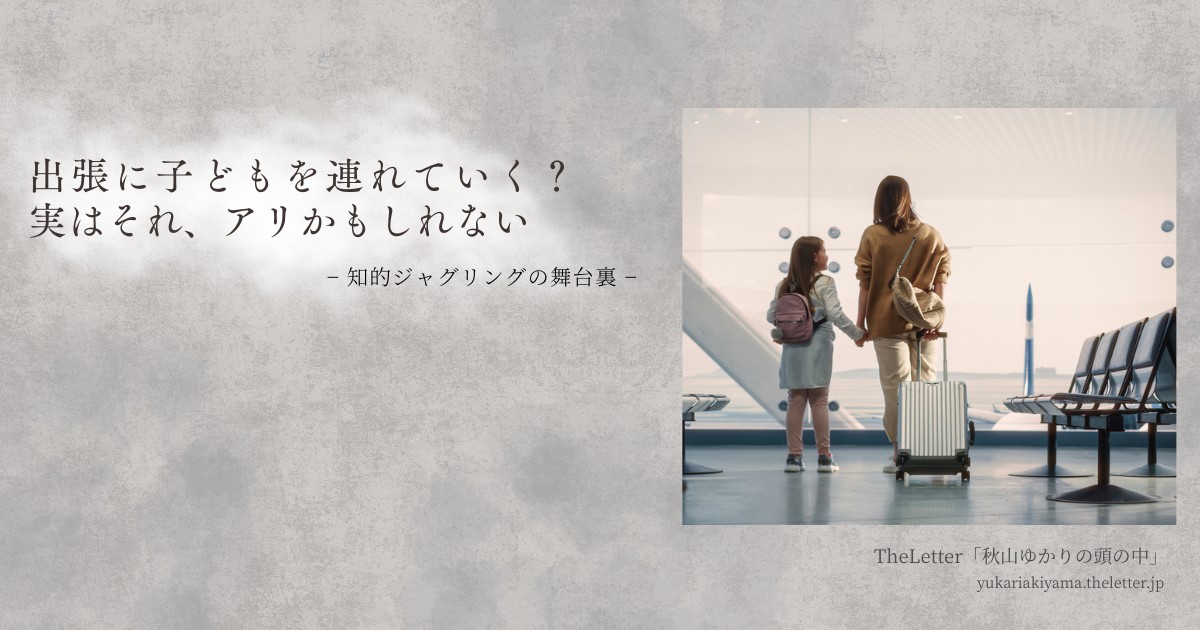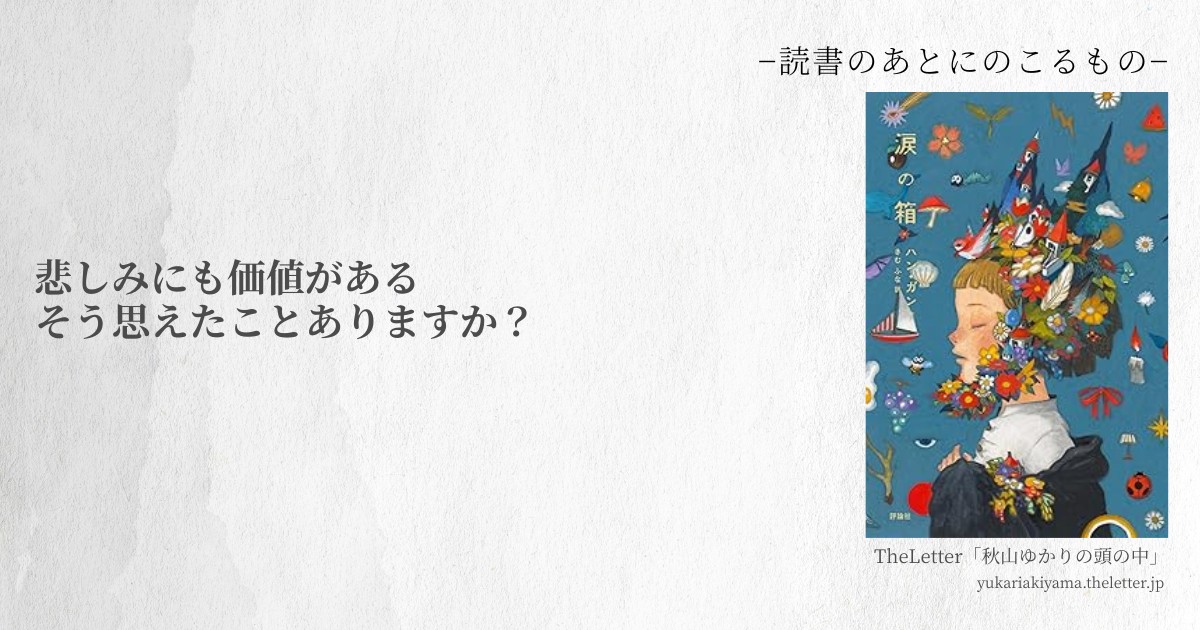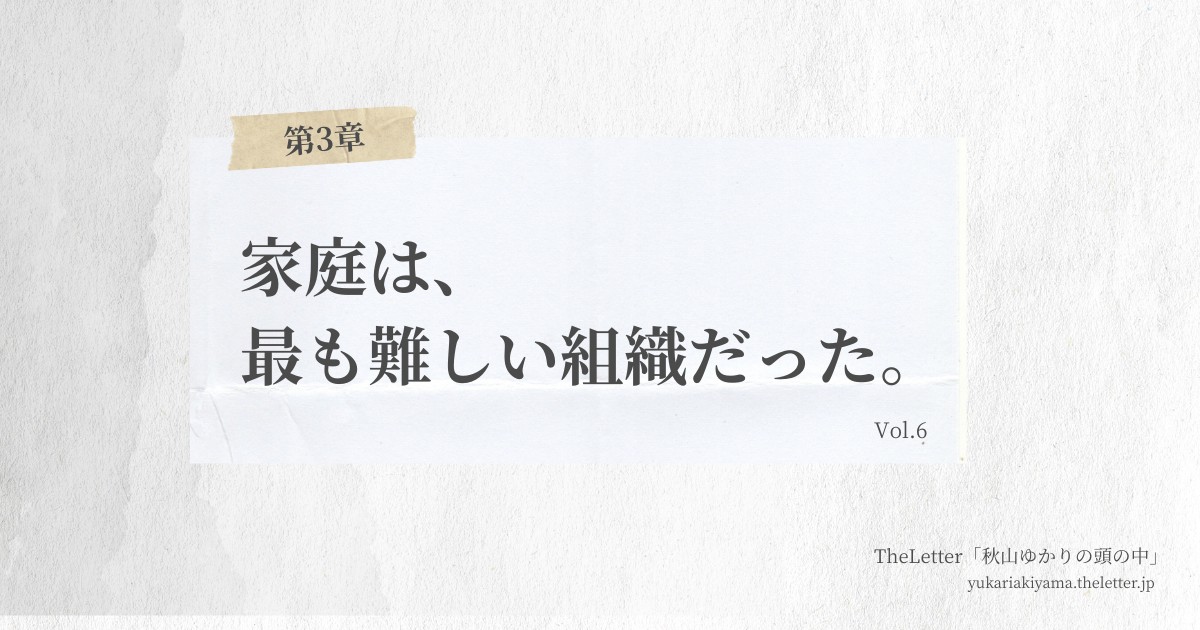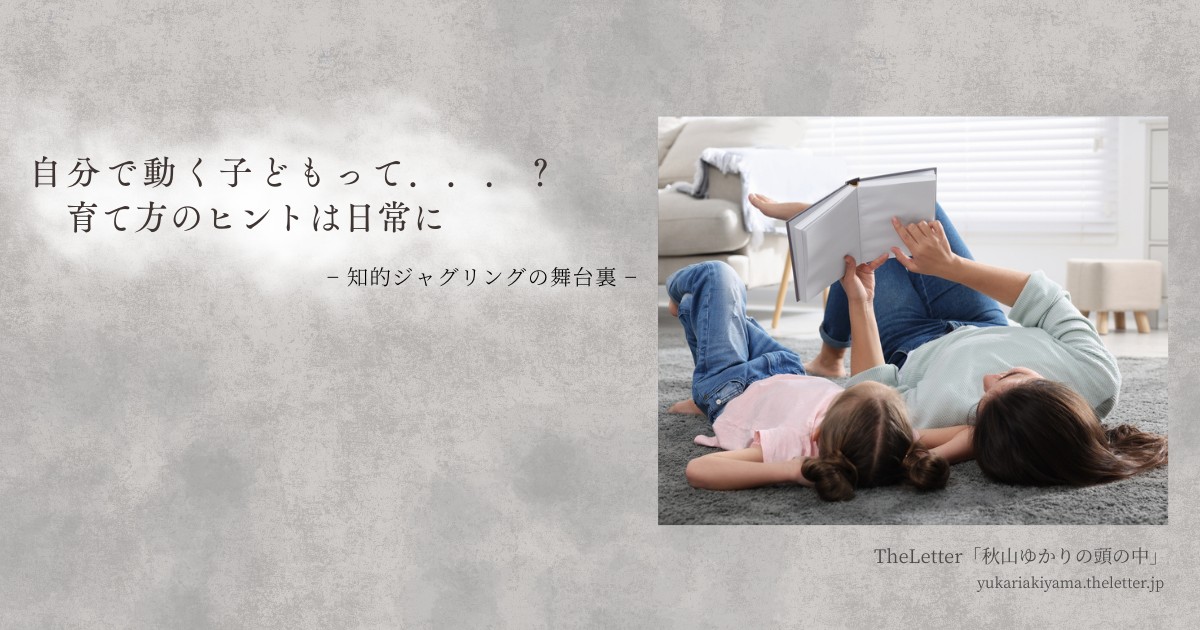『プロ目線のPodcastのつくり方』を読んで気づいた、声で届ける理由
戦略コンサル、グローバル企業での事業開発、エグゼクティブの実務に加え、アーティスト・研究者・母の視点から発信しています。無料記事はサポートメンバーの支えで成り立っています。共感いただけた方は、ぜひご参加ください。
文字だけでは届かないあいだを、どう伝えようか
TheLetterを始めてまだ1年も経たないのに、今日まで99本の記事を書いてきました。今週の水曜日は、記念すべき100号リリース予定です!
家庭と経営、子育てとキャリア、感情と合理、アートと思考法……日々の生活の「あいだ」で揺れ動く私の考えごとを、4,000字、5,000字、長いときは6,000字を超える文章で綴ってきました。
ありがたいことに、「深く読めるのが嬉しいです」「毎回、気づきがある」と温かい言葉をたくさんいただきます。
一方で、こんな声も増えてきました。
「ゆかりさんの記事、全部読み切れないんです…!」
「家事しながら聴けたらいいのに」
「家庭と経営のつながりをもっと語ってほしい」
そうなんですよね。家庭と仕事を行き来する毎日は、本当に慌ただしい。
私自身、ムスメの習い事を待つ間に、Podcastをながら聴きしている時間が、もっとも思考が冴える瞬間でもあります。洗濯物をたたみながら、料理をしながら、通勤しながら。音声は、忙しい生活のあいだに、そっと寄り添ってくれるんですよね。
「文字では伝わらない息づかいのようなものを、どう届けたらいいんだろう?」
そんなことを考えていた時に手に取ったのが、野村高文さんの『プロ目線のPodcastのつくり方』でした。
『プロ目線のPodcastのつくり方』が教えてくれた丁寧な音の届け方
この本は、単なる「Podcastの作り方」ではありません。もっと深い、人に何かを届ける仕事の本質に迫る一冊です。
野村さんは、聴かれるPodcastには4つの要素があると言います。
発見 × 理解 × 共感 × 空間設計
読みながら、「ああ、これは私がずっと大切にしてきたことだ」と思いました。
発見
家庭PMや家庭=ジョイントベンチャーの話をすると、よく「そんな視点、考えたこともありませんでした」と言われます。まさに発見の瞬間です。企業経営の視点を家庭に持ち込んでみたら、毎日の食卓や寝室での会話が、経営会議と同じくらい重要だと気づく。そういう「見方が変わる瞬間」こそが、コンテンツの価値なのだと野村さんは語ります。
理解
コンサルタントとして構造化して伝えること。感情と合理のあいだを可視化すること。これも、音声ならもっと自然に伝えられる気がしました。文章では図が必要でも、声なら自然に伝えられますね。
共感
TheLetterを通じて、「うちも同じです」「自分だけじゃなかったんだ」という声をいただくたび、文章が対話に変わっていくのを感じます。迷いながら話す言葉、ふと息をつく間、そういう「完璧じゃない瞬間」にこそ、人は共感するのかもしれません。
空間設計
そして何より大切なのが、空間としての音声。
耳から入ってくる言葉は、忙しい生活の合間に、そっと寄り添ってくれる。家事をしながら、会社へ向かいながら、眠りにつく前に。その人の生活に溶け込むメディアなんですよね。
野村さんが書く「リスナーとの深い関係性」や「ながら聴きの力」を読んで、私の中で、少しずつ何かが形になっていきました。
本書には、もっと実践的なこともたくさん書かれています。特に印象的だったのは、「Podcastは、リスナーの時間をいただいている」という視点です。
野村さんは、番組の長さについてこう書いています。「15分なのか、30分なのか、60分なのか。それは内容ではなく、リスナーの生活リズムで決まる」と。
通勤時間が20分なら、15分の番組がちょうどいい。家事をしながら聴くなら、30分くらいが集中力が続く長さ。そういう「聴く人の生活」を起点に考えることが、愛される番組を作る秘訣なのだと。
これは、まさに私がTheLetterで意識してきたことと同じでした。TheLetterで発信している方々は、TheLetter編集部に選ばれた専門家の人たち。読者の多くは5000-6000文字を読みなれている人たちなので、中身の薄い記事ではなく、しっかりと書きこんでくださいと編集長から言われました。読者の方がどんな時間に読んでくださるのか。朝のコーヒータイムなのか、夜の静かな時間なのか。その想像から、記事のトーンも長さも決まってくる。
Podcastも同じだそう。番組の長さをどうするか。エピソードの構成をどう組み立てるか。リスナーがどんな瞬間に聴いているかを想像しながら作る。
それは、まるで夕飯を作る時に「今日のムスメは何を喜ぶかな」と考えるのと同じ。相手のことを思いながら、丁寧に届ける。その姿勢こそが、Podcastの本質なのだと気づかされました。
野村さんは、「完璧を目指さない勇気」についても書いています。最初から完璧な番組を作ろうとすると、スタートできない。まずは始めて、リスナーの反応を見ながら改善していく。そのプロセスこそが、番組を育てていくのだと。
この言葉に、私は背中を押されました。TheLetterも、最初の記事は今読み返すと恥ずかしくなるほど拙い。でも、書き続ける中で、少しずつ自分の声が見つかっていった。Podcastも同じなのだと思います。
ムスメと交わす会話の空気感──だから声がいいと思った瞬間
実は、音声を始めるかどうか、ずっと迷っていました。
文章を書くことは、私にとって思考を整理する手段です。書きながら考え、考えながら書く。そのプロセスが心地よかった。
でも、心の奥にずっと引っかかっていたテーマがあります。
たとえば、ムスメと夕飯を作りながら交わす何気ない会話には、言葉にならない不安や迷いが含まれていることがあります。
文章で「ムスメとこんな会話をしました」と書くことはできる。でも、その時の空気感、言葉を選ぶ時の迷い、ふと笑ってしまった瞬間。そういうものは、やっぱり音声でないと届かないんじゃないか。
最近、こんなことがありました。
ある夜、ムスメが「将来、私は学校の先生になりたいの。でも、お店屋さんにも、クワガタの研究者にもなりたい。どれか1つを選ぶってとっても難しいから、どうしようかなぁ。全部になれる方法がわからないから、どうなりたいのか分からない」と言ってきました。10歳の彼女なりに、周りの友達が「医者になりたい」「商社マンになりたい」と言う中で、自分だけいろんなものになりたくて、答えが見つからないことに焦っていたんです。
私は、夕飯の準備の手を止めて、彼女の隣に座りました。そして、こう言いました。
「ママも、10歳の時は何になりたいか分からなかったよ。でもね、大学でインターネットに出逢って、ITエンジニアになって、その後は、戦略コンサルタントで、イタリアに留学した後に、事業会社に行って戦略や事業開発をやりながら、歌ってた。今は、戦略コンサルタントで、経営者で、声楽家で、研究者なの。全部、やりたいことをやっていたら、こうなった」
ムスメは目を丸くして、「ママ、作家じゃなかったの?」
「そうだね、作家って顔もあるね。だからね、一つに決めなくていいんだよ。いろんなことを組み合わせて、自分だけの形を作ればいい」
その会話のあと、私はふと思いました。
「あ、この間は、声じゃないと伝わらない。」
家庭PMという概念も、家庭がジョイントベンチャーだという視点も、文章で伝えることはできる。でも、その考えに至るまでの葛藤、迷い、小さな発見の瞬間。そういうものは、声で語った方が伝わるんじゃないか。
野村さんの本には、こんな一節があります。
「Podcastは、パーソナルなメディアです。一対一で語りかける感覚が、深い信頼関係を生む」
まさに、これだと思いました。
TheLetterは「読者の皆さん」に向けて書いています。でも、Podcastでは「あなた」に向けて話すことができる。運転中のあなた、洗濯物をたたんでいるあなた、通勤電車の中のあなた。一人ひとりの生活の中に、私の声が届く。
そこに、『プロ目線のPodcastのつくり方』が追い打ちをかけてきました。
深い関係性は、音声のほうが育ちやすい
という言葉が、心に刺さったのです。
文章には文章の強さがあるけれど、音声には寄り添う力がある。
家庭と経営のあいだを語るなら、ムスメとのやり取りを語るなら、不安や迷い、感情の微妙な揺れまで含めて伝えるなら、きっと声のほうがいい。
私がよく言う「壁打ち」も、実は声のコミュニケーションです。BCG時代、「頭貸してください」と先輩に頼んで、とりとめのない話をしながら思考を整理していく。あの感覚を、Podcastで再現できたらどうだろう。
リスナーの方と、まるで運転中の車の中で隣に座って話しているような、そんな時間を作れたら。
11月20日、声でお会いします。あなたのおすすめPodcastも教えてください
というわけで
11月20日(木)からPodcastを始めることにしました。
タイトルは、「家庭と経営のあいだで」
家庭PMの話、キャリアと子育ての両立、経営者としての視点、アート思考、感情の揺れまで、TheLetterで書いてきたあいだの思考を、声でお届けします。
文章とは違った形で、もっとラフに、もっと自然に。迷いも含めて、正直に語っていきたいと思っています。
『プロ目線のPodcastのつくり方』は、「技術」ではなく聴いてくれる人を大切にする設計図を教えてくれる本でした。そのおかげで、私もようやく覚悟が決まりました。
野村さんは本の中で、「Podcastは、リスナーの生活の一部になれる」と書いています。毎週水曜日の夜、TheLetterを読んでくださっている方が、木曜日の朝は私の声と一緒に通勤してくれる。そんな新しい関係が築けたら、こんなに嬉しいことはありません。
はじめての取り組みですから、最初は試行錯誤かもしれません。でも、文章もそうだったように、みなさんと対話しながら、少しずつ形を作っていけたらと思っています。
最後に、お願いがあります。
あなたがいつも聴いているPodcastを、コメントで教えてください。
ジャンルでも、番組名でも、理由でもOKです。「通勤中はこれ」「家事しながらこれ」「寝る前はこれ」──そんな情報も嬉しいです。
あなたの聴く習慣から、これからの番組づくりに活かしたいのです。
木曜日から声でもお会いできるのを楽しみにしています。
See you in the space between
あいだの世界で、お会いしましょう。
【紹介した本】 『プロ目線のPodcastのつくり方』野村高文著
【Podcast情報】
番組名:「家庭と経営のあいだで」
配信開始:2025年11月20日(木) 7:00am
配信プラットフォーム:Stand.fm、Apple Podcast
すでに登録済みの方は こちら