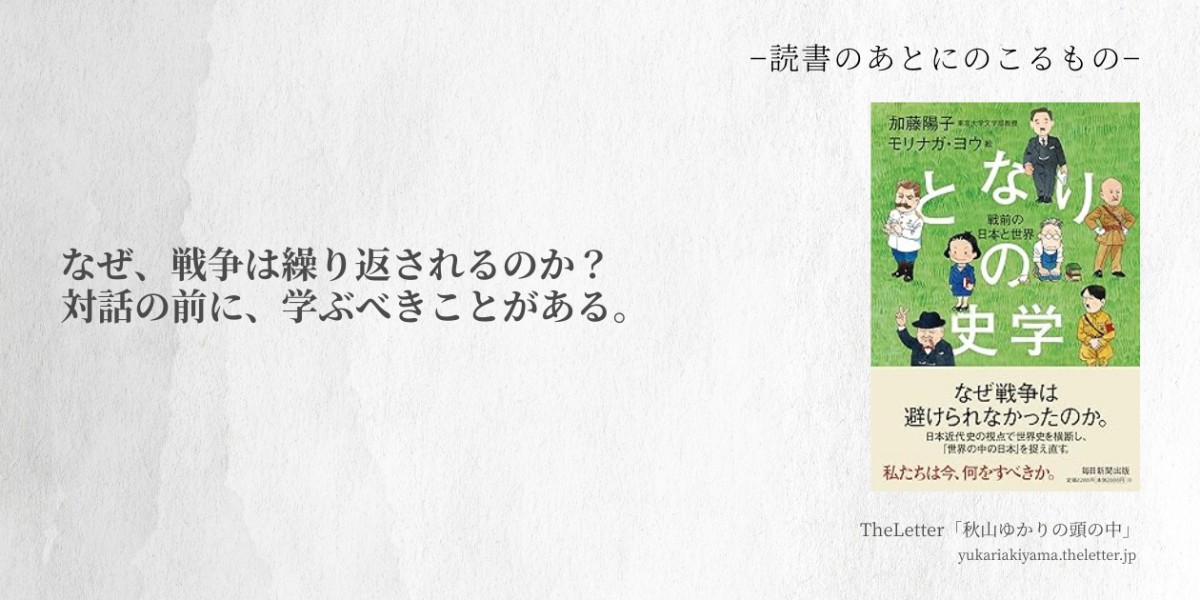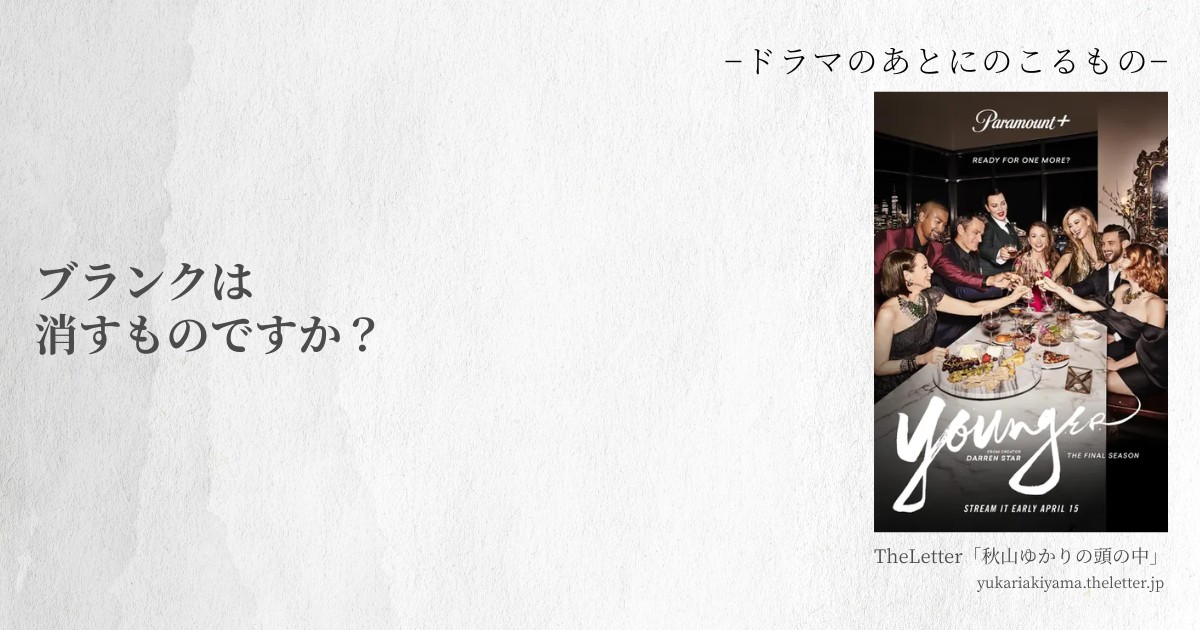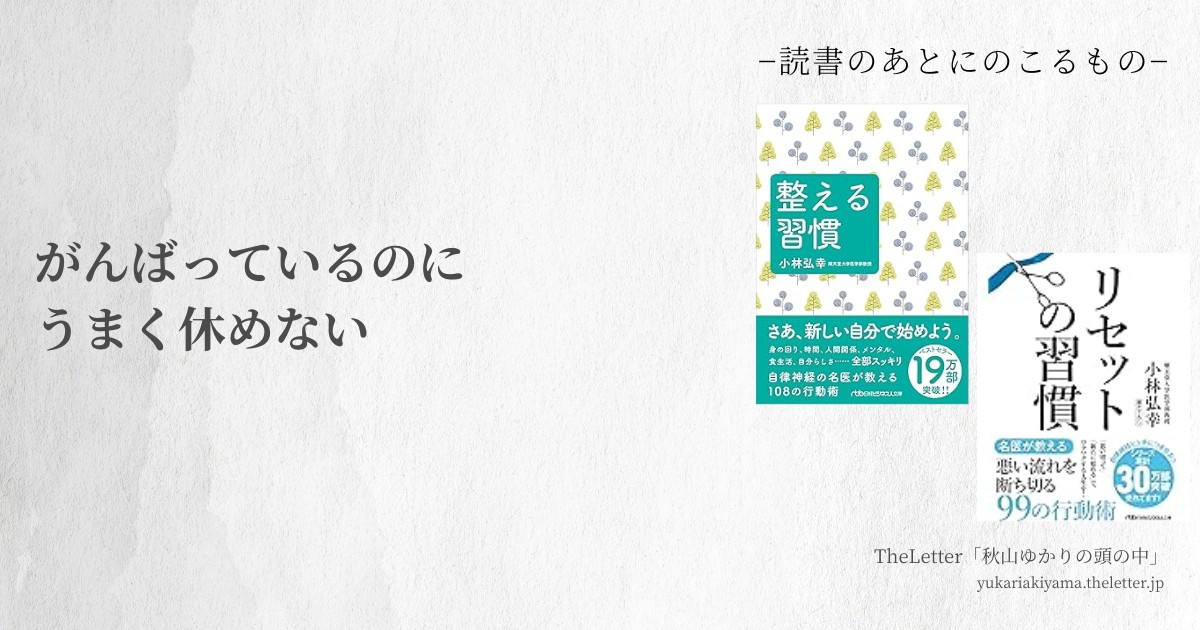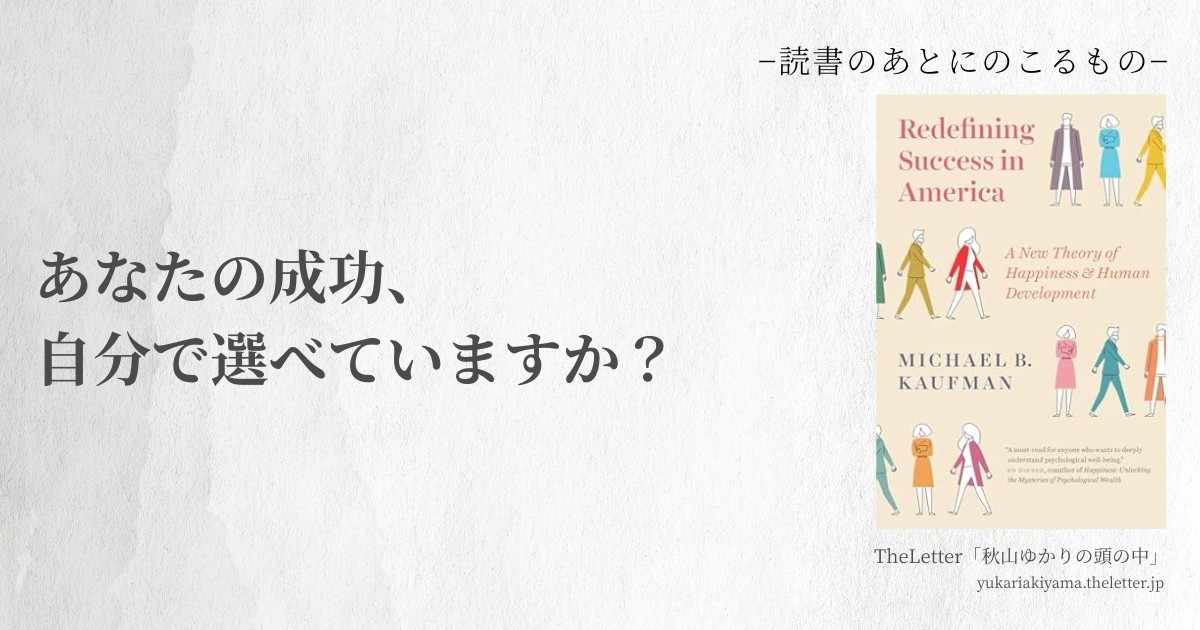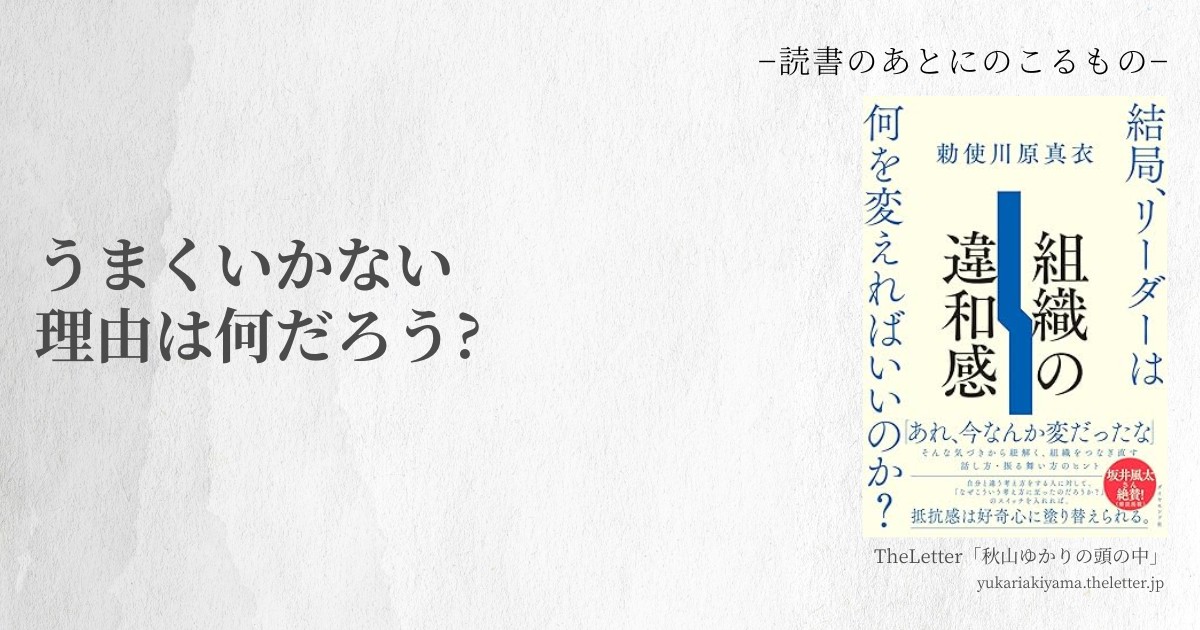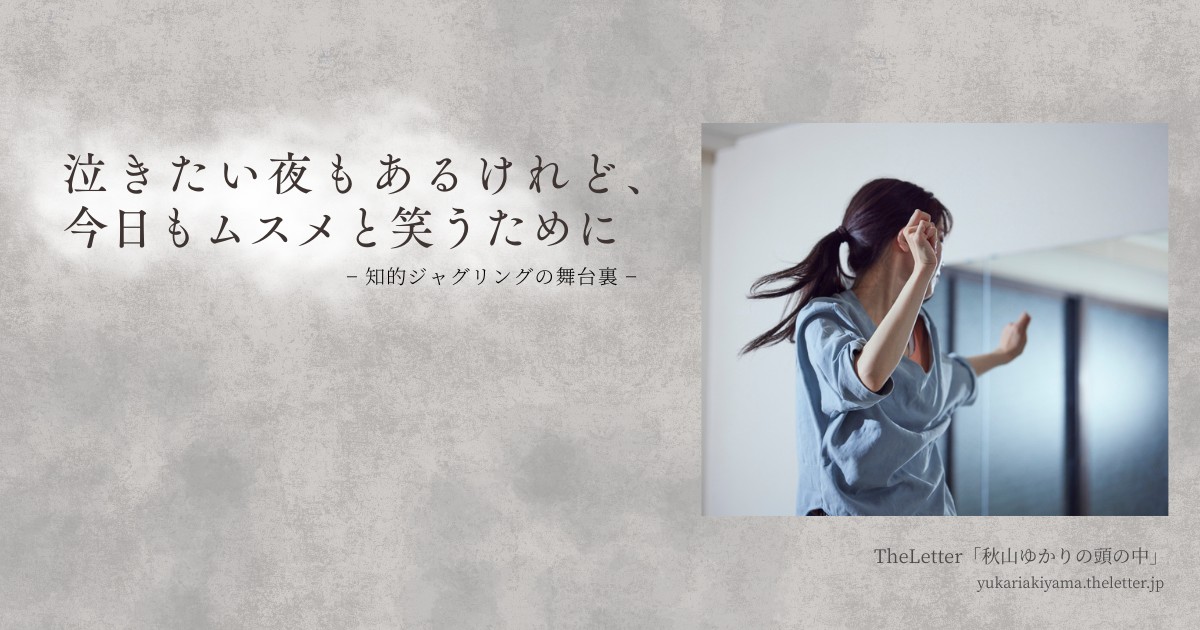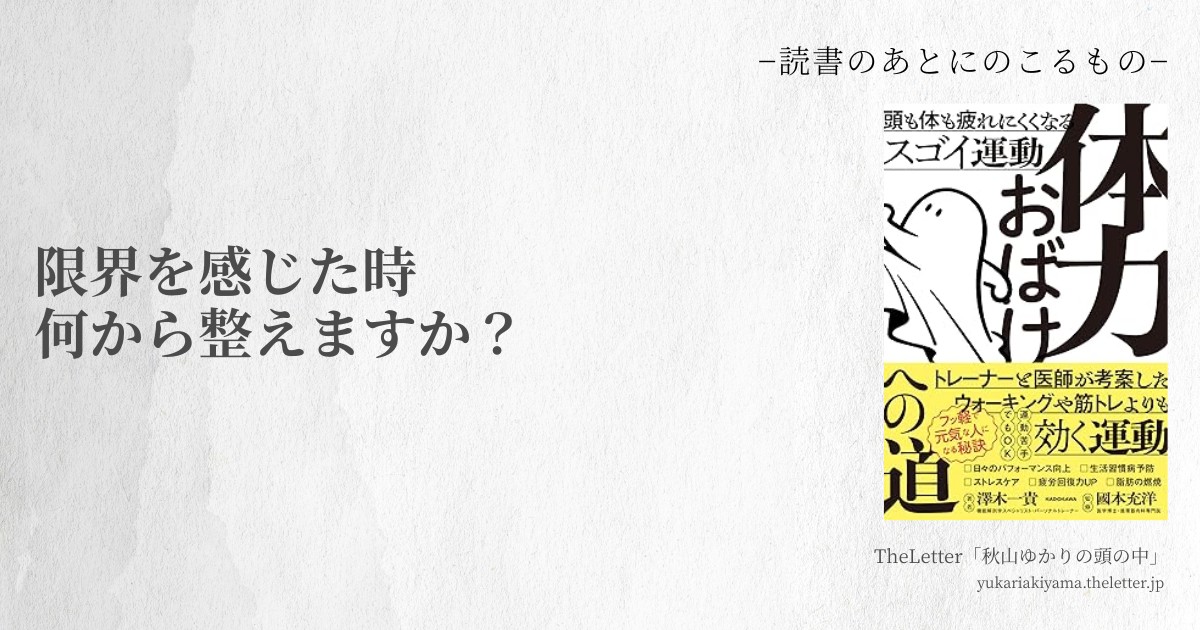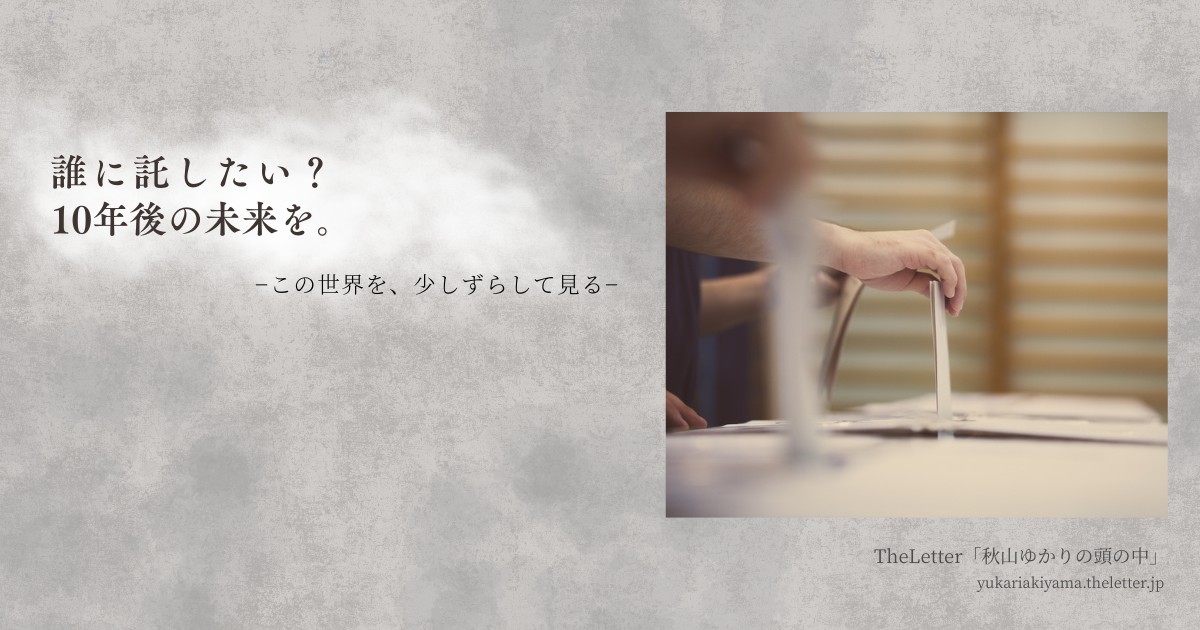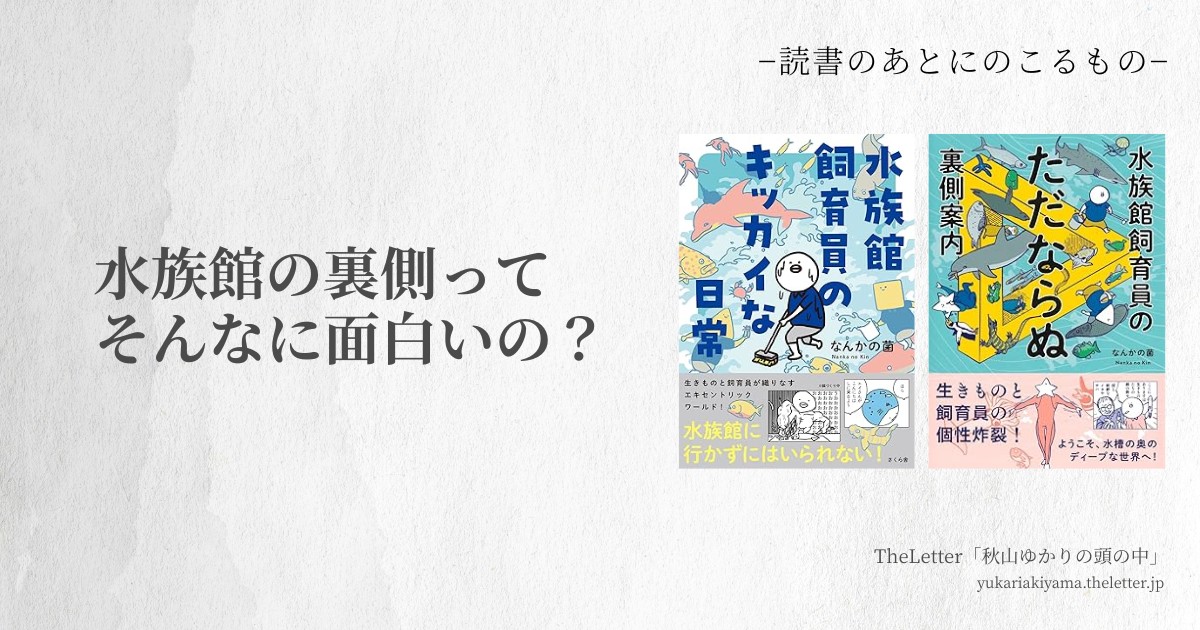戦争はなぜ繰り返されるのか?──加藤陽子『となりの史学』が教える隣人理解の方法論
戦略コンサル、グローバル企業での事業開発、エグゼクティブの実務に加え、アーティスト・研究者・母の視点から発信しています。無料記事はサポートメンバーの支えで成り立っています。共感いただけた方は、ぜひご参加ください。
先週の夕食時、小学生のムスメが突然、こんなことを聞いてきました。
「ママ、どうしてロシアとウクライナはいつまでも戦争してるの?ニュースでガザの子どもたちが泣いてるのも見たよ。どうして大人は戦争をやめられないの?」
その純粋な問いかけに、私は箸を止めて考え込んでしまいました。
「それはね...」と説明しようとして、自分がいかに「なぜ争いが繰り返されるのか」という根本的な問いに向き合ってこなかったかに気づかされたのです。
「みんな仲良くすればいいのに」と続けるムスメの言葉は、シンプルだけれど本質を突いています。
そう、なぜ「仲良く」できないのか——。
その夜、ムスメが寝た後、私は書棚から一冊の本を取り出しました。
加藤陽子先生の『となりの史学 戦前の日本と世界』。
ページを開いて最初に目に飛び込んできた一節に、私は衝撃を受けました——
「日本は古代中国の偉人たちを見続け、中国は近代日本の侵略者たちを見続けている」。
ああ、これだ、と思いました。同じ隣国なのに、お互いがまったく違う「物語」を見ている。
この認識のズレこそが、ムスメの「どうして仲良くできないの?」という問いへの、一つの答えなのかもしれない。
今日は、月曜の朝にふさわしい「知のジャグリングの旅」として、この一冊をご紹介します。なぜなら、この本は小学生の素朴な疑問にも、そして私たち大人の複雑な悩みにも、「平和のための方法論」という形で答えてくれるからです。
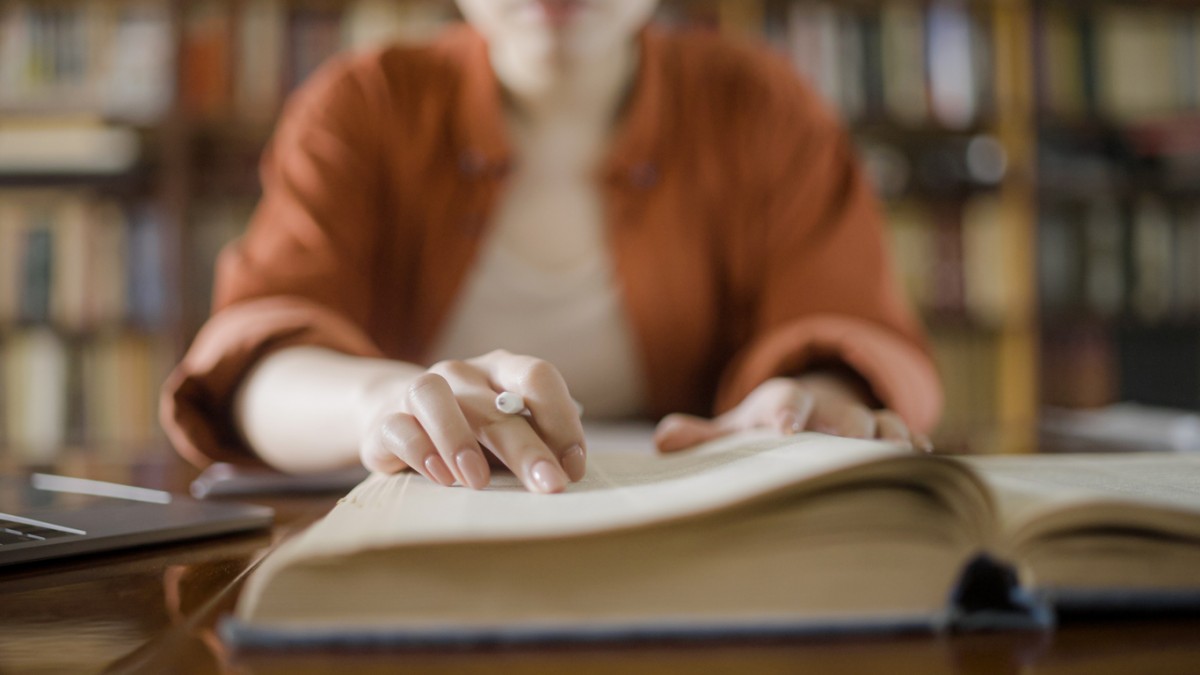
この記事は無料で続きを読めます
- 知識ではなく、視座を学ぶ——「となりの史学」との出会い
- 「となりの史学」という知的トレーニング
- 「歴史を知ること」は「平和をつくること」
- 私たちの「となりの史学」を始めよう
すでに登録された方はこちら