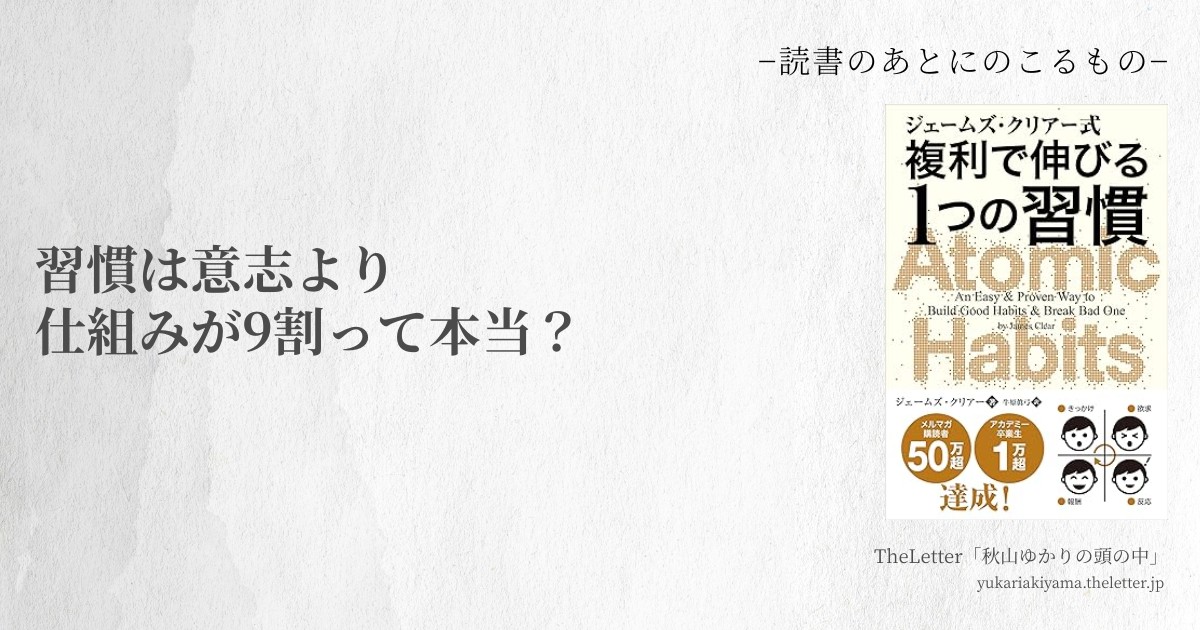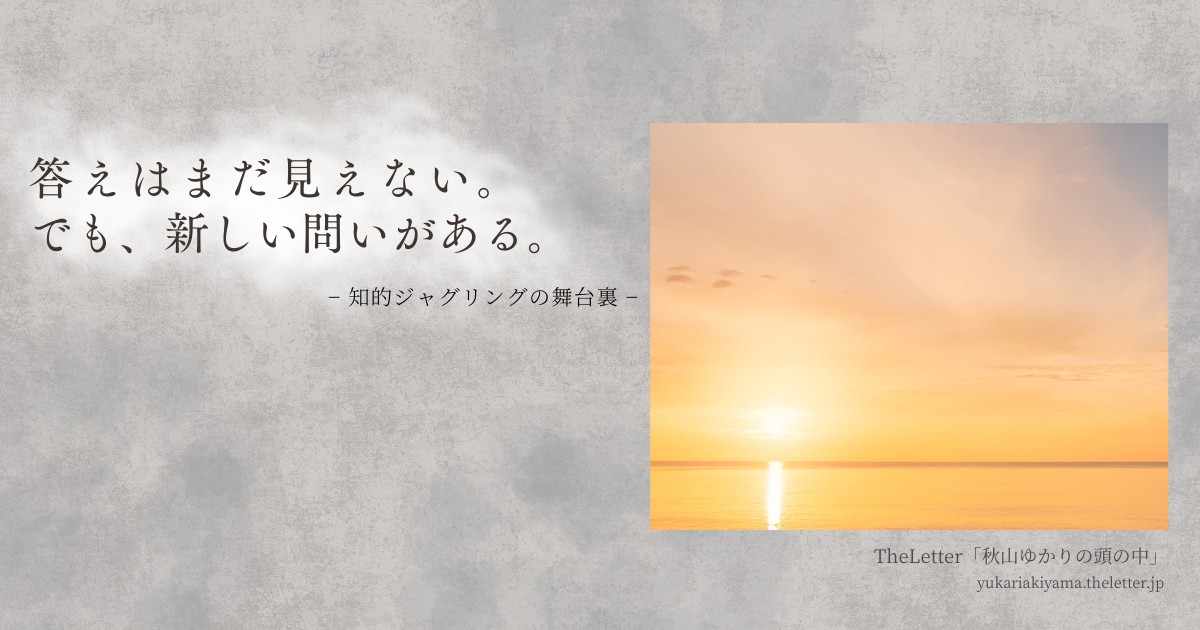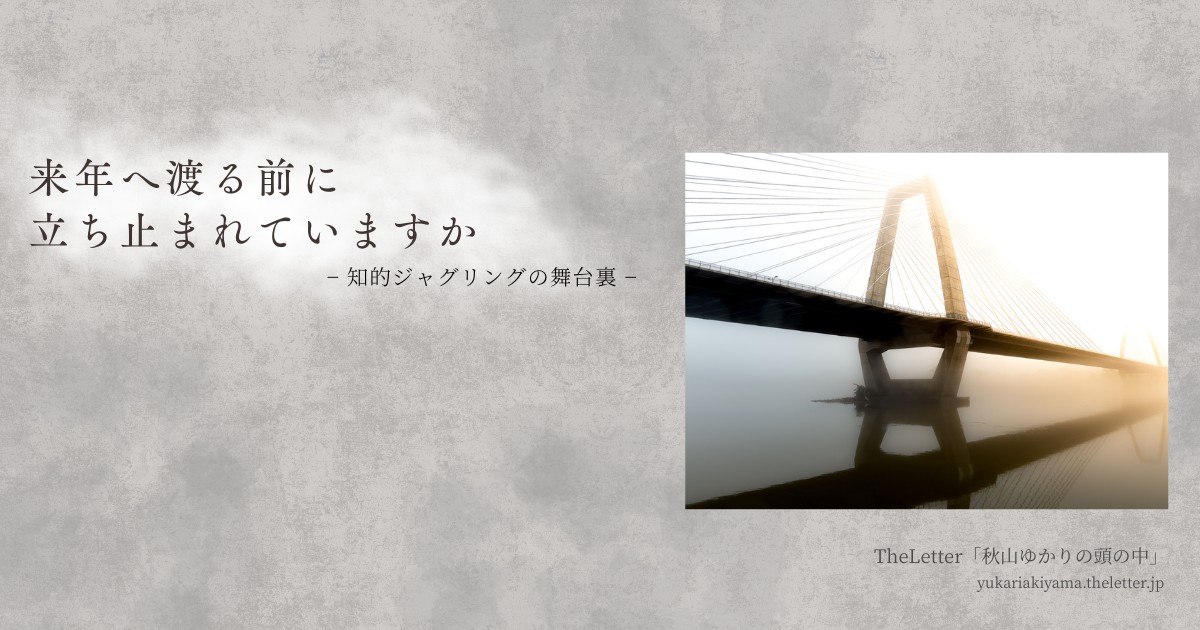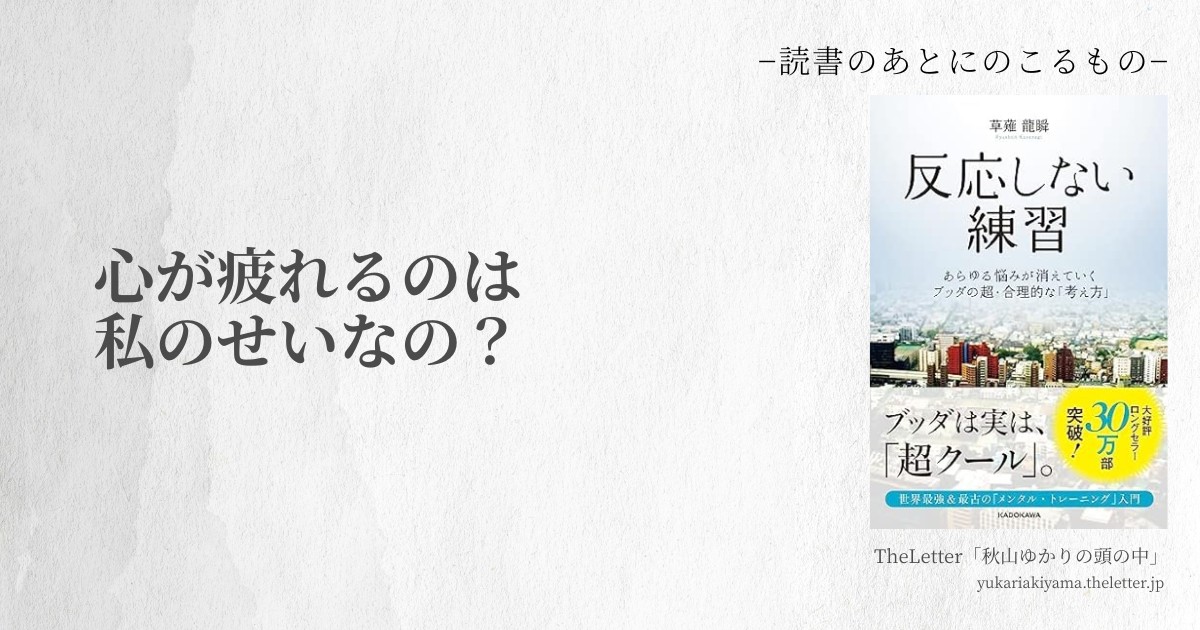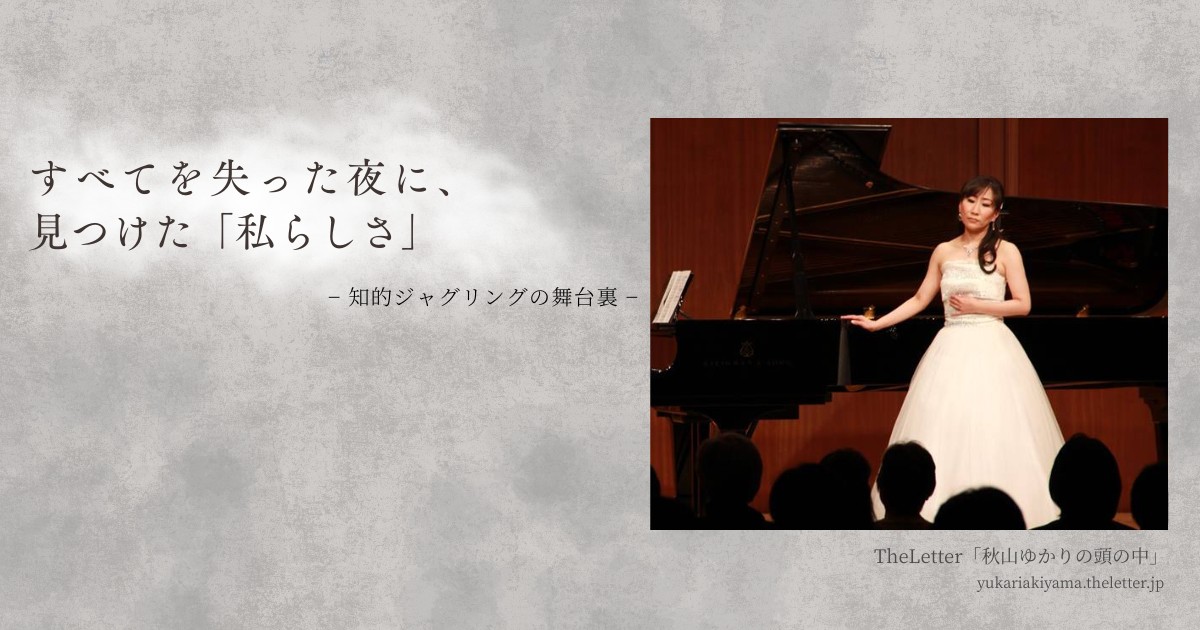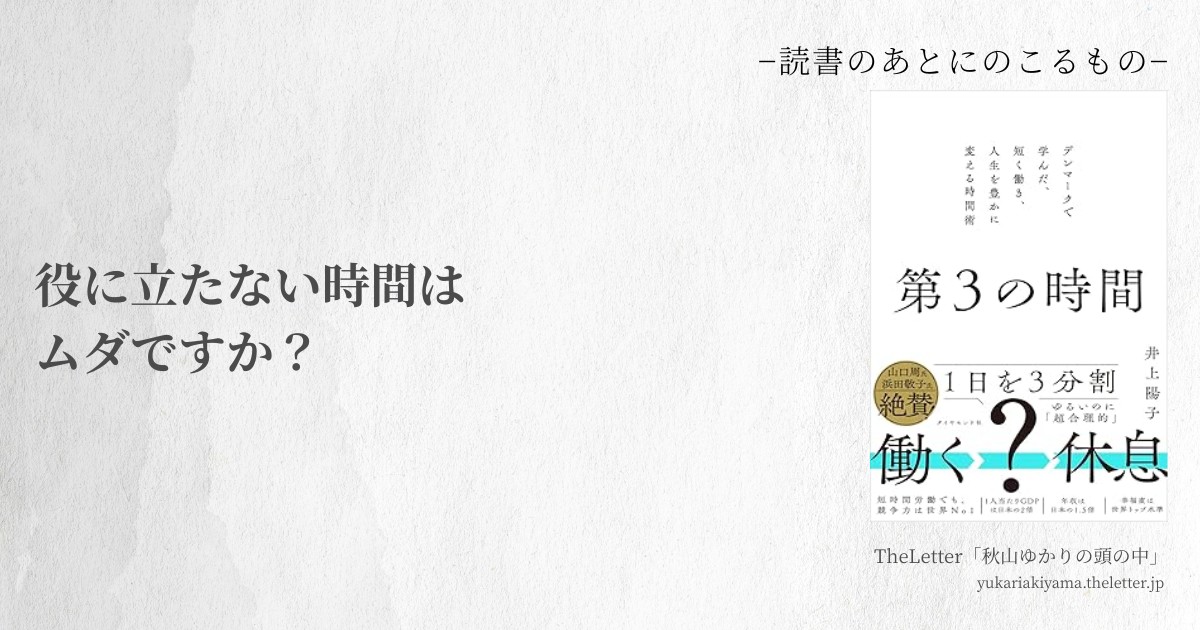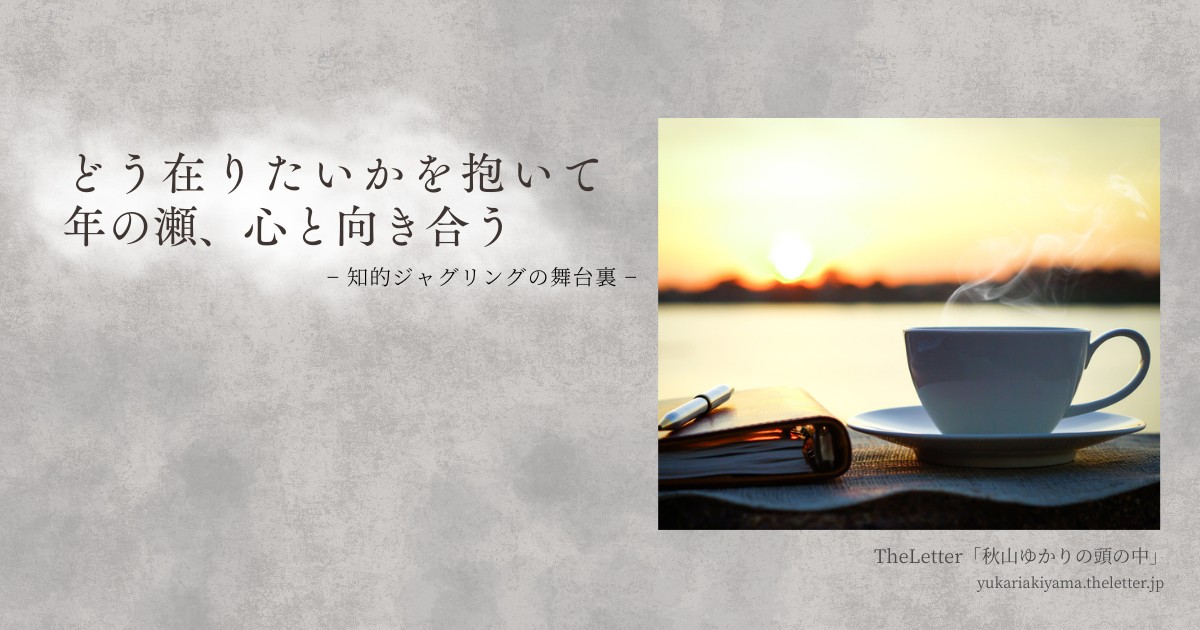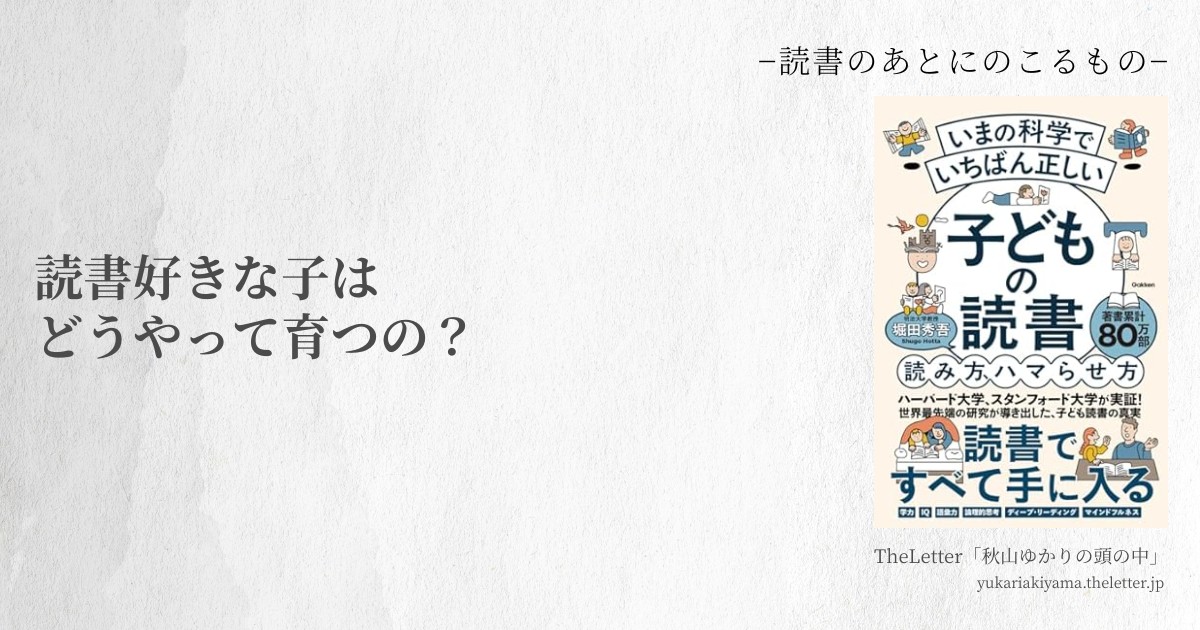「ママ不在」で崩壊した家庭——娘が副菜5品を作った日
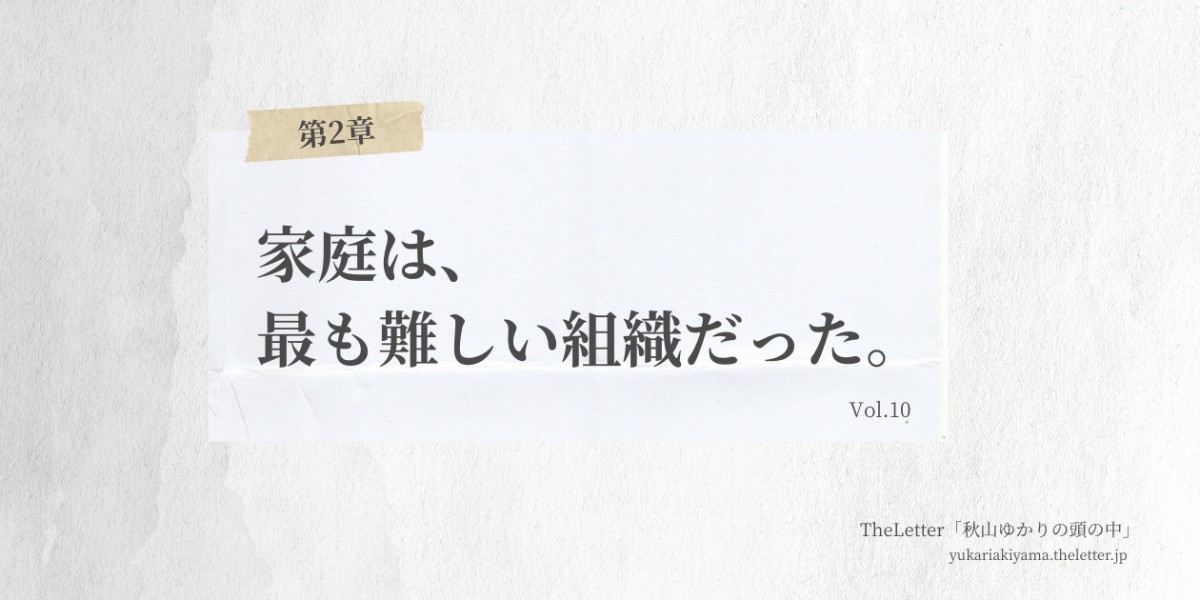
戦略コンサル、グローバル企業での事業開発、エグゼクティブの実務に加え、アーティスト・研究者・母の視点から発信しています。無料記事はサポートメンバーの支えで成り立っています。共感いただけた方は、ぜひご参加ください。
「冷蔵庫あければわかるでしょ?」と思った私
「出汁、切れたから買ってきてくれる?」
そう夫にLINEを送ったのは、私が仕事の合間にスーパーに寄る時間がなかったから。家に戻ってもすぐにZoom会議に参加しないといけないから。でも、その5分後からスマホは通知の嵐になりました。
-
「出汁ってどれ?液体?粉末?」
-
「メーカーあるの?」
-
「味噌も買うんだよね?種類は?」
-
「冷蔵じゃないやつ?棚どこ?」
私は思いました。「冷蔵庫、あければわかるでしょ……」。
でも、それは「私の中だけの常識」だったのです。
家庭には、無数の「見えないルール」と「当たり前」が存在しています。 それを知っている人には簡単でも、知らない人にとっては謎解きゲーム。 日々の小さな摩擦の多くは、こうした“見えない情報”のすれ違いから起きているのです。
「察してよ」が爆発する日常
我が家の買い物担当は基本的に夫。調理は100%私。ムスメが超偏食な上に、食物アレルギーと内臓疾患があるので、材料の選定や銘柄にはこだわりがあります。
でも、私の頭の中の「買い物仕様」は夫には共有されていません。
-
出汁を頼めば、液体と顆粒のどちらを選ぶかで迷う。
-
豆腐をお願いすれば、絹と木綿に迷う。
-
味噌を頼めば、九州味噌と長野味噌で悩む。
私にとっては「見ればわかるでしょ?」の世界。でも夫にとっては、全部が暗号。仕様が共有されていないのに、最適解を求められる状態でした。
仕事で言えば「仕様書なしで発注されるプロジェクト」と同じです。どれだけ頑張っても「それじゃない」と言われる。結果、家庭でも「なんでわかってくれないの?」が積み重なり、双方に不満がたまっていくのです。
心理学では、これを「期待値ギャップ」と呼びます。 人は「自分の当たり前」を相手も知っているはずだと考え、無意識に期待してしまう。ところが現実にはその前提が共有されていないため、期待は裏切られ、不満や怒りが生まれるのです。
職場でも「言わなくても伝わるだろう」と思ったことが伝わらず、炎上するのは典型的な期待値ギャップ。家庭でもまったく同じ構造でした。
この記事は無料で続きを読めます
- 母の緊急搬送、家庭のナレッジが崩壊した日
- 学校支度ルーチンという“もう一つの暗黙知”
- 家庭ナレッジを「次世代」に渡す
- 「察して文化」の裏側にある「思考のショートカット」
- 「察しない家庭」は、優しさで回るチームだった
すでに登録された方はこちら