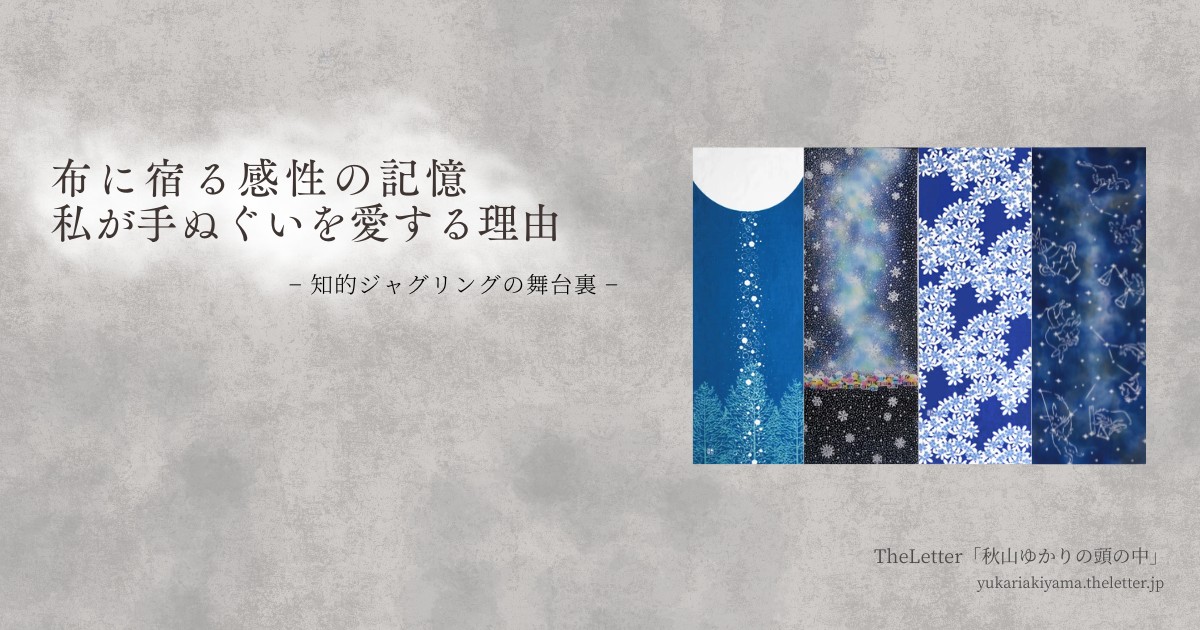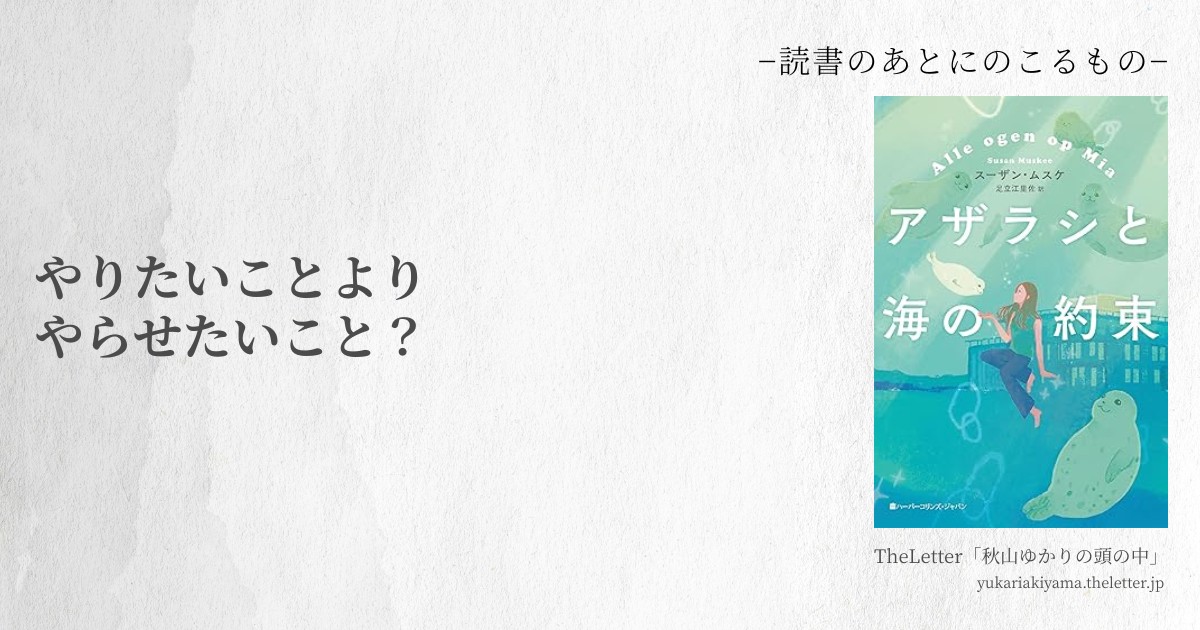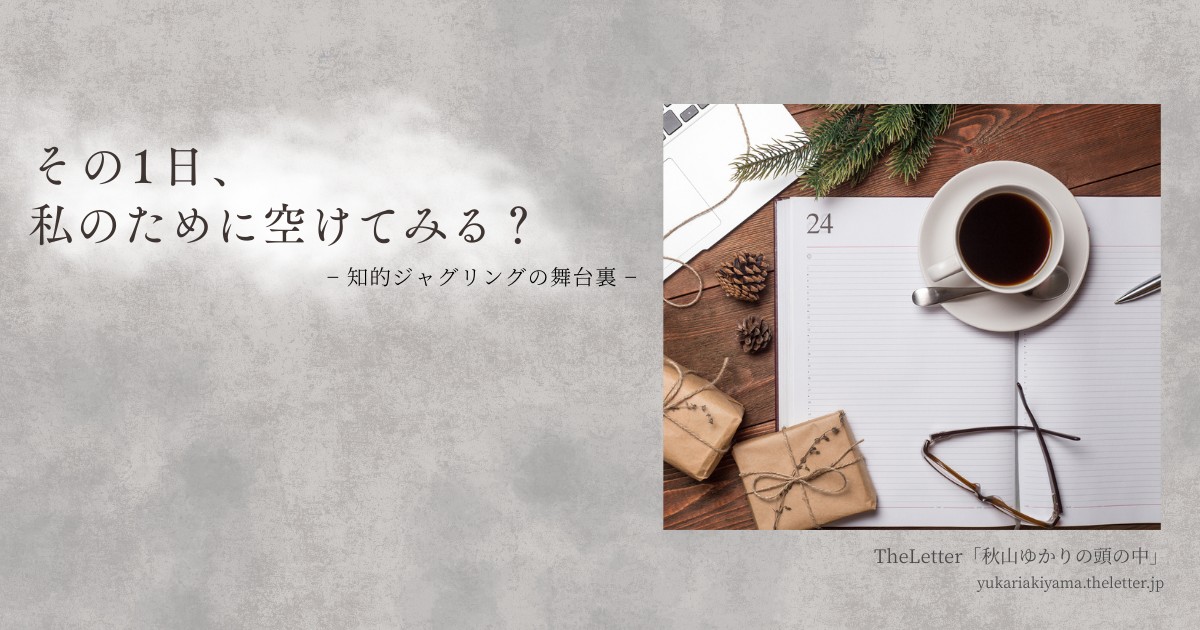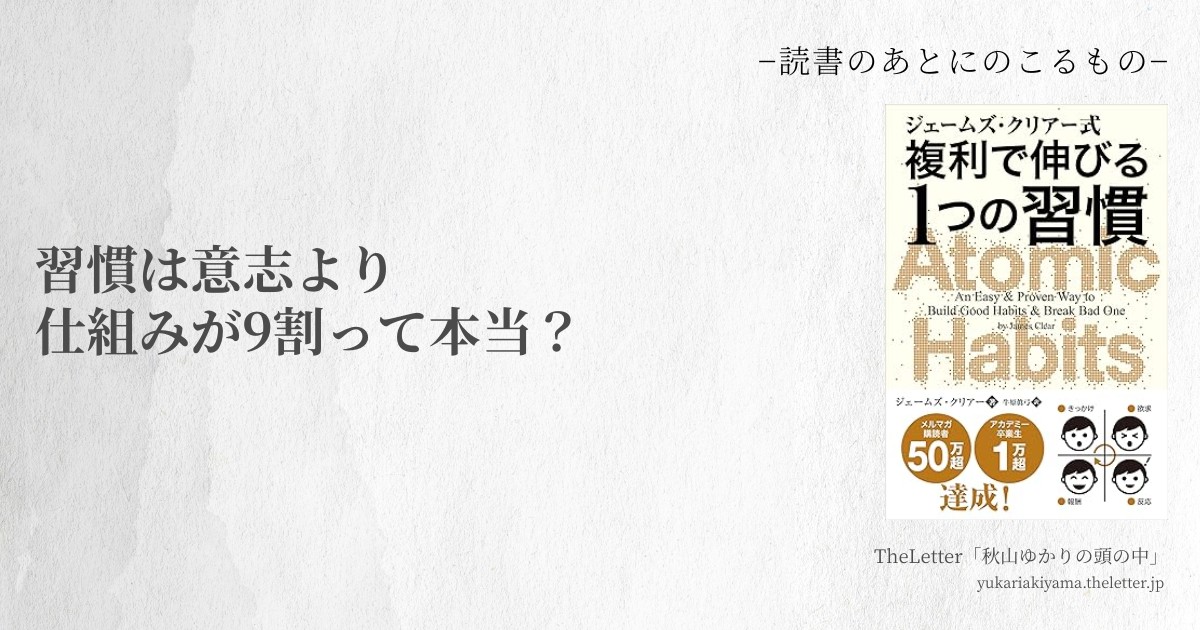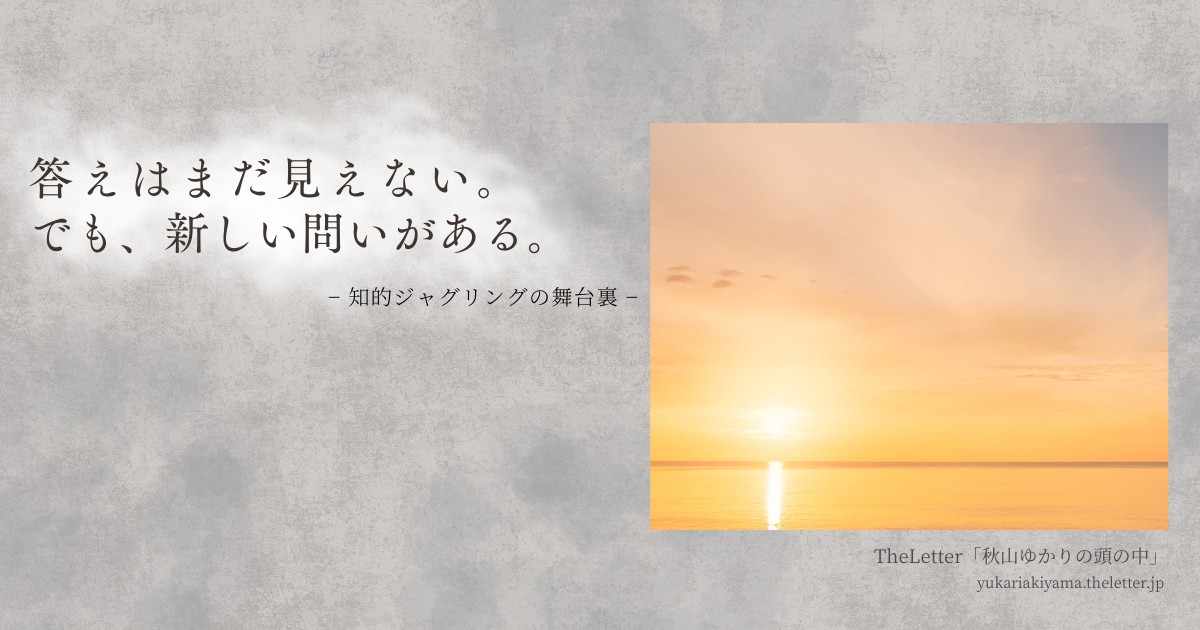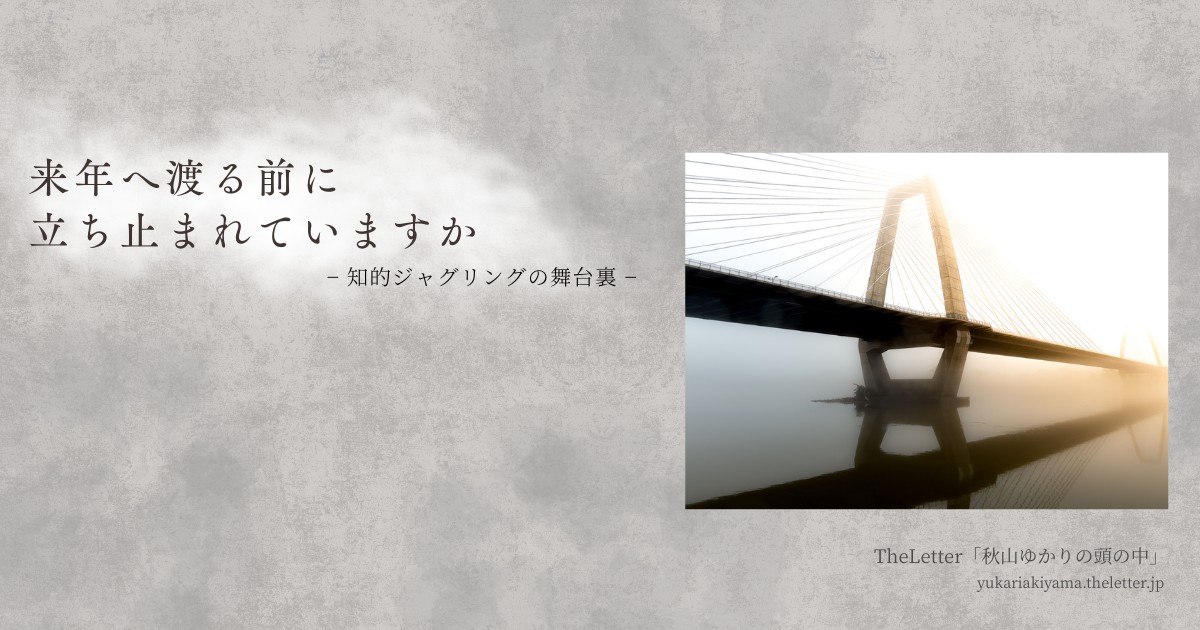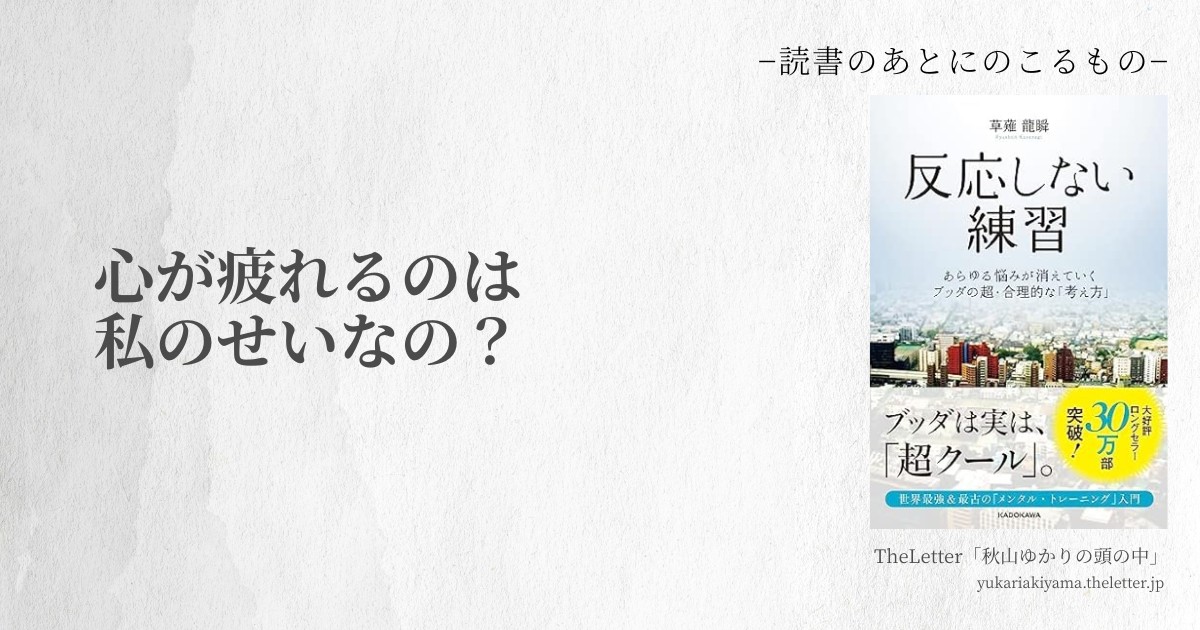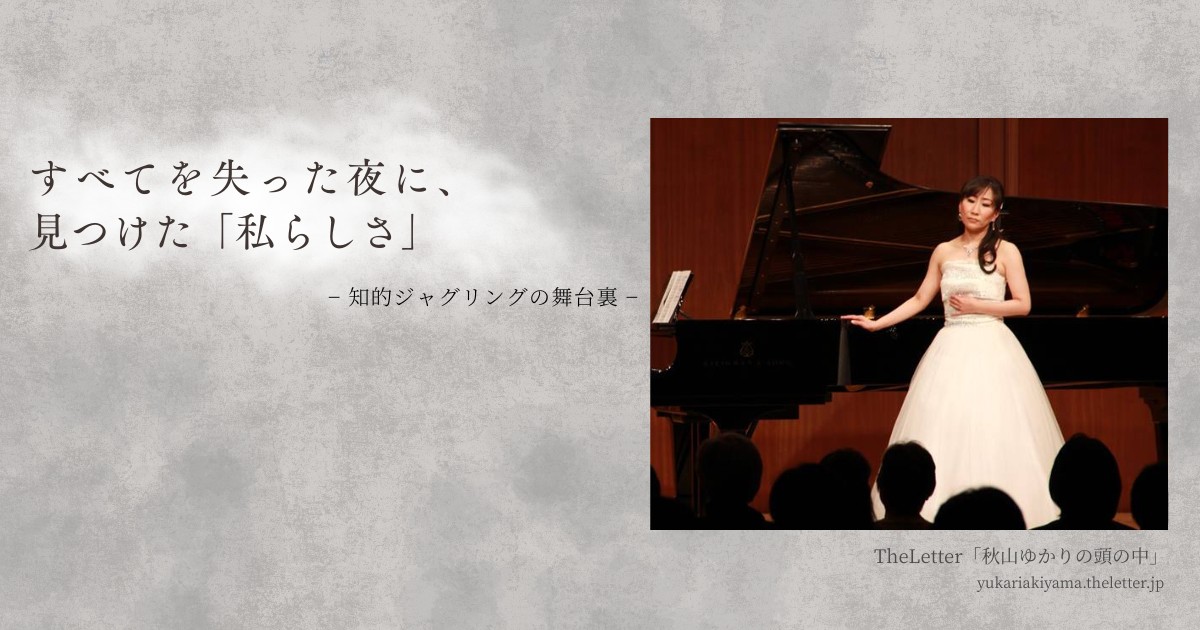“政治に無関心”な親でいいのか?——『だから、日本の政治はつまらない』を読んで
戦略コンサル、グローバル企業での事業開発、エグゼクティブの実務に加え、アーティスト・研究者・母の視点から発信しています。無料記事はサポートメンバーの支えで成り立っています。共感いただけた方は、ぜひご参加ください。
あなたは自分の子どもたちに、どんな日本を残したいですか?
教育費の負担に悩み、働き方改革が進まない職場で疲弊し、将来の年金に不安を抱く——そんな日常を送りながら、「でも政治の話は難しいし...」と遠ざけていませんか?
実は、子どもの未来を真剣に考えれば考えるほど、政治と無縁でいることは難しくなります。教育制度、労働環境、社会保障、そして国際情勢への対応。これらすべてが、政治の選択によって決まるからです。
政治を避けてきたあなたにこそ、今回お伝えしたいことがあります。なぜ日本の政治は「つまらない」と感じられるのか。その構造的な理由と、それでも私たちにできることについて、2冊の本を通じて考えてみませんか。
日本政治の「閉塞感」はどこから来るの
都議選の数日前、私は一冊の本に出会いました。グットマン・ティエリー氏とグットマン・佳子氏による『だから、日本の政治はつまらない:フランスとの比較でみる日本政治の構造的欠陥』。このタイトルに、「そうそう、まさにそれ!」と膝を打ったのです。
この本が明らかにするのは、日本の政治が「つまらない」のは偶然ではなく、構造的な問題があるということです。その最大の要因が、公職選挙法という「世にも奇妙な謎ルール」です。
まず、異常に複雑で曖昧な選挙ルール。 公職選挙法は「究極の"べからず法"」と呼ばれるほど細かく、しかも解釈が曖昧です。例えば、候補者の名前入りタスキを身につけることは違反ですが、名前のないタスキなら問題ありません。しかし、どこまでが「名前」でどこからが「デザイン」なのか、その境界線は不明確です。このような細かすぎるルールが無数にあり、新しい人が政治活動を始めようとすると、まずこの複雑さに圧倒されてしまいます。法律の専門家でさえ解釈に悩む規則を、一般の候補者が理解するのは至難の技です。
次に、たった2週間という短すぎる選挙期間。 これは現職議員や著名人に圧倒的に有利です。新しい候補者が有権者に自分の政策や人物を知ってもらうには、あまりにも短すぎます。街頭演説、戸別訪問、政策説明会——これらすべてを2週間で効果的に行うのは物理的に困難です。結果として、すでに知名度のある現職や、メディア露出の多い著名人が圧倒的に有利になります。
そして、世界一高い供託金制度。 衆議院小選挙区で300万円、参議院選挙区で300万円、比例代表で600万円という供託金は、経済的な障壁として機能し、多様なバックグラウンドを持つ人材の立候補を妨げています。しかも、一定の得票率を下回ると没収されるため、リスクは極めて高くなります。
これらの制度が組み合わさることで、いつも同じ顔ぶれ、同じ言葉、同じ空気が生まれ、国民は「どうせ変わらない」と思ってしまう。こうして「観客民主主義」という悪循環に陥っているのです。
この記事は無料で続きを読めます
- 「空気」に支配される日本の政治文化
- 日本の政治システムは世界的に見てどうなのか?
- フランスから学ぶ、「政治の面白さ」とは?
- 日本でも生まれ始めた変化の兆し
- 私が政治家を選ぶ「秋山基準」
- 候補者を見極める具体的な方法
- 「どうせ変わらない」から「どうすれば変わるか」への転換
すでに登録された方はこちら