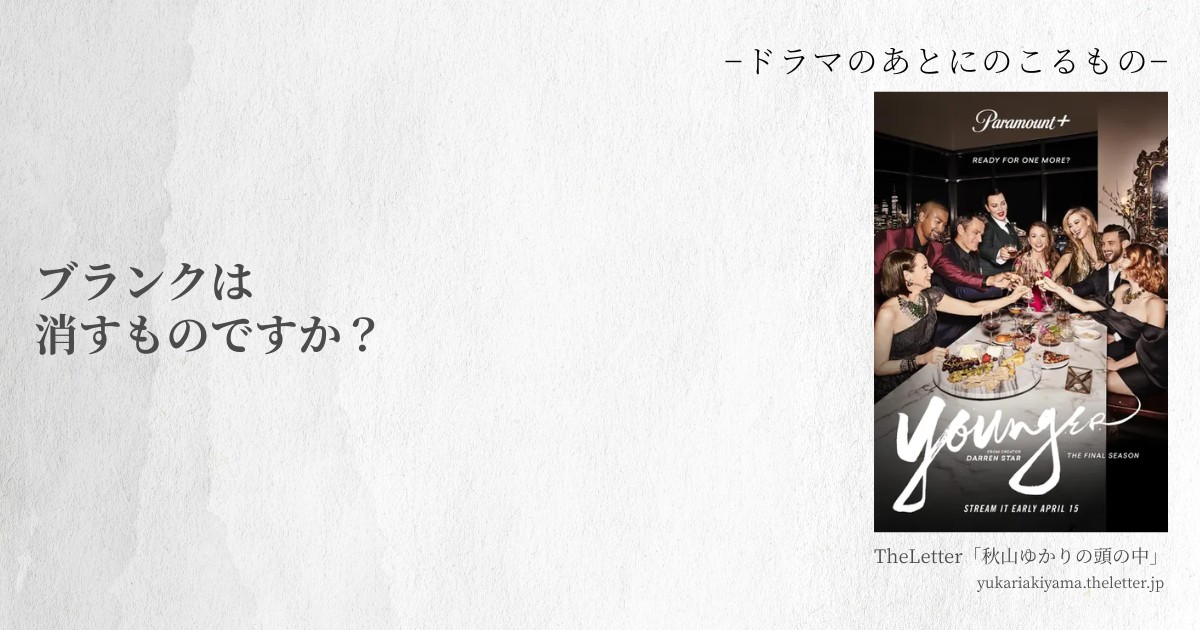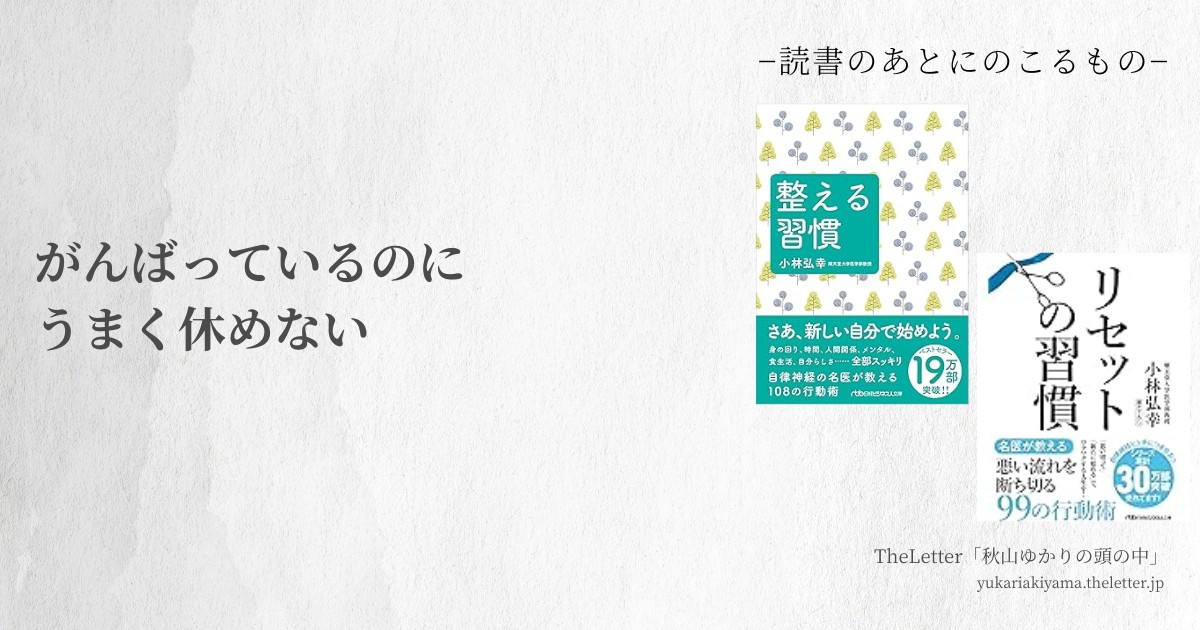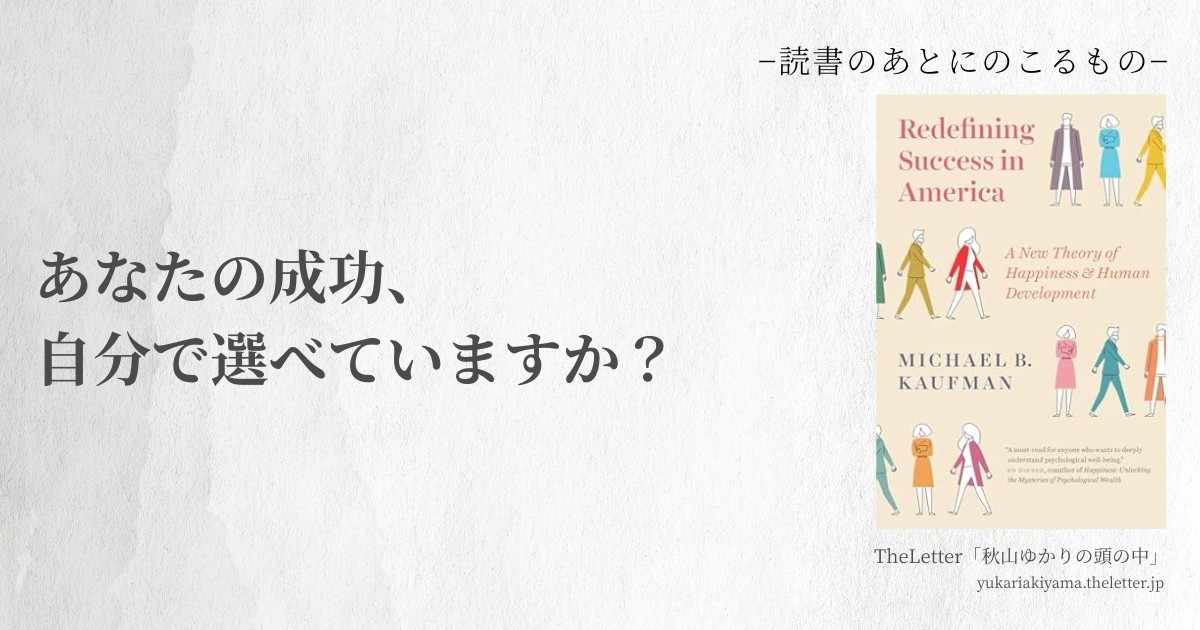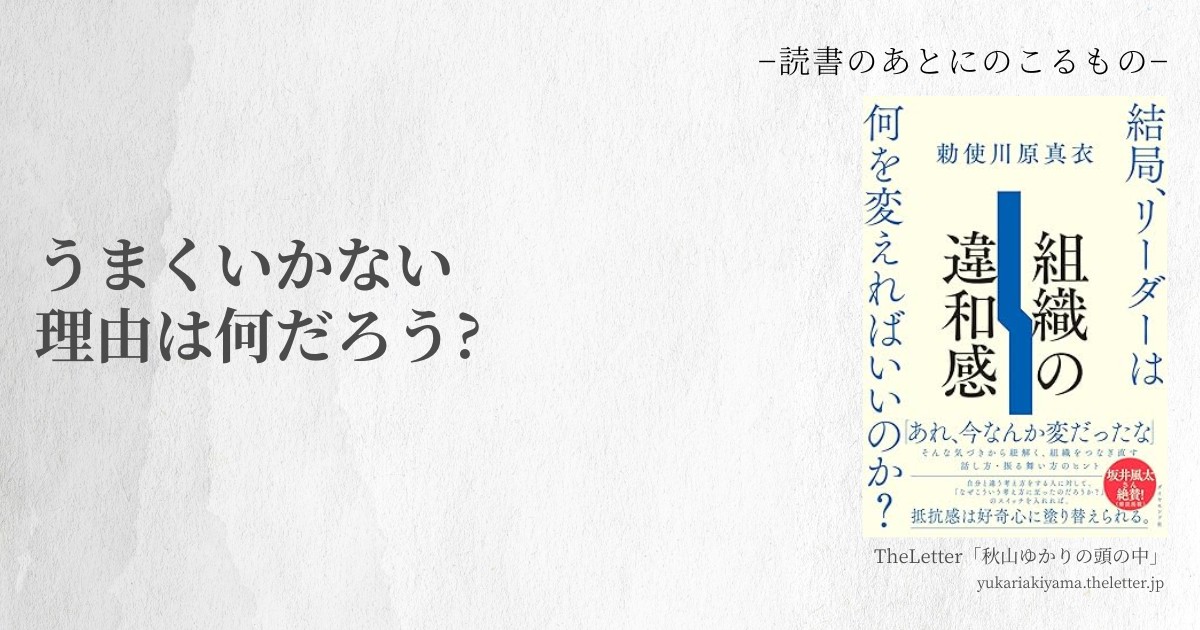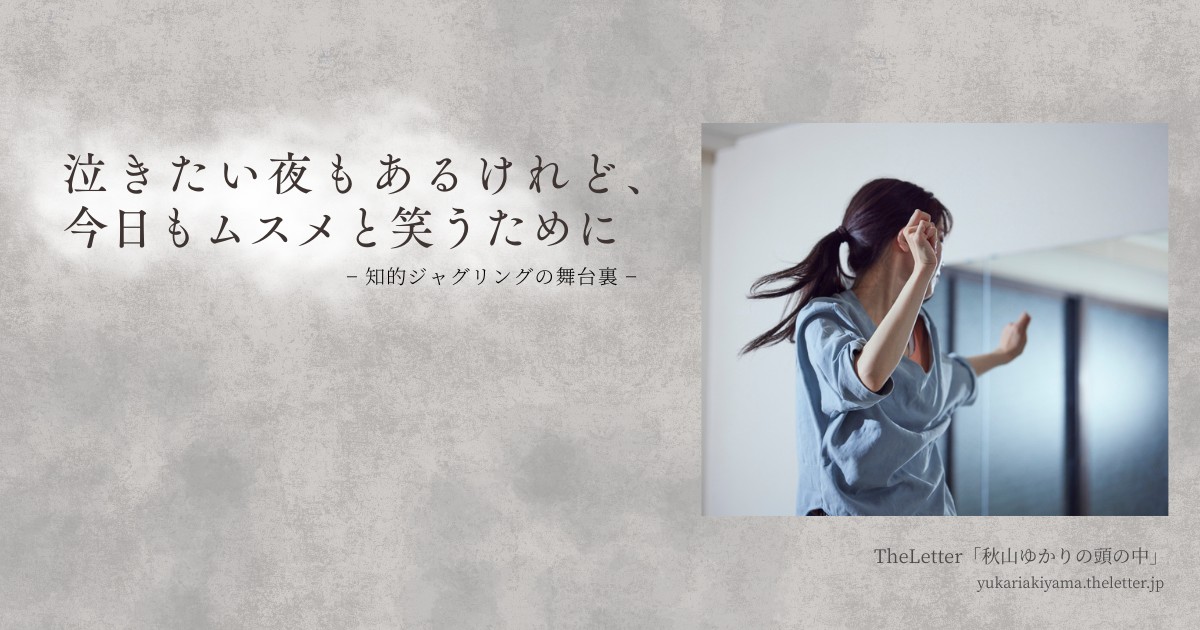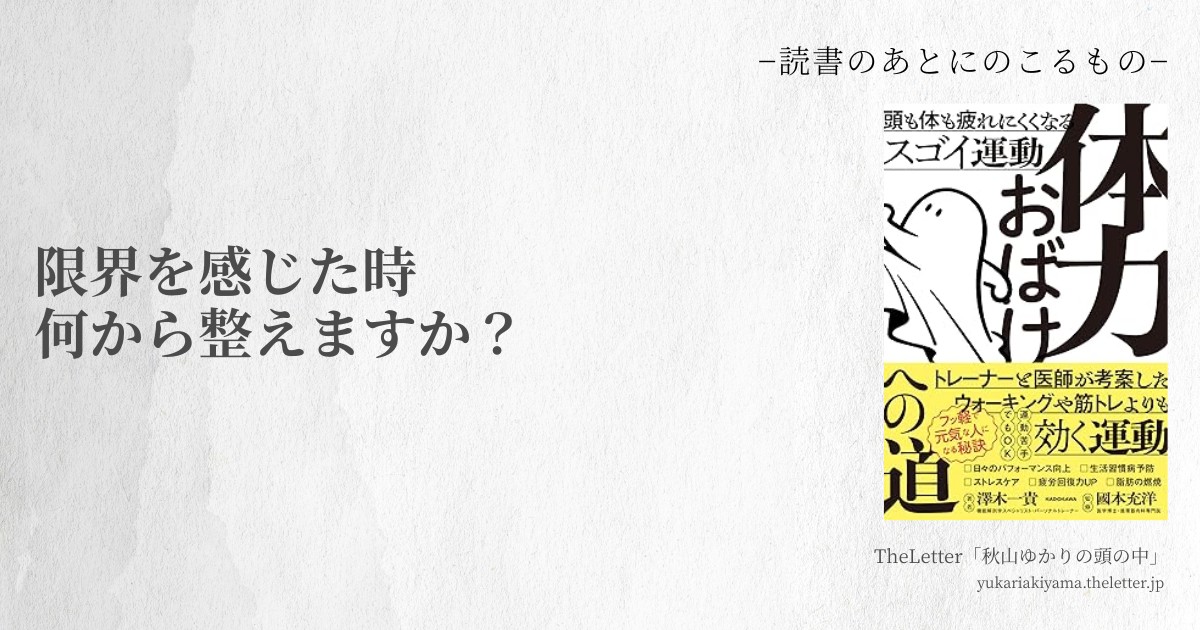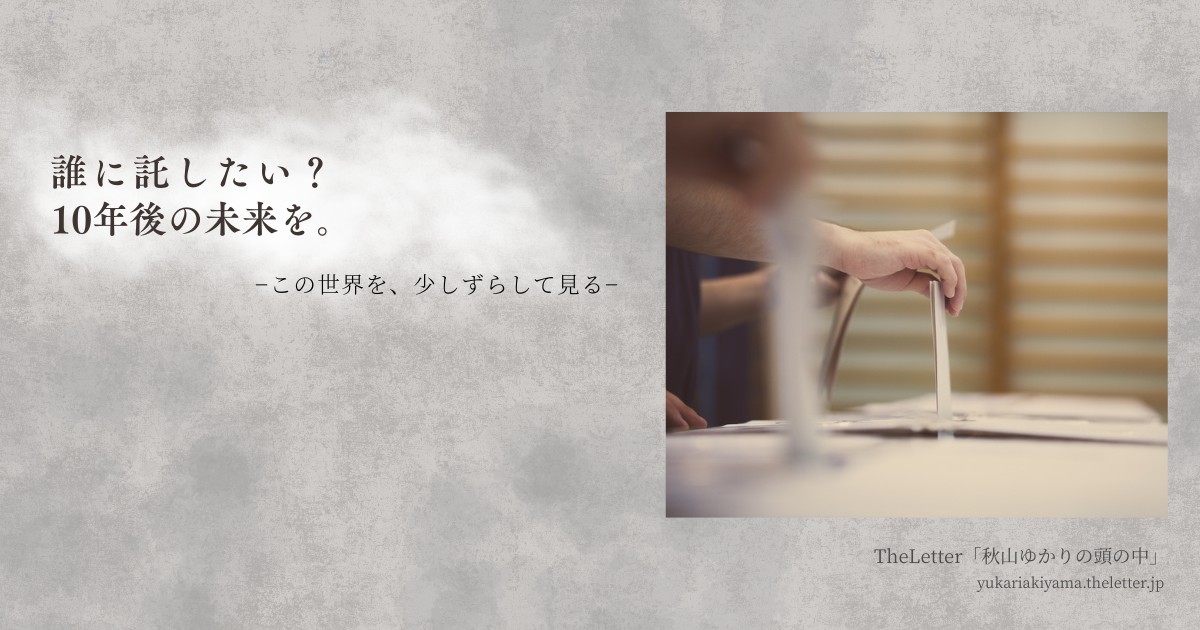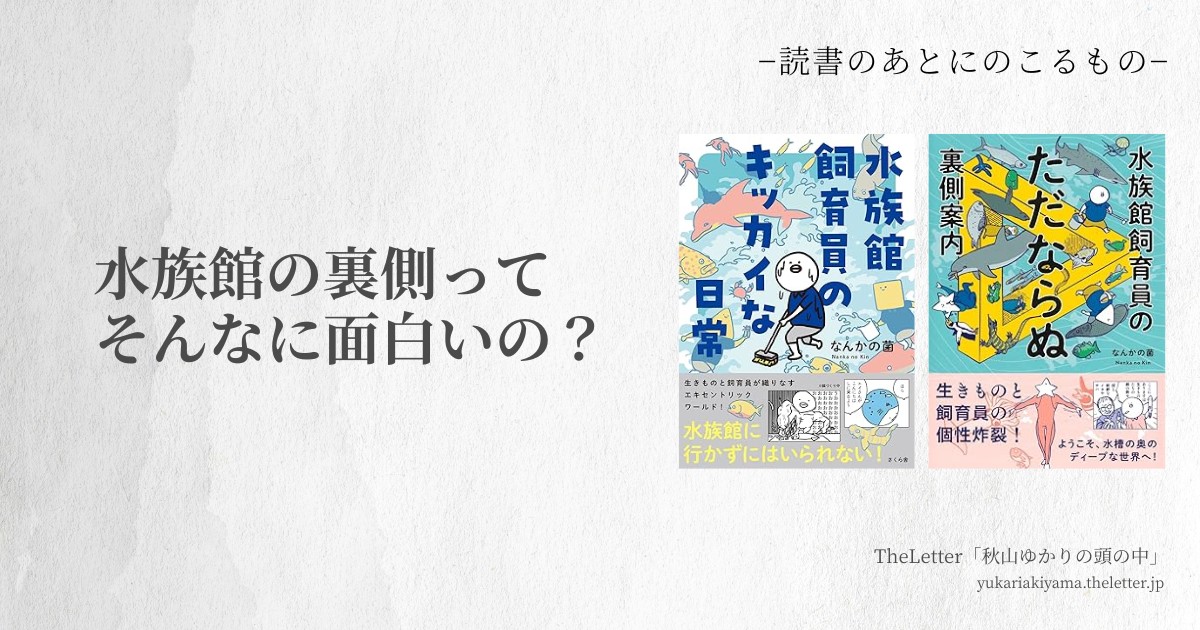職務定義書がない家庭は、ワンオペ地獄の温床だった──実録・家族を"共創チーム"に変える方法

戦略コンサル、グローバル企業での事業開発、エグゼクティブの実務に加え、アーティスト・研究者・母の視点から発信しています。無料記事はサポートメンバーの支えで成り立っています。共感いただけた方は、ぜひご参加ください。
「なぜ私だけが回してる?」その疑問に答えるのが、家庭の役割設計です。
「何をすればいいかわからない」
「いつも私が全部考えている」
このすれ違いの根本原因は、家庭内の「ジョブディスクリプション(職務定義書)」が存在しないことにあります。
前回は「子育てを究極の人材開発ベンチャー」と捉え、家庭組織の成長ステージや部門設計について考えました。今回は、さらに踏み込んで「家庭内の業務を誰がどこまで担うのか」という役割の明確化に焦点を当てます。
“家事育児”って何職あるか知ってる?──専門職の集合体を見える化する
家事育児とは、実は複数の「職種」の集合体です。
シンクの水漏れを直すとき、私たちは何気なく「水道工事の専門職」の仕事をしています。子どもが熱を出したとき、「看護師」「薬剤師」「栄養士」の役割を担っています。心の傷をケアするとき、「カウンセラー」の技能が求められます。
にもかかわらず、これらの多種多様な専門職が「家事育児」という言葉に一括りにされ、しかも「やって当たり前」と思われがちなのです。
企業なら、専門職域ごとに職務内容が明確化され、責任と権限、必要スキル、評価基準までもが文書化されています。しかし家庭では、これらが曖昧なまま「誰かがやるだろう」状態になっているケースが多いのではないでしょうか。
また、この家事育児は、子どもの成長ステージによっても、必要なものが変わってきます。そのタイミングで職務内容のアップデートができているかも、大事なポイントとなってくるでしょう。
この記事は無料で続きを読めます
- 家庭経営にもフェーズがある──子どもの成長に合わせて“親の役割”をアップデートする
- 我が家の“家庭ターンアラウンド”の舞台裏
- 数字で話せば夫が動く──KPIが育児改革のスイッチになる
- 「何をどこまでやるか」を明文化すれば、“うちは手伝ってる”が終わる
- 子どもも夫も育つ「失敗レポート」──責めずに仕組みで直す方法
- 家族の方針は2人で握る──“育児は夫婦の共同経営”という視点
- まずは棚卸しから──家庭の“職務定義書”をつくる3ステップ
- 子どももメンバー!“戦力化”する家庭のしくみ
- “全部私がやる”をやめた日──家庭業務の明文化がもたらした5つの変化
- 家庭は最高の「共創プロジェクト」
- 今後の展開予告:「子どものスペックシートは親子で書くもの」
すでに登録された方はこちら