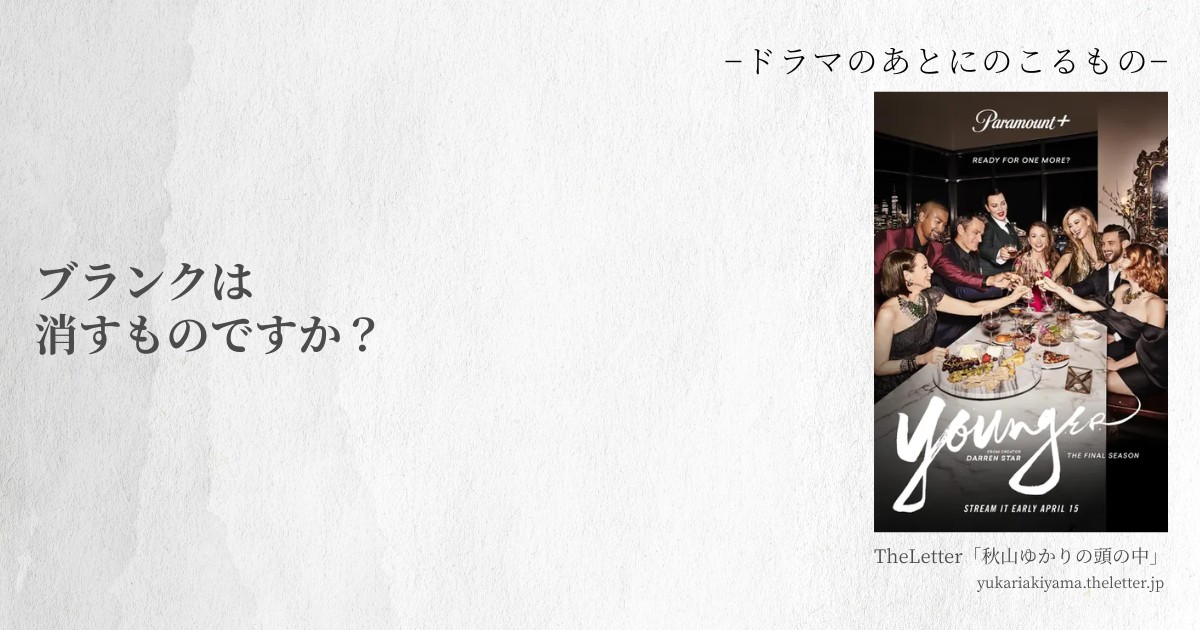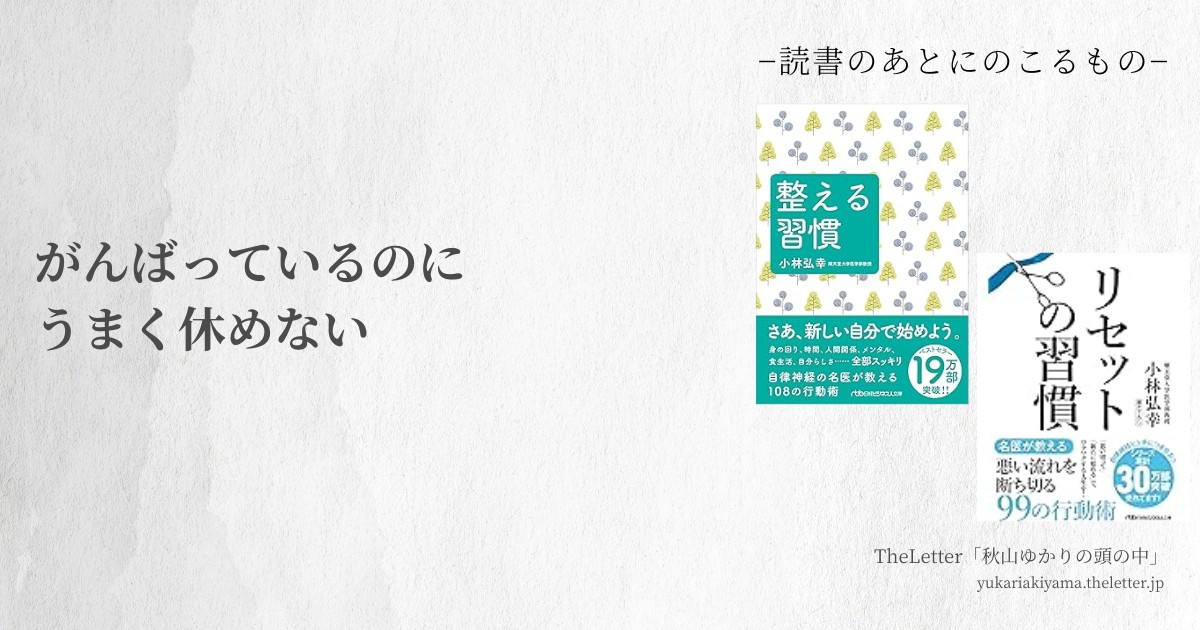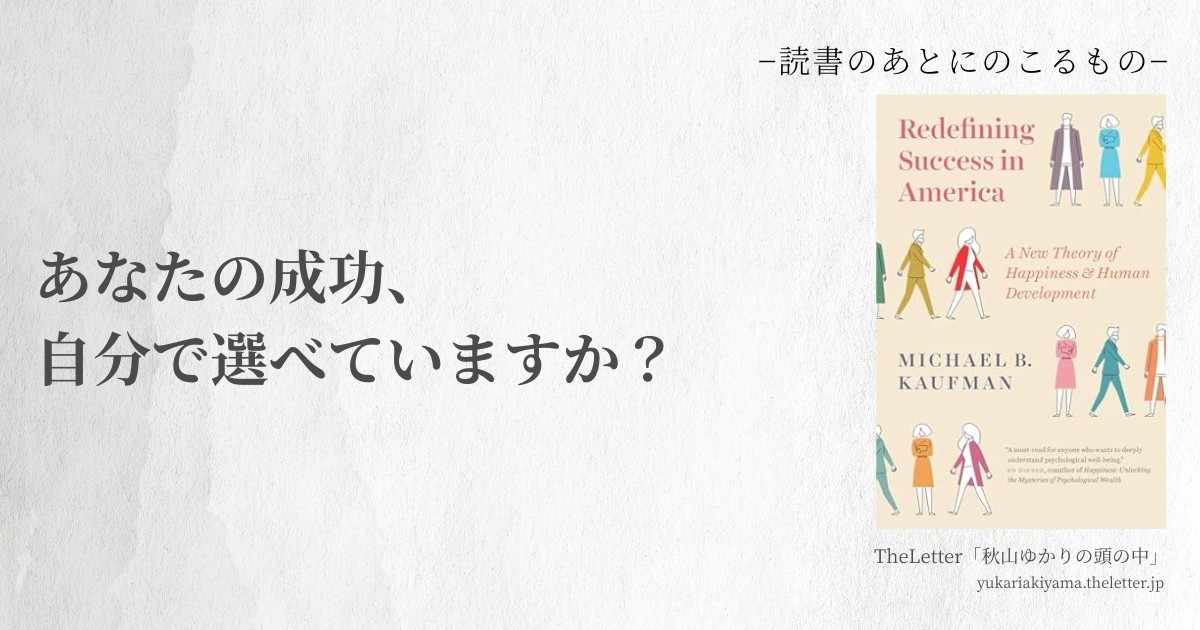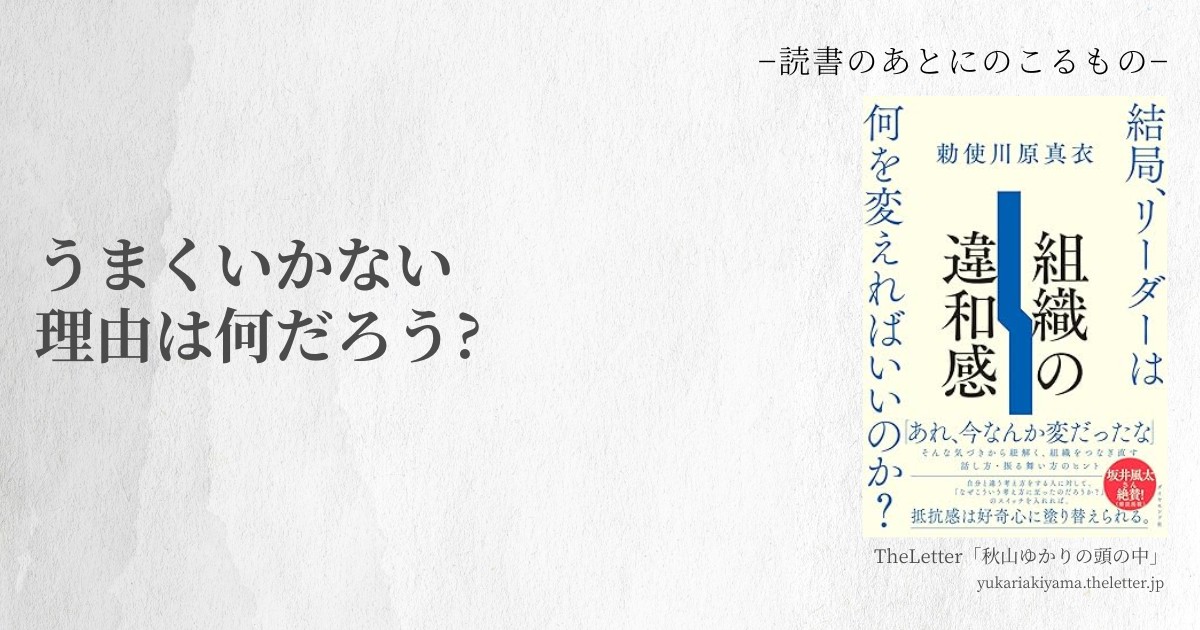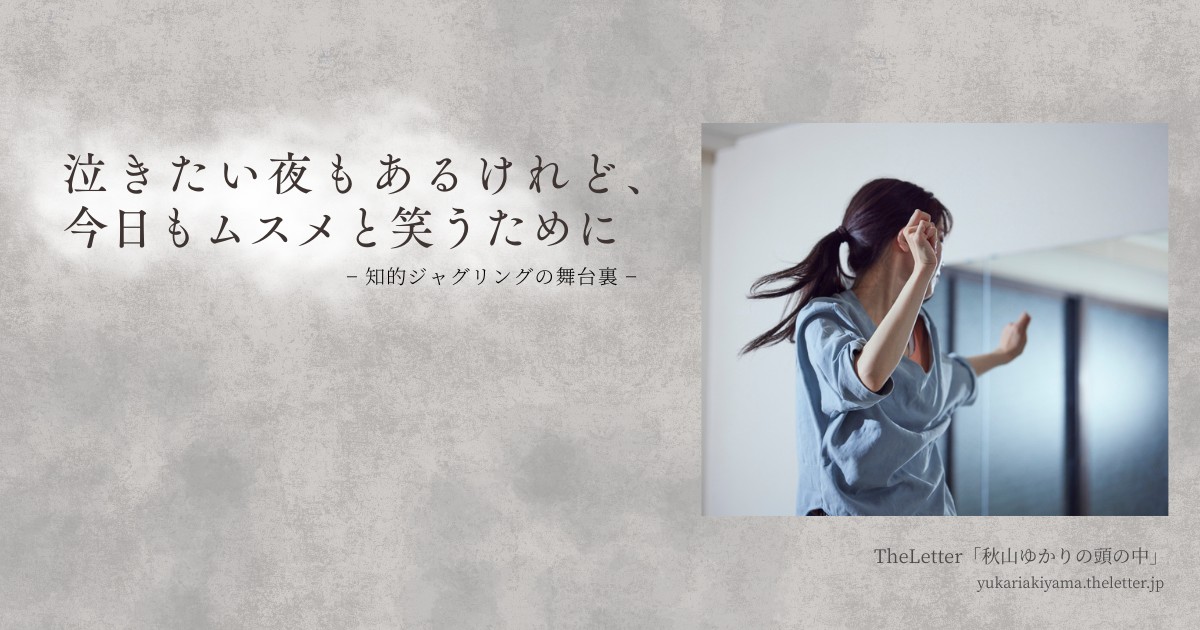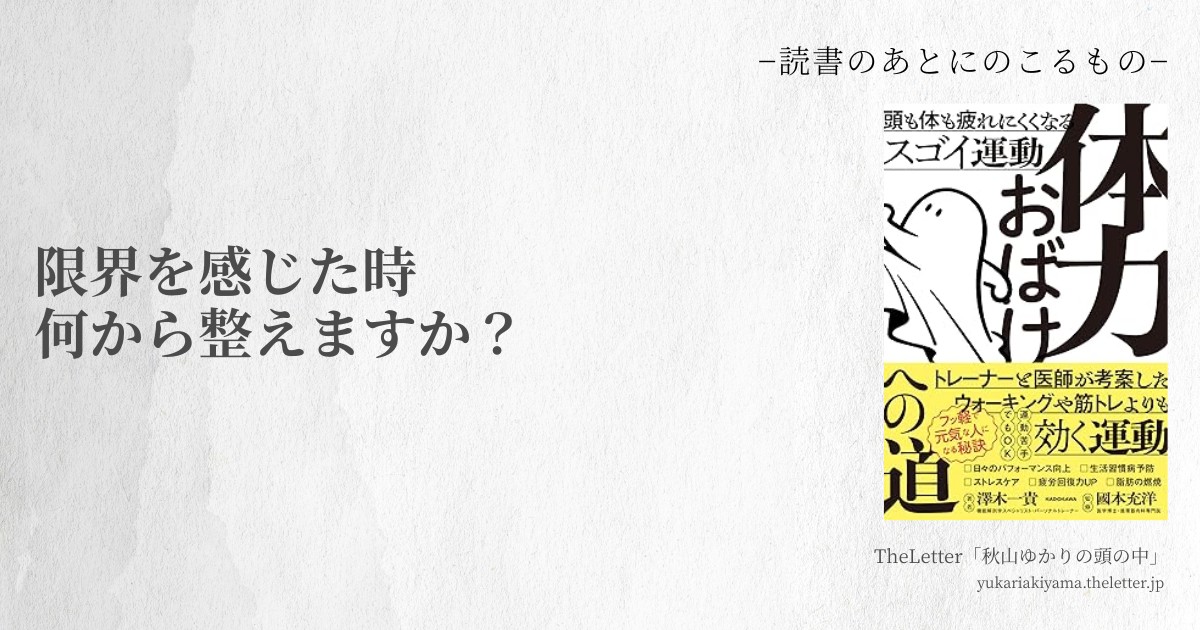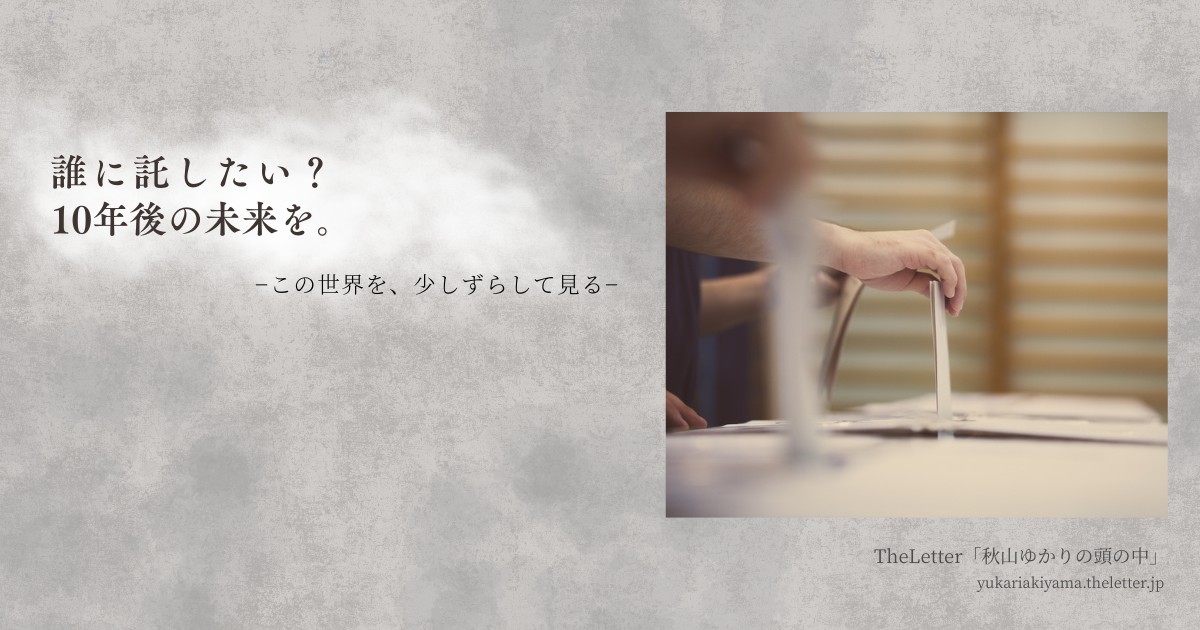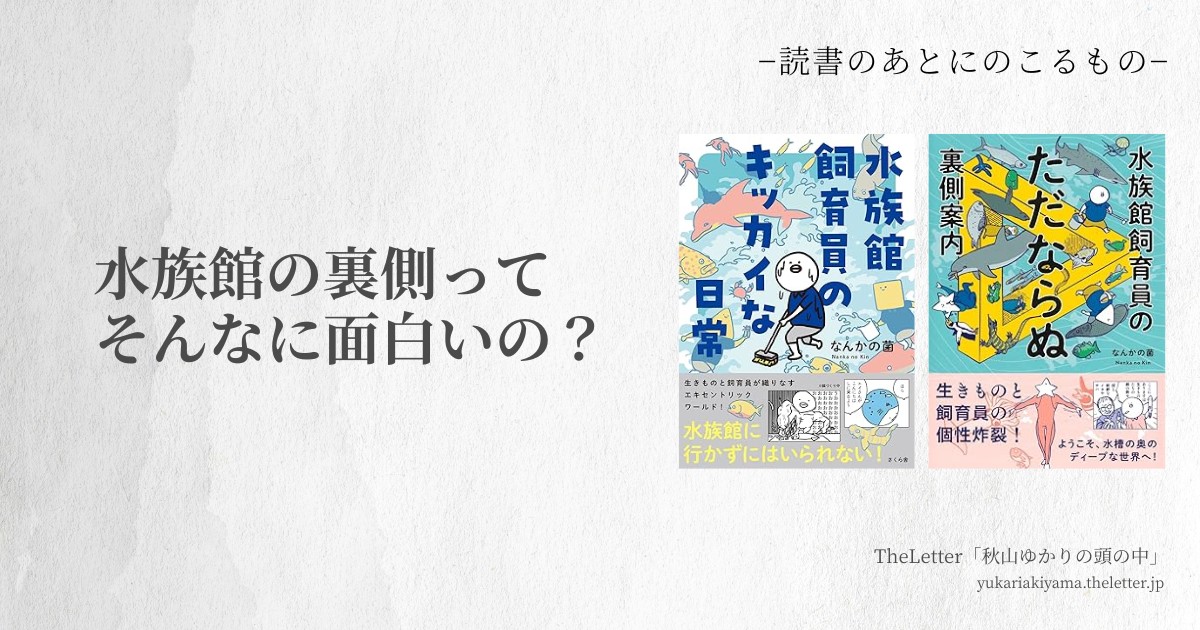「話してるのに、なぜ決まらない?」——家族を動かす15分ミーティングの技術
戦略コンサル、グローバル企業での事業開発、エグゼクティブの実務に加え、アーティスト・研究者・母の視点から発信しています。無料記事はサポートメンバーの支えで成り立っています。共感いただけた方は、ぜひご参加ください。
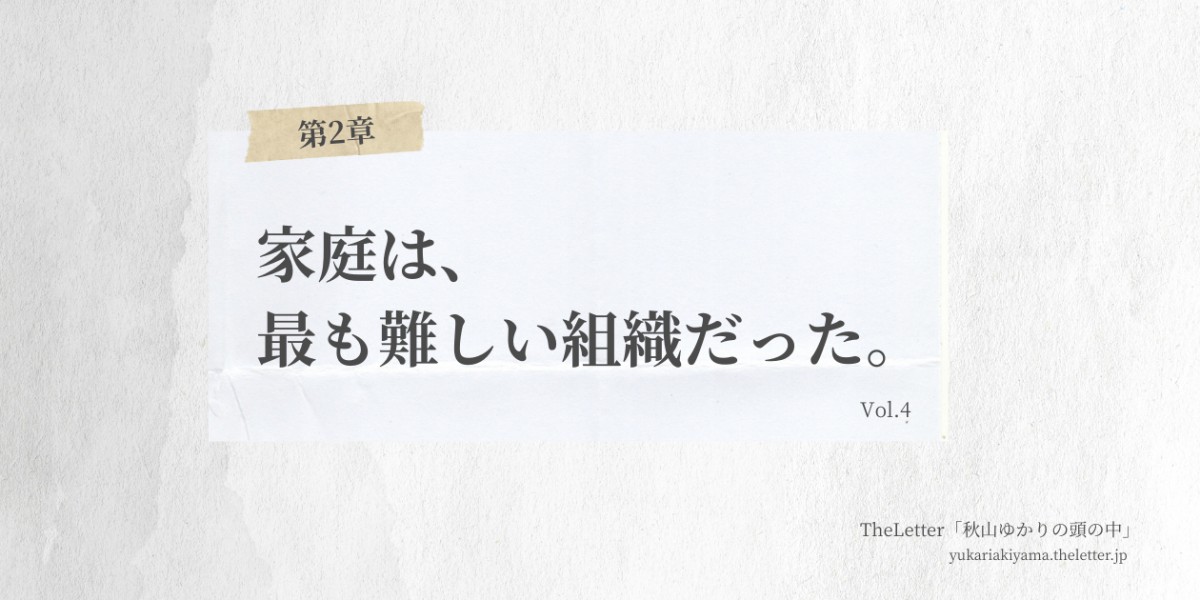
「話し合いはしているんです。でも、なぜか何も変わらない」
そんな声を、よく聞きます。
私たち夫婦も同じでした。娘の通級指導に関する温度差で大きく衝突したとき、お互いの思いは伝わっているはずなのに、「じゃあどうするか」が決まらない。
娘が通級の先生との間で価値観のすれ違いを感じ、2時間以上泣き続けた夜のこと。私が先生へのレターを作成し、夫に添削を依頼したところから事態は悪化しました。夫は「学校がイヤという表現は入れる必要がない」と主張し、私は娘の本音をありのまま伝えることの重要性を訴える。感情の共有はできても、実行に結びつかないもどかしさを抱えていました。
つい最近も、ムスメが「どうしても中学受験したい」と言い出したとき、似たような状況になりました。夫も私も「別に今めちゃくちゃがんばって勉強して中学受験しなくってもいいんじゃないの?あなたの良さが消えてしまうよ」と反対。しかしムスメの意志は固く、8月末の入塾テストに向けて猛勉強を始めたのです。
でも、そこはしょせん10歳児。自分の想いは空回りします。1万5千円分のドリルを積み上げて1か月強でこなすメニューを作っても、学校でまだ習っていないものはやり方がわからず途方に暮れるだけ。親にやり方を聞こうとしても、どうしてもわがままになってしまって、突然「学校で習ってないもん」と泣き出す始末。
そして夫は「塾に受からないなら受験勉強したって受からない!」と極論を言って、ムスメをさらに号泣させてしまいました。
「私たちはちゃんと話している」そう思っていたけれど、実際には話しているようで話していなかった。感情のぶつけ合いはあっても、「では明日から何をどう変えるのか」という具体的な合意形成には至らない。この状況が続くと、話し合うこと自体が疲れる作業になってしまいます。
それは「会話」ではなく、「合意形成」の仕組みがないからかもしれません。企業なら当たり前にある意思決定プロセスが、家庭には存在していなかったのです。
家庭に必要なのは、感情を受け止めながらも、確実に前に進める意思決定のプロセス。そこで私たちが導入したのが、15分間の「ファミリーミーティング」でした。
このミーティングを通じて、私たちの家族は確実に変わりました。中学受験問題も、感情的な対立から建設的な解決策へと導くことができました。そして先日、ムスメが顔面から転倒して目を強打したときは、夫が迷わず「自分も行く」と言い、15分後には救急外来で合流していたのです。今まででは考えられない変化です。
この記事は無料で続きを読めます
- ファミリーミーティングは"戦略的設計"でまわす
- 家庭こそ"アジャイルマネジメント"が生きる場所
- スプリントのような短時間集中
- ロールの柔軟なシフト
- バーンアウトを防ぐためのリソース判断
- クライシスモード:緊急時の意思決定プロセス
- 誰でも始められる「15分ミーティング」実践テンプレート
- 「話し合った」ではなく「動き出せた」をゴールにする
すでに登録された方はこちら