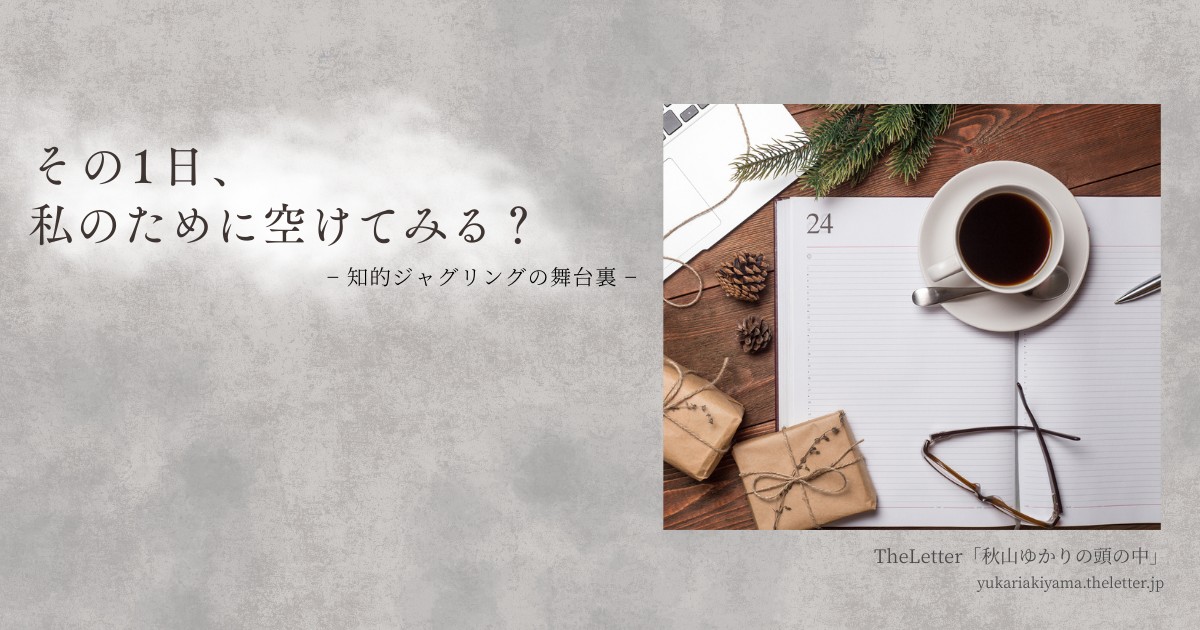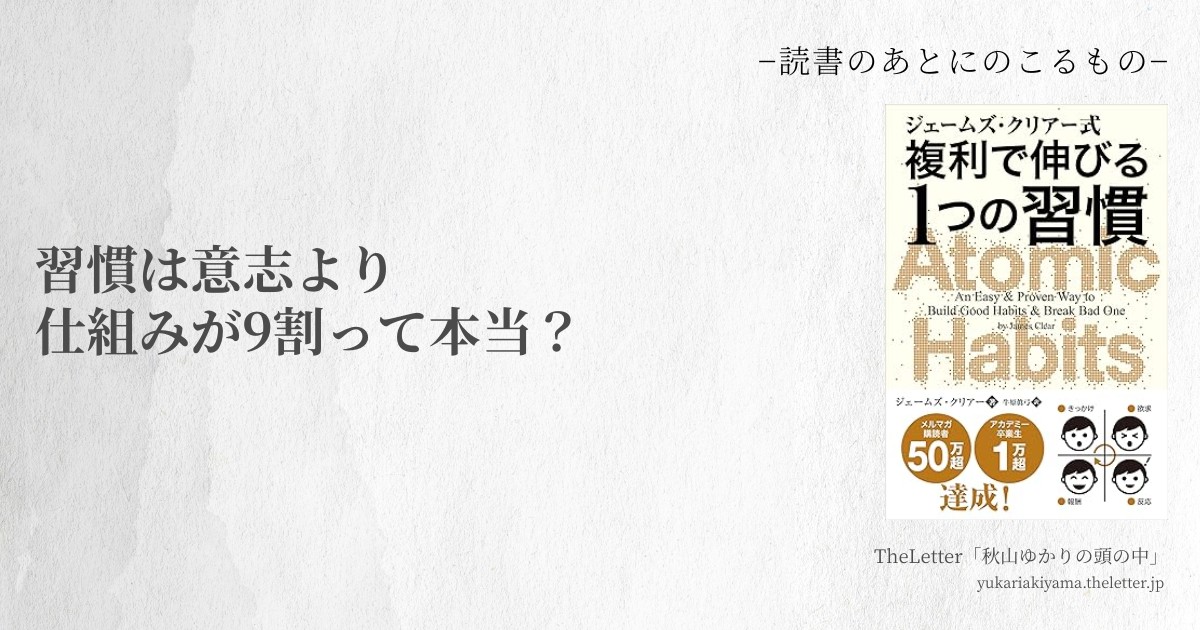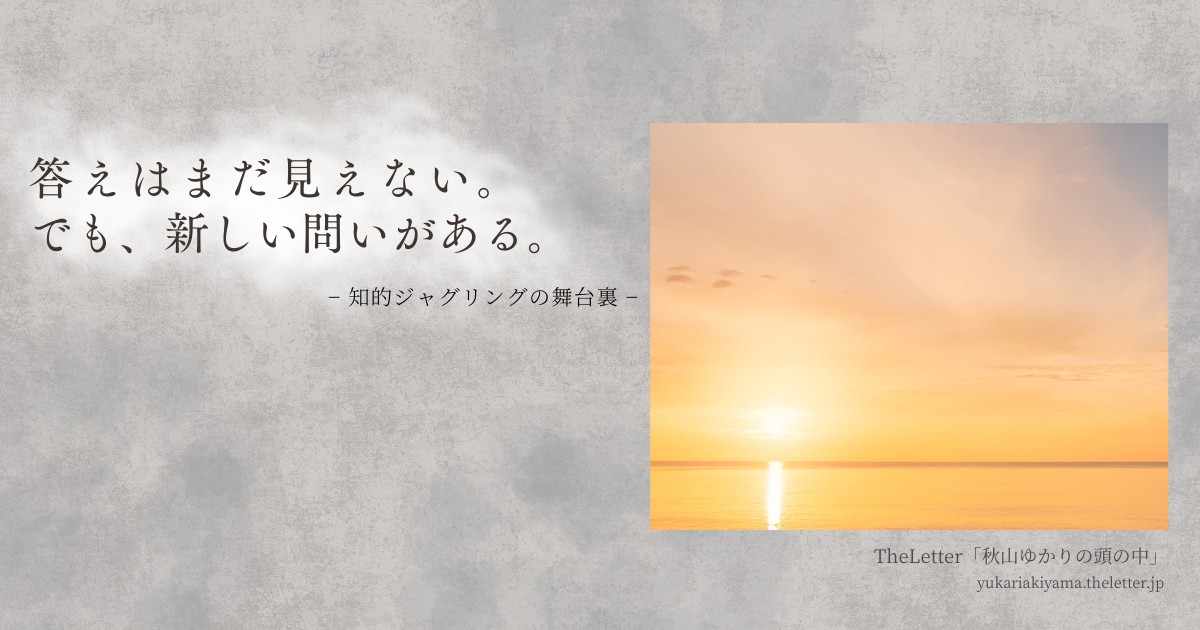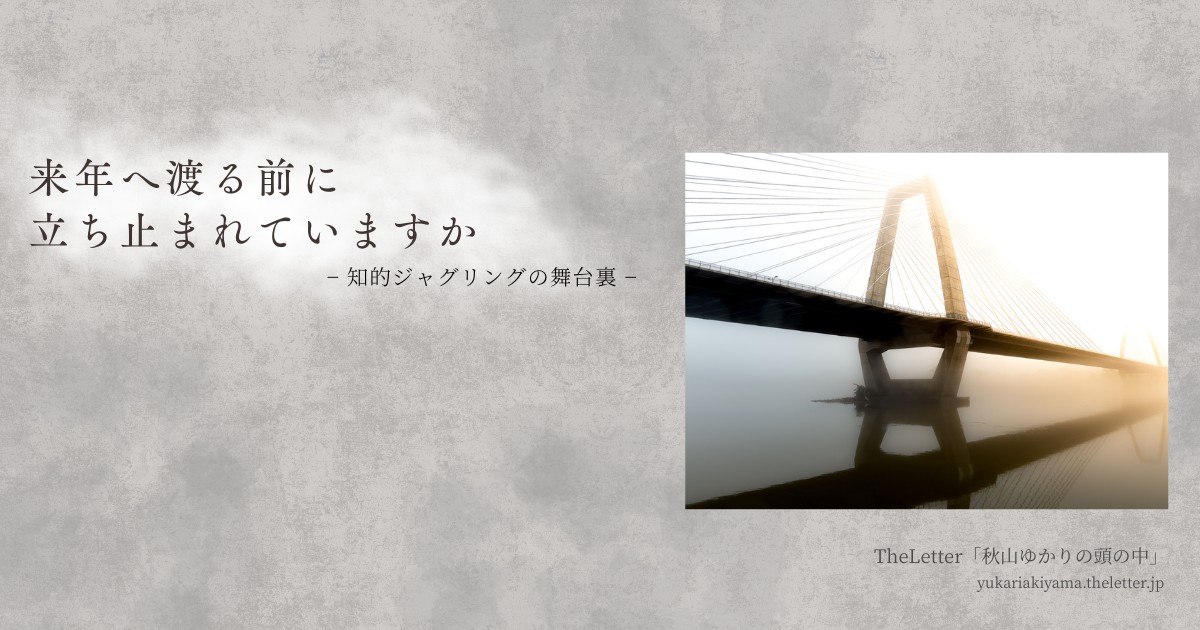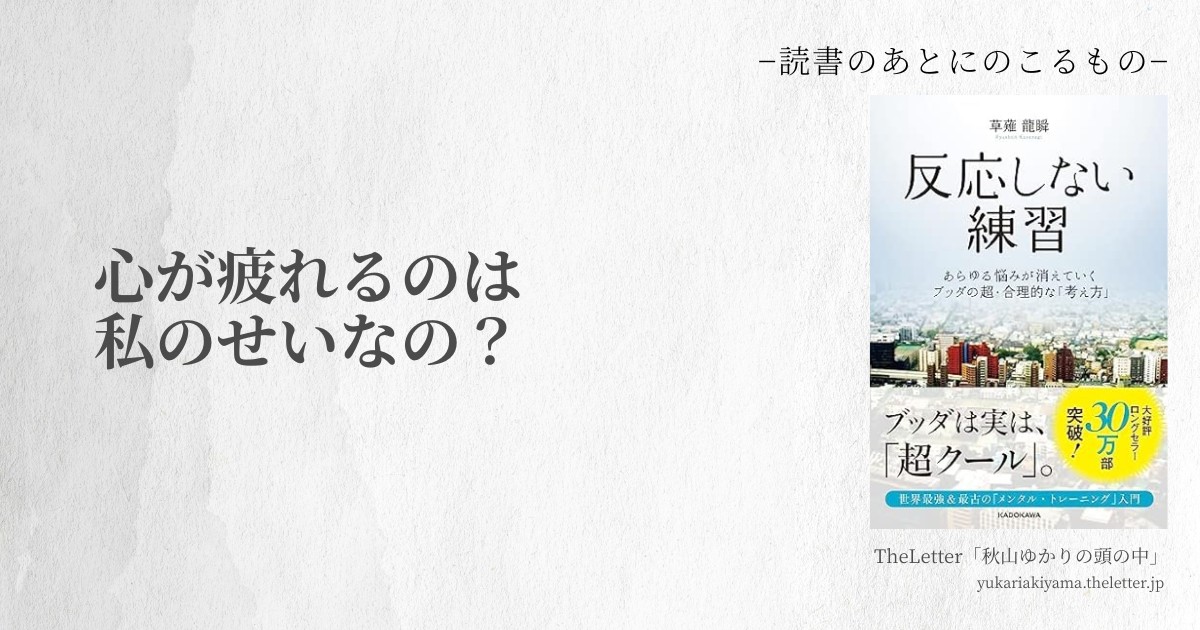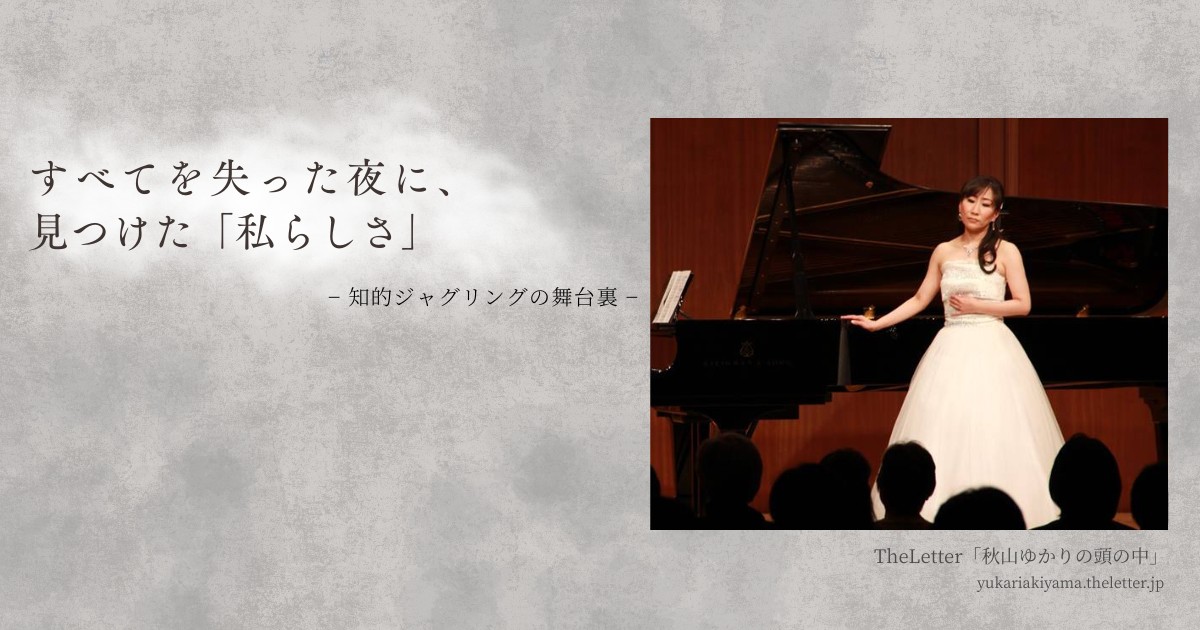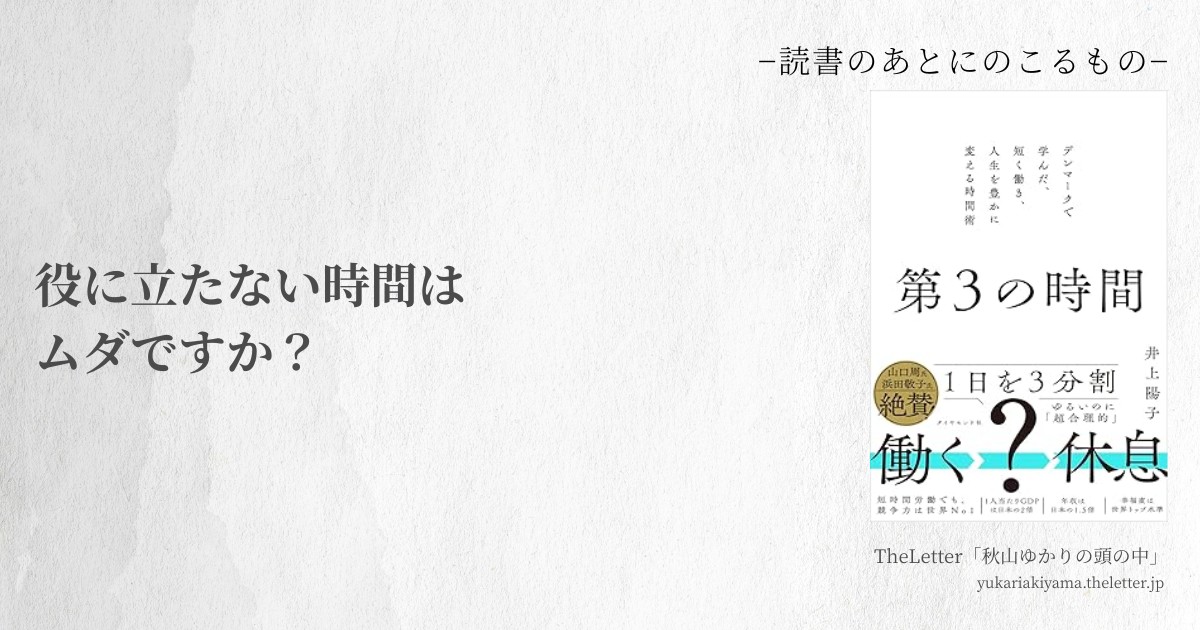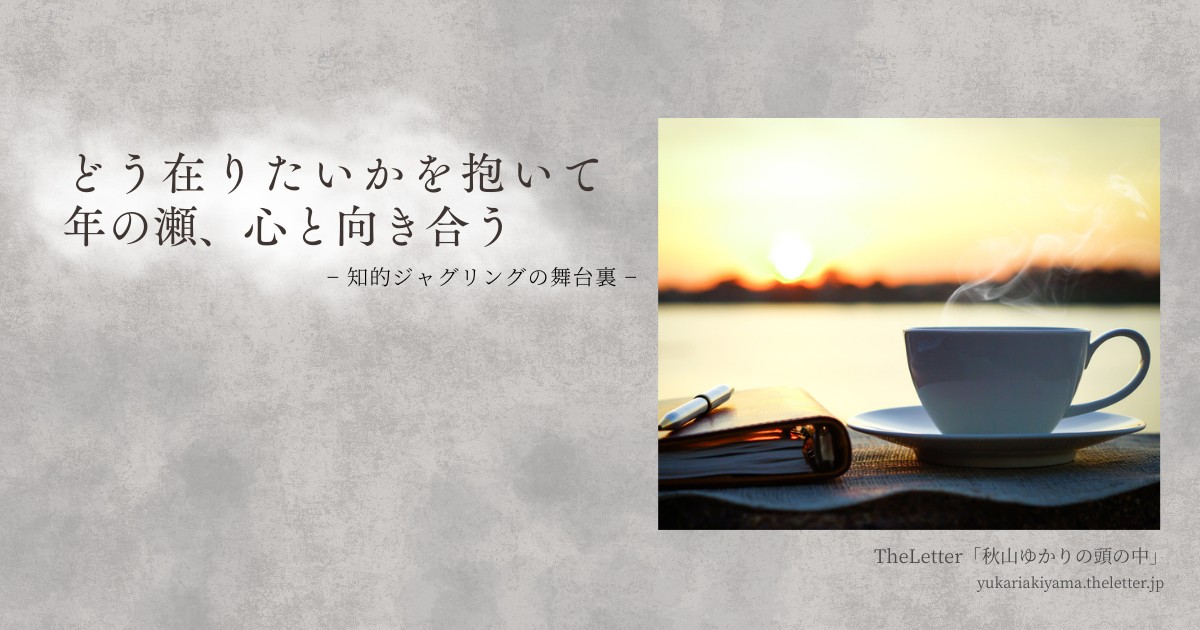クワガタ娘が夢中になった『恐竜本』──GWに親子で“研究者ごっこ”しませんか?
「好き」が広がり、やがて探究心に変わっていく——。
親子で楽しむ知の冒険、その始まりの記録です。
戦略コンサル、グローバル企業での事業開発、エグゼクティブの実務に加え、アーティスト・研究者・母の視点から発信しています。
無料記事はサポートメンバーの支えで成り立っています。共感いただけた方は、ぜひご参加ください。
GWが近づくと、どこか心がそわそわしてきますよね。せっかくの連休、家族でおでかけ?それとも自宅でのんびり読書?今回は、そんな大型連休にぴったりな「親子で楽しめる本」をご紹介します。
本のタイトルは、土屋健さん著『基本から「なぜ?」まですっきり理解できる 古生物超入門』。
一見すると、小学生男子が好みそうな「恐竜・化石」ジャンルの本ですが、侮るなかれ。私はこの本を、9歳のムスメと一緒に読みました。そして、思いがけず深い学びと発見の時間になったのです。
“なんで?”に本気で答えてくれる、親子のための探究入門
『基本から「なぜ?」まですっきり理解できる 古生物超入門』は、一見すると派手な図鑑のような装いではありません。
きらびやかなイラストやキャッチーな構成ではなく、あくまで「読み物」として、じっくりと古生物の世界へと誘ってくれる本です。
全5章、約30のトピックを通じて、古生物学の基本から最新の研究視点までが、驚くほどコンパクトに、そして丁寧に語られています。
一つひとつのトピックが短くまとまっているので、子どもと一緒に少しずつ読み進めるのにもぴったり。読み終えるたびに「へぇ、そうなんだ!」と話し合える構成になっていて、親子の対話が自然と生まれる本なのです。
第1章では「古生物学とは何か」という基本から始まり、考古学との違いといった初心者がつまずきがちな点も丁寧に説明されています。第2章では「化石はどうできるのか」「なぜすべての生物が化石になるわけではないのか」など、子どもの「なぜ?」をとことん掘り下げてくれます。
特に印象に残ったのは、「ざんねんな古生物なんていない」という視点。私たちが現代の価値観で生物を勝手に“評価”してしまうことへの、やさしく鋭い問いかけです。ムスメはこの部分を読んで、「クワガタも、ちゃんと何かの役割があって進化してきたんだよね」と、新たな目線で大好きな虫たちを見つめ直していました。
タイトル通り、「基本から『なぜ?』まで」がしっかり詰まった一冊。図鑑のように視覚で惹きつけるタイプではありませんが、「読みながら考える力を育ててくれる」点において、本書はとても優れた“知的な入門書”だと感じました。
クワガタとの出会いが、ムスメの世界を変えた
うちのムスメは、恐竜にはあまり興味がありません。でも、「クワガタ」には目がありません。きっかけは、祖母の庭でひっくり返っていたヒラタクワガタのメス(クワコと命名)を拾ったこと。まさかそのへんにヒラタクワガタがいるとは思わず、小さめだったので、「コクワガタだよ」と教えていたのですが、どうやら違ったようで…(汗)。大事に家に持ち帰ってきたものの、クワコが家に来て3週間で亡くなった時、彼女はあまりの悲しさに吐くほど泣きました。
「クワコの代わりにはならないけれど、クワガタがすごく好きになったから、大事に育ててみたい。」
その一言から、わが家のクワガタ飼育ライフがスタート。友人からコクワガタのカップルを譲り受け、近所の公園ではノコギリクワガタを捕り、さらにはオオクワガタの幼虫まで——次第にムスメの世界は、虫かごの中から広がっていったのです。
一歩踏み出す:興味の領域を超えて
初めは正直、恐竜の本をムスメに勧めることに迷いがありました。「クワガタが好きな子に、恐竜の本は響くだろうか?」という疑問です。しかし、土屋健さんの『古生物超入門』は、単なる恐竜本ではなかったのです。
この本の魅力は、「なぜ?」という問いを大切にしていること。専門家がどのように疑問を持ち、それを解き明かしていくのか——その過程そのものに焦点を当てています。
「好き」を超えた学びの扉
「恐竜が好き」という入り口は一つにすぎません。この本は、生命の進化、地球環境の変化、科学的思考法といった普遍的なテーマに、自然と読者を誘います。
ムスメは最初、「クワガタじゃないから…」とためらっていましたが、一緒にページをめくるうちに、次第に引き込まれていきました。それは彼女が「昆虫」という限られた世界から、「生命」という広大な世界へと視野を広げる瞬間でもありました。
親子で楽しむための読書テクニック:対話が鍵
専門書や科学の本を子どもと読む際には、ちょっとした工夫が効果的です。私たちが試してみて良かった方法をご紹介します。
①「知っていることから」始める
まず、子どもがすでに知っていることや興味のあることから会話を始めます。ムスメの場合は「クワガタの体のつくりは、約1億2500万年前も前からあまり変わっていないらしいよ。最古のクワガタの化石は、中国の遼寧省から発見されたらしいよ」と話すと、目を輝かせました。自分の知識と本の内容をつなげることで、理解が深まります。
②「想像する時間」を大切に
「もし恐竜が絶滅していなかったら、今の地球はどうなっていたと思う?」といった問いかけをすると、子どもの想像力が刺激されます。正解を求めるのではなく、自由に考える楽しさを共有しましょう。
③「わからない」を共有する
親も「へぇ、これは知らなかった」「これってどういうことだろう?」と素直に疑問を口にすると、子どもも安心して「わからない」と言えるようになります。一緒に調べる姿勢が、学びの深さを作り出します。
進化と絶滅の「なぜ?」に、ムスメはワクワクした
そんなムスメが、この『古生物超入門』に食いついたのは、「研究者の視点」に触れたからでした。特に第4章「生物の進化で地球がわかる」の中に出てくる一節に、彼女は目を輝かせたのです。
「研究の最前線は、大量絶滅の原因よりも、大量絶滅の物語の細部の解明に向かいつつあります。」(p.146)
「絶滅と生存をわけた分水嶺」って、なんだろう? なぜワニは生き残り、恐竜は滅びたの? そこには、何があったの?
普段、クワガタの生態の違いに夢中になっているムスメにとって、「研究者がどんな視点で『好きなもの』を観察し、掘り下げているか」を知ることが、何より刺激になったようです。
好奇心の連鎖反応
土屋さんの本が秀逸なのは、答えをすべて提示するのではなく、「まだわかっていないこと」も正直に示している点です。これが子どもたちの好奇心に火をつけます。
「わからないことがあるなら、私が調べてみたい!」
ムスメは本を読み終えた後、図書館で昆虫の進化に関する本を探し始めました。クワガタが地球上にいつ現れたのか、大量絶滅を生き延びたのか、そんな疑問が次々と湧いてきたのです。
“自分で調べる力”が芽生えるとき
ムスメがこの本に惹かれたのは、古生物の面白さだけでなく、「どうやって調べるか」という科学的な探究のしかたにも触れられていたからでした。
第5章では、インターネットの情報、論文、サイエンスライターの記事の違いにも言及されています。
今までは、ムスメが調べものをする時は、最終的に私のところに持ってきて「これって信じていい情報?」と尋ねるのが常でした。でも、この本を読んでからは「これは誰が書いてるの?」「出典ある?」と、自分で確認しようとする姿勢が出てきたのです。
「研究者って、仮説を立てて、証拠を探して、結果を確かめるんだね。探偵みたい!」と、目を輝かせて話すムスメを見て、私は心の中でガッツポーズをしていました。
情報があふれる現代で、子どもたちに必要なのは、事実をただ暗記する力ではなく、「信頼できる情報を見分ける力」なのだと、改めて実感しました。
土屋さんの本は、まさにその第一歩を自然に促してくれる。
小学生でも「これは正しそうか?」「どうやって調べようか?」と考える視点を、親子で共有できたことは、私にとって何よりの贈り物になりました。
読書から広がる探究活動:GWにぴったりのプロジェクト
本を読んだ後は、その学びを実践に生かすアクティビティに発展させると、理解がさらに深まります。GWにぴったりの活動をいくつかご提案します。
① 自宅で化石レプリカづくり
小麦粉と塩で作る塩粘土に、貝殻やカブトムシの抜け殻などを押し付けて「化石」を作れます。乾燥させた後絵の具で着色すれば、本物さながらの化石のできあがり。本書にたくさん出てくる「化石」がどのように作られるのか、遊びながら体験できます。

② 進化のストーリーボード
大きな紙に時間軸を描き、生物の進化を絵や写真を使って視覚化します。「なぜこの時代にこの生物が現れたのか」を考えながら作業すると、環境と生物の関係性への理解が深まります。ムスメはクワガタの祖先について調べ、自分なりの「クワガタ進化図」を作成しました。
③ 科学者インタビューごっこ
親が科学者役、子どもが記者役になって、本で学んだことをインタビュー形式で復習します。役割を交代してもOK。「先生、なぜ恐竜は絶滅したのですか?」「それはですね...」と会話することで、知識が整理されていきます。
ムスメはテレビの枠を画用紙で作って、テレビに出ている風でインタビューごっこを楽しみました。
④ 地層ケーキづくり
地層の形成を理解するために、異なる色や味のゼリーを重ねた「地層ケーキ」を作ってみるのも楽しいです。各層に小さなおもちゃや果物を「化石」として埋め込めば、発掘体験も楽しめます。できあがったケーキを切り分けながら、地層の成り立ちについて話しあってみるのも楽しいですよ。
好きが「知」になり、「未来」へつながっていく
『古生物超入門』は、恐竜が好きな子どもだけの本ではありません。
むしろ、「いま好きなものを、もっと好きになる方法を教えてくれる本」なのです。
ムスメは、自分の「クワガタ愛」を研究者たちの探究姿勢と重ねていました。そして、「私は将来、クワガタ博士になれるかな?」なんて話しながら、虫かごを眺めていました。
私たち大人は、キャリアや学びを「合理的に設計」しがちです。でも、子どもたちが歩む道の原点には、たいてい「好き!」という感情があります。
それをどう広げてあげられるか。 どんな視点で世界を見せてあげられるか。 そのヒントが、こんな科学の入門書の中に詰まっているのです。
「研究者の視点」が教えてくれること
土屋さんは、他の著作に関するインタビュー等で古生物学を「探偵学」とも表現しています。断片的な化石という証拠から、失われた世界を推理していく——その謎解きのプロセスは、子どもたちの論理的思考力を自然と育みます。
ムスメはクワガタを飼い始めた時から詳細なクワガタ観察ノートをつけていたのですが、この本を読んだ後は「この種類はなぜ角が大きいんだろう?DNAを見ると違いはわかるのだろうか?」「恐竜とほぼ同時代に生きていた昆虫の末裔なのに、なぜ生き延びられてるんだろう?」と、研究者のような視点で疑問を書き留めるようになりました。
科学の本が育てる将来の選択肢
専門家が書いた科学の入り口との出会いは、子どもの将来に思いがけない影響を与えることがあります。
ムスメはこの本を読んで以来、「研究って、好きなことを深く掘り下げることなんだね」と言うようになりました。彼女の中で「クワガタが好き」という感情が、「クワガタについて研究したい」という知的探究心へと変化しつつあるのです。
子どもが「好き」を深めていくプロセスを見守ることは、親にとっても大きな学びがあります。大人の私たちは、ついつい「役に立つか?」「将来の仕事につながるか?」という視点で子どもの興味を判断しがちです。でも、純粋な好奇心こそが、創造性や粘り強さを育む土壌になることを、この読書体験を通して改めて実感しました。
子どもの「好き」を広げるには、親の“ちょっとした冒険心”が必要なのかもしれません。
『古生物超入門』は、恐竜の知識だけでなく、「知ることの喜び」「探究する姿勢」という一生の宝物を子どもに届けてくれる本です。まさに、知的冒険のパスポートともいえるでしょう。
「異分野」の本を一緒に読むという贅沢
私が強く感じたのは、「少しだけ距離のあるジャンルの本を、子どもと一緒に読む時間の贅沢さ」です。
たとえば、ムスメのように昆虫に夢中な子が、恐竜や進化、生態系に触れる。そうすると、自分の好きな領域がぐんと広がって、「世界はつながっている」と実感できるんです。
そしてそのつながりが、「学ぶこと」や「探究すること」の楽しさへと変わっていきます。
今回の読書体験は、まさにそんな"知的ジャグリング"の時間でした。
GWこそ、知的冒険の絶好のチャンス
GWは、忙しい日常から少し離れて、子どもと一緒に新しい世界に触れる絶好の機会です。
もちろん、家族旅行も素晴らしい経験になります。でも、一冊の本をきっかけに始まる知的冒険も、長い目で見れば子どもの人生を豊かにする大切な時間です。
『古生物超入門』のような良質な科学入門書は、そんな冒険の最高の道案内人になってくれます。
このGW、どこかに出かけるのもいいけれど、ちょっと立ち止まって、親子で知の冒険に出かけてみませんか?
『古生物超入門』は、そんな旅のはじまりにぴったりの一冊です。虫かごの中の小さな命から、地球の進化まで——本のページをめくるたび、世界が少しずつ広がっていきます。
きっとあなたの子どもにも、新しい「好き」が芽生える瞬間があるはずです。
🌱 読者のみなさんへ
もしこの本を読んだ親子の体験があれば、ぜひ教えてください。
このGW、あなたのお子さんの『好き』は、どんな新しい扉を開くでしょうか?
それでは、よい連休を。たくさんの知的な冒険がありますように!

戦略コンサル、グローバル企業での事業開発、エグゼクティブの実務に加え、アーティスト・研究者・母の視点から発信しています。無料記事はサポートメンバーの支えで成り立っています。共感いただけた方は、ぜひご参加ください。
すでに登録済みの方は こちら